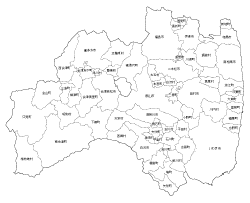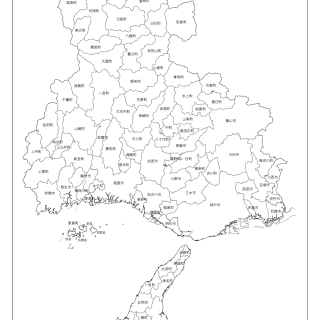速度伝達比が30で動力伝達効率がほぼ100%で滑りのない歯車装置の記述として、最も適切なものはどれか。 ただし、速度伝達比は、歯車装置の入力軸の角速度を出力軸の角速度で割った値とする。最も適切なのは3番です。 解説 速度伝達比を と定義すると、出力角速度は です。すなわち、入力軸が30回転する間に出力軸は1回転します。 動力伝達効率がほぼ100%(滑りなし)なので、入力軸の入力トルク と出力軸の出力トルク は動力(トルク×角速度)が等しく、 となります。これを出力トルクについて解くと、 よって出力トルクは入力トルクの約30倍になります。 以上より、
- 入力軸が1回転する間に出力軸は30回転し、出力軸のトルクは入力軸のトルクとほぼ等しい。
- 入力軸が30回転する間に出力軸は1回転し、出力軸のトルクは入力軸のトルクとほぼ等しい。
- 入力軸が30回転する間に出力軸は1回転し、出力軸のトルクは入力軸のトルクのほぼ30倍になる。
- 入力軸が1回転する間に出力軸は30回転し、出力軸のトルクは入力軸のトルクのほぼ30倍になる。
- 入力軸が30回転する間に出力軸は1回転し、出力軸のトルクは入力軸のトルクのほぼ1/30倍になる。https://kakomonn.com/gijyutushi/questions/80689
「入力軸が30回転する間に出力軸は1回転し、出力軸のトルクは入力軸のトルクのほぼ30倍になる。」 (選択肢3番)が正解です。
トルクとはなんですか?
トルク(力のモーメント)とは、ある点(回転中心)を軸に物体を回そうとする「回転させる力の強さ」を表す物理量です。定義と式
- 力 (ニュートン, N)
- 力の作用線から回転中心までの距離(腕の長さ) (メートル, m)
- 単位:N·m(ニュートン・メートル)
意味・使い方
- 回転運動の駆動力 モータやエンジンがシャフトを回す力、工具でボルトを締めるときの力、ドアノブを回すときの力など、身の回りの“回す”動作はすべてトルクで表せます。
- 機械設計の評価指標 ギア、シャフト、軸受けなど回転機構の設計では、必要なトルクに耐えられる部品強度やモータ選定(出力トルク)を評価する際に用います。
- 力と距離の関係 同じ力 でも、力点を軸から遠く(大きな )にするとトルクは大きくなるため、「長いレンチのほうが小さな力でボルトを回せる」といったレバレッジ効果(てこの原理)が生まれます。
例:レンチでボルトを締める場合
- ボルト中心からレンチの柄の先端までが 、人が の力をレンチに垂直にかけると のトルクがボルトに伝わり、締め付けが行われます。
トルクは「回す力の大きさ」を定量的に扱うための基本概念です。機械設計や制御、日常の作業の効率化まで、幅広く利用されます。
入力歯車と出力歯車はかみ合っていますが、トルクは異なるのですか?
はい。歯車がかみ合って伝達するのは「周方向(接触面に沿った)力」です。この力自体は入力歯車・出力歯車でほぼ同じですが、トルクは力に腕(歯車中心から歯先までの半径)を掛けたものなので、歯車の半径が異なるとトルク値は変わります。なぜトルクが変わるのか
- 周方向力
- 入力歯車と出力歯車の歯面は滑りなくかみ合うので、歯先で伝わる接触力(周方向成分)はほぼ等しい。
- トルクの定義
- :歯車の半径(モジュール×歯数/2)
- :周方向力
- 歯数比と半径比
- 速度伝達比(歯車比) (歯数比 と同じ)
- 半径比も同じく
- トルク比 すなわち、
具体例(先ほどの速度比30の場合)
- 入力歯車の半径:
- 出力歯車の半径:
- かみ合う歯先での力: (同じ)
出力歯車側を回そうとすると大きなトルクや力を必要としますか
出力歯車側を手で回そうとすると、確かに「トルク」は入力側に比べて大きくなりますが、歯車のかみ合い面で必要な「力」(周方向の接触力)は入力側と同じ大きさです。ポイント1:トルクは歯車半径×力
- 出力歯車のトルク
- 入力歯車のトルク
ポイント2:力(F)は同じ、トルク(T)は大きい
- かみ合い点で必要な接触力 は、入力・出力ともに同じ。
- 回転中心からの距離(腕の長さ) が30倍あるので、
手で回す場合
- ギアの歯元(かみ合い面)を直接押す力:入力側を回すときと同じ力でOK。
- 回転中心に発生するトルク:出力歯車の方が大きい(30倍)ので、たとえば同じ力で回すなら、手を掛ける「腕の長さ」を短くできるぶん、少ない手の力でも高トルクをかけられる、と考えることもできます。
まとめ
- 出力歯車を回すには、歯車どうしのかみ合いで伝わる「力」は変わらず同じ大きさ。
- しかしその力を大きな半径 に掛けるため、回転中心にかかるトルクは入力の30倍必要(もしくは発生)します。
- 手で回す場合は、出力歯車の半径分だけ手の位置を調整すれば同じ力で高いトルクを得られる、ということです。
トルクは回転の中心で発生していますか?
いいえ。「トルク」は回転の中心で「発生」するものではなく、回転中心(軸)から距離のある点に力がかかったときに、その力が生み出す「回そうとする力の効果」を回転中心まわりのモーメントとして表したものです。ポイント整理
- 力の作用点と腕の長さが本質
- 真正面から中心だけに力をかけても回りません。
- 軸から離れた位置(腕長さ )に力 をかけることで、回転させようとする“ねじり効果”が生じます。
- トルクはその“ねじり効果”の大きさ
- この式は「腕の長さ 」と「かかった力 」の積で評価するもので、作用点で生じた力の効果を回転中心まわりに置き換えて定量化したものです。
- トルクのベクトル表現
- 数学的にはベクトルの外積 で表し、結果として回転中心(軸)の方向を向くトルクベクトルが得られます。
- これは「作用点で生じた力 → 回転中心を軸に回そうとする方向のベクトル」という意味づけです。
したがって、
- 力は作用点(歯車の歯先やレンチの先端など)でかかり、
- トルクはそれを回転中心まわりの“モーメント”として表現した量 であり、中心で発生しているわけではありません。力が「軸から離れた位置」にかかることで、その回転効果を回転中心に集約したのがトルクです。