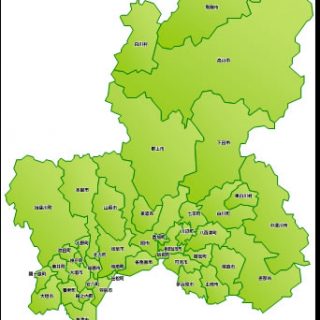「地球温暖化対策の推進に関する法律( 温対法 )」の目的及び内容に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。最も不適切なのは1番の記述です。 「温対法では森林などによる吸収作用の保全に言及していない」という点が誤りで、実際には吸収源(森林等)の保全・強化も基本的な対策の一つとして明記されています。https://kakomonn.com/gijyutushi/questions/36525
- 地球温暖化を防止することが人類共通の課題であることに鑑み、温室効果ガスの排出抑制を促進するための措置を講ずることなどを定めたものであり、森林などによる吸収作用の保全には言及していない。
- 温室効果ガスとして、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定められるもの、パーフルオロカーボンのうち政令で定められるもの、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素を対象としている。
- 事業活動に伴う温室効果ガス排出量が相当程度多い特定排出者のうち、政令で定める規模以上の事業所を有する場合には、その事業所ごとに、温室効果ガス算定排出量に関し定められる事項を事業所管大臣に報告しなければならない。
- 国民が行う温暖化防止のための行動を効果的に進めるため、都道府県知事は、地球温暖化防止活動推進員の委嘱や地域地球温暖化防止活動推進センターの指定を行うことができる。
- 地球温暖化対策計画は、温室効果ガスの排出量などの事情を勘案して、少なくとも3年ごとにその目標及び施策について検討し、必要と認めるときは速やかに変更しなければならない。
吸収源(森林等)の保全・強化はどのように明記されていますか
「吸収源(森林等)の保全・強化」は、本法の冒頭部分である総則の中で、次のように明記されています。■第二条(定義)第二項
この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。 (japaneselawtranslation.go.jp)ここで、地球温暖化対策には「吸収作用の保全及び強化」も含まれることが定義されています。
■第三条(国の責務)第三項
国は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、…技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。 (japaneselawtranslation.go.jp)ここでは、国が「吸収作用の保全及び強化」に向けた具体的な措置を講ずる義務を負うことが規定されています。
また、第五章(森林等による吸収作用の保全等)を設けて、森林吸収源対策の実施状況の把握等を規定するなど、本法全体を通じて森林などの吸収源の保全・強化が体系的に位置づけられています。
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定められるもの、パーフルオロカーボンのうち政令で定められるものとは何ですか?
政令(地球温暖化対策法施行令)で定めるハイドロフルオロカーボン(HFC)の種類は、IPCC第2次評価報告書に掲載された以下の13物質です。 (env.go.jp)- HFC-23(トリフルオロメタン)
- HFC-32(ジフルオロメタン)
- HFC-41(フルオロメタン)
- HFC-125(1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタン)
- HFC-134(1,1,2,2-テトラフルオロエタン)
- HFC-134a(1,1,1,2-テトラフルオロエタン)
- HFC-143(1,1,2-トリフルオロエタン)
- HFC-143a(1,1,1-トリフルオロエタン)
- HFC-152a(1,1-ジフルオロエタン)
- HFC-227ea(1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン)
- HFC-236fa(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン)
- HFC-245ca(1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン)
- HFC-43-10mee(1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン)
- PFC-14 (四フッ化炭素: CF₄)
- PFC-116 (ヘキサフルオロエタン: C₂F₆)
- PFC-218 (オクタフルオロプロパン: C₃F₈)
- PFC-31-10 (デカフルオロブタン: C₄F₁₀)
- PFC-c318 (ヘプタデカフルオロプロパン: C₄F₈)
- PFC-41-12 (ドデカフルオロブタン: C₅F₁₂)
- PFC-51-14 (テトラデカフルオロペンタン: C₆F₁₄)
政令で定める規模以上の事業所を有する企業の対象になっているのはどこですか?
政令で定める規模以上の事業所を有する企業とは、いわゆる「特定事業所排出者」に該当する企業のことを指します。具体的には、次のいずれかの要件を満たす事業者です。(policies.env.go.jp)- 全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が 1,500キロリットル/年以上 となる事業者 (※省エネ法における「特定事業者」「特定連鎖化事業者」「管理統括事業者等」を含む)
- (別途)三ふっ化窒素(NF₃)の排出量が CO₂換算で 3,000トン/年以上 と算定される事業所を有する事業者 (env.go.jp)