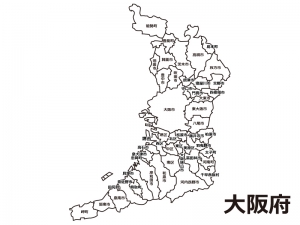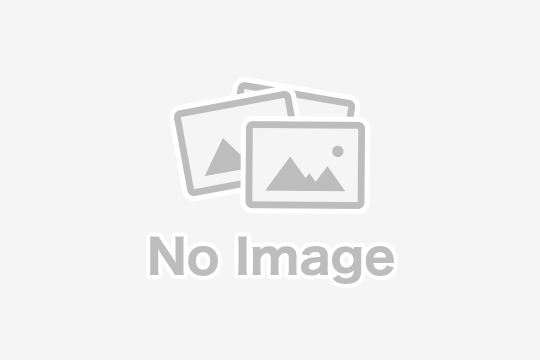1 序論
ロボット工学は、医療分野 [28, 85, 233, 362]、軍事分野 [144, 312, 421]、産業分野 [5, 23, 161, 226, 430]、宇宙分野 [26, 258, 263, 294, 398]、農業分野 [97, 111, 240, 260, 276, 439] など、さまざまな応用領域で私たちの生活に影響を与えてきた。作業環境が異なれば、必要とされる移動ロボットも異なる(付録C参照)。自律性は移動ロボットの性能を大幅に向上させる。なぜなら、自律的に移動できれば、必要な場所へ自ら到達できるからである。自律航法に関する文献は膨大で進化のスピードも速いため、定期的に文献レビューを作成することが不可欠である。こうすることで、経験豊富な研究者も初心者も、自律航法分野の最新の最先端状況を把握でき、本総説もその目的で執筆された。
自律移動ロボットへの道のりは、世界初の汎用移動ロボット「Shakey」[297] の開発から始まった。スタンフォード研究所の人工知能センターによって開発されたShakeyは、自らの行動を推論できる能力を持っていた。もう一つの注目すべき移動ロボットとして「CART」[10, 95] があり、カメラと無線制御リンクを用いたライン追従が可能であった。移動ロボットは宇宙探査用にも開発されてきた。例えば、ソ連が月探査のために開発した「Lunokhod」[66, 184] や、米国が大気温度、風速・風向、気圧などを測定するために開発したバイキング火星着陸機(VL-1、VL-2)[153]、さらに火星探査車「Sojourner」[269] がある。
自律航法の進展の一環として、自律移動ロボットは運転 [86, 187, 299, 317, 345]、病院での医療補助 [298]、活火山の探査(Dante I、II)[29, 216] などに利用されてきた。2004年に開催されたDARPAグランドチャレンジ [412] のような国際競技会は、この進歩を大きく後押しした。この大会では、自律走行車が人間の介入なしに240kmのオフロードコースを走破することが求められた。完走者は出なかったものの、多くの失敗から貴重な教訓が得られた。翌年の再挑戦では、5台の自律走行車(AV)が完走し、その中でスタンフォード大学の「Stanley」[386] が優勝した。2006年には、交通規則を順守しながら都市部を走行するチャレンジ [413] が行われ、カーネギーメロン大学とゼネラルモーターズが開発した車両「Boss」[394] が優勝した。
研究者たちはマルチロボット構成にも取り組んできた。Swarm-botsプロジェクト [137] は、単純なロボット群が自己組織化して複雑なタスクを達成することを目的としていた。また、自律型無人潜水機(AUV)の群れを用いたステルス性の高い水中ミッションの研究も行われた [245]。この手法では、衛星など外部からの位置情報取得のために水面へ浮上する頻度を減らし、任務が発覚する可能性を低減できる。2010年には「Multi Autonomous Ground-Robotic International Challenge(MAGIC)」[18] が開催され、自律ロボット群が協力して作業を行う競技が行われた。
これまでにも、自律移動ロボットに関する複数の総説論文が発表されているが、本研究と既存の総説の違いは表1に示されているとおりである。表からわかるように、過去の総説ではいくつかの重要なトピックが欠けており、本論文ではそれらを補っている。 例えば、Niloy ら [296] は屋内自律航法にのみ焦点を当てている。Pol と Murugan [316] の総説も屋内航法に限られているが、環境内での人間の存在は考慮されている。Mohanty と Parhi [273] は、グローバルおよびローカル経路計画とナビゲーションの要件に焦点を当てた。Guzel の総説 [142] は地図なしのビジョンベース航法が主題だが、一部の地図あり手法も扱っている。しかし、SLAM やその他の重要トピックは含まれていない。 Injarapu と Gawre [164] は経路計画と従来型の障害物回避のみを対象としている。Pandey ら [306] はナビゲーションアルゴリズムを、決定論的、非決定論的、進化的アルゴリズム(EA)、およびグローバル/ローカル手法 [295] に分類したが、SLAM や最新の障害物回避手法は扱っていない。Victerpaul ら [396] は経路計画手法に重点を置き、ナビゲーションや従来型障害物回避もカバーしている。Tzafestas [391] は多くのトピックを網羅しているが、最新の障害物回避手法やシミュレーションツールなどが欠けている。 Alatise と Hancke [12] はセンサーの種類、自律移動ロボットの課題、従来型障害物回避、センサーフュージョンなど複数のテーマを扱っているが、SLAM や強化学習(RL)/深層学習(DL)による障害物回避の最新手法は含まれていない。Ibanez ら [338] は地上車両向け経路計画手法に焦点を当てており、他のプラットフォーム(自律船舶など)にも応用可能だが、SLAM、最新の障害物回避、センサーフュージョンなどは欠けている。Panigrahi と Bisoy [309] は経路追従/計画、シミュレーションツールなどを調査していない。Zghair と Al-Araji [433] は過去10年間の移動ロボット制御システムの進化を調査しているが、やはり最新の障害物回避やシミュレーションツールは取り上げていない。 これら既存総説の不足点を踏まえ、本総説では表1に示したすべてのトピックを網羅することを目指した。具体的には以下を行った: 従来法および強化学習(RL)・深層学習(DL)に基づく最新の障害物回避手法を包括的に解説 代表的なSLAM手法のレビュー よく知られたロボットシミュレーター(付録B)と、それらがROS(Robot Operating System)に対応しているかどうかの紹介 [320] 運用環境に基づく移動ロボットプラットフォームの種類と特徴 カルマンフィルタ [178] やその拡張、パーティクルフィルタ [133] など有名なセンサーフュージョン手法の簡潔なレビュー オープンソースのSLAMデータセットの紹介 本総説の残りの構成は以下のとおりである。 第2章:経路計画手法のレビュー 第3章:経路追従手法のレビュー(付録Dも参照) 第4章:センサーフュージョン手法のレビュー(付録Fも参照) 第5章:ナビゲーション手法とSLAM手法のレビュー(SLAMは付録Hも参照) 第6章:既存の自動運転車の事例をレビュー(付録Gも参照) 第7章および第8章:将来の研究課題と結論 また、センサーの種類、シミュレーションツール、移動ロボットプラットフォーム(付録A~C)、障害物回避手法(付録E)についても詳細を掲載している。2 経路計画
ロボットは、機載センサー(付録A参照)によって環境を認識した後、現在位置から目的地まで到達するために実行可能な経路を計画する必要がある。経路計画アルゴリズムには豊富な文献があり、大きく以下の3つに分類できる。
-
従来型手法(例:A* [147]、ダイクストラ法 [87] など)
-
AIベース手法(例:強化学習(RL)、遺伝的アルゴリズム(GA)など)
-
ハイブリッド手法(従来型手法とAI手法を組み合わせたもの)[53]
また、経路計画手法の別の分類 [140] として、次の4つのクラスがある(図1参照)。
-
幾何モデル探索(Geometric Model Search)
-
人工ポテンシャル場(Artificial Potential Field, APF)(付録E.1.3参照)[191]
-
ランダムサンプリング(Random Sampling)
-
生物模倣型(Bio-inspired)[140, 230]
2.1 幾何モデル探索手法
幾何モデル探索手法は、最も初期に登場した経路計画アルゴリズムの一群であり、理論的な基盤がよく確立されている。これらの手法では、探索空間に関して特定の条件が成り立つことを前提とする場合が多い。
例えば、Aやダイクストラ法は、重み付きグラフにおける最短経路を求める。オキュパンシーグリッドマップにおいては、D [366] やその拡張手法(Focused D* [367]、D* Lite [205])が有効である。Dは、未知領域に障害物がないと仮定し、そのマップに基づいて始点から目標までの最短経路を計算する。航行中に新たな障害物を発見するとマップを更新し、必要に応じて新しい最短経路を計算する。この処理は目標に到達するか、到達不可能と判断されるまで繰り返される。航行中に新しい障害物が見つかることは一般的であるため、再計算が高速であることが重要であり、これはD系手法の強みである。
Focused DはAとDのアイデアを組み合わせたものであり、D LiteはLifelong Planning A*(LPA*)[206] と動的SWSF-FP [321] の考え方を統合した増分探索法に基づく。
レベルセット法(Level Set Method, LSM)[302] は、自律型無人潜水機(AUV)の経路計画に用いられる幾何モデル探索手法の一つである。LSMは海洋の動的な流れをシミュレーションできるため、水中での効率的な経路計画において重要である。単に最短距離の経路を辿るだけでは、海流の影響により最短時間での到達が保証されない [372]。LSMは海流の変化を考慮することで効率的な経路計画を実現する [248]。幾何モデル探索手法の特性は表2に示されている。
2.2 ランダムサンプリング手法
ランダムサンプリング手法は、探索空間をすべて調べるのではなく、障害物のない領域内でランダムに点をサンプリングすることにより、素早く探索を行うことを目的としている。サンプリングした点を接続して経路計画を完成させる [65]。探索空間を完全に調べないことが、この手法の主な利点である。また、探索グラフの拡張における反復回数を増やせば、計画経路の質(最適性)を向上させることも可能である。
しかし、ランダムサンプリング手法は狭い通路のような空間を通過する経路を見つけるのが苦手な場合がある。このカテゴリの代表的手法として、確率的ロードマップ法(PRM)[186] や急速探索ランダムツリー(RRT)[222] がある。
2.3 生物模倣型手法
生物模倣型(Bio-inspired)手法は、動物や人間などの生物の行動から着想を得たものである。図1に示すように、これらは進化型アルゴリズム、人間由来の発想、群知能アルゴリズムに分類できる。本節ではそれぞれを簡単に解説し、表3に長所と短所をまとめる。
2.3.1 粒子群最適化(PSO)
粒子群最適化(Particle Swarm Optimization, PSO)[188] は、複雑な最適化問題の解法として知られる群知能手法の一つである。PSOでは、探索空間内に粒子と呼ばれる候補解の集団を配置し、それぞれの粒子は位置と速度を持つ。また、粒子は全体の最良位置 、自身の最良位置 、直前の状態を保持する。反復ごとにこれらの値を更新し、粒子の位置と速度を調整する。
AUV(自律型無人潜水機)の経路計画において、複数のウェイポイントを通過する最短経路の計算 [257] や、AUV群の障害物回避協調行動 [403] にPSOが利用されている。
2.3.2 アントコロニー最適化(ACO)
アントコロニー最適化(Ant Colony Optimization, ACO)[88] は、アリが餌を探索する際にフェロモンを残す行動を模倣した群知能アルゴリズムである。餌を見つけたアリはフェロモンの付いた経路を戻り、他のアリがそれを辿ることで最短経路が強化される。この仕組みは単純ながら、効率的に最短経路を見つけることができる。
ACOは移動ロボットの経路計画 [58, 73, 231] に応用されている。
2.3.3 遺伝的アルゴリズム(GA)
遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm, GA)[155] は、ダーウィンの進化論と自然淘汰に基づく進化型アルゴリズムである。まず初期集団をランダムに生成し、世代ごとに評価関数で適応度を計算する。適応度に応じて親個体を選択し、交叉と突然変異を行って次世代を作る。このプロセスを繰り返し、最終的に最適解を得る。
GAは静的環境での経路計画 [219] や、複数ロボットの経路計画 [291] に利用されている。
2.3.4 差分進化(DE)
差分進化(Differential Evolution, DE)[369] は、個体群に基づく最適化手法であり、突然変異・再結合・選択を繰り返して進化させる。DEはシンプルかつ高性能で、非ホロノミックロボットの障害物回避経路計画 [261] や、ロボット経路をサブゴールに分割して表現する手法 [166] に適用されている。
2.3.5 ファイアフライアルゴリズム(FA)
ファイアフライアルゴリズム(Firefly Algorithm, FA)[427] は、ホタルが光を用いて互いに引き寄せられる行動を模倣したメタヒューリスティック手法である。明るいホタルに暗いホタルが引き寄せられる原理を利用する。AUVの3次元経路計画や、ガウスランダムウォークによる探索能力強化版(PPMFA)[59] などで利用されている。
2.3.6 生物地理学的最適化(BBO)
生物地理学的最適化(Biogeography-Based Optimization, BBO)[360] は、種の移動・定着・絶滅などの生物地理学的現象を模倣する。良好な解(高HSI)ほど変化に強く、移民・移出確率を基に他の解から情報を交換する。ロボット経路計画では、固有値分解に基づく情報共有の改善や、非線形移民戦略、エリート保持機構の導入による性能向上が報告されている [288, 423]。
2.3.7 ファジィ論理(FL)
ファジィ論理(Fuzzy Logic, FL)は、変数が0または1の二値だけでなく、0~1の任意の値を取れる多値論理である。不確実な情報に基づく推論や意思決定が可能であり、移動ロボットの経路計画にも利用されている [307, 422]。
2.3.8 学習アルゴリズム
経路計画は、環境が既知で静的障害物のみの場合はオフライン(例:A*)、部分的に未知で動的障害物がある場合はオンライン(例:D*)で行える。オンライン計画では強化学習(RL)が有効だが、報酬が疎な大規模環境では学習が遅く、未知環境への汎化が難しい課題がある [402, 304]。
これを解決するため、グローバル誘導とローカルRL計画を組み合わせたG2RL [402] や、TD3とPRMの組み合わせ [120] などが提案されている。
3 経路追従
計画された経路を実行するためには、移動ロボットがその経路に沿って走行できるような仕組みが必要である。経路追従手法は、単純なPure Pursuit(付録D参照)のような方法から、動的システムや深層学習に基づくより複雑なアプローチまで幅広く存在する。本章では、いくつかの代表的な経路追従手法を解説する。
3.1 線形二次レギュレータ(LQR)
線形二次レギュレータ(Linear Quadratic Regulator, LQR)は、最適制御理論 [378] に属する手法で、移動ロボットの経路追従にも利用できる [69, 217, 397]。LQRは、所望の軌道 を最小の制御労力で追跡することを目的とする。ロボットのセンサー情報を受け取り、以下の最適化問題に基づいて制御入力 を求める。
ただし、
ここで、 と は時刻 の状態と制御入力、 と はシステムの状態方程式を表す行列である。 は状態コスト、 は制御入力コスト、 は時間地平(horizon)を表す。
3.2 モデル予測制御(MPC)
モデル予測制御(Model Predictive Control, MPC)[213] は、有限の未来時間地平における制御入力を最適化し、そのうち最初の制御コマンドのみを実行する手法である。次の時刻で再び最適化を繰り返すため、将来の事象を考慮して制御指令を適応的に調整できる。LQRと同様、システムの動的モデルに基づいたコスト関数を最小化する。
MPCは移動ロボットの経路追跡に応用されており、例えば一輪車型ロボットの横滑り問題を外乱として扱い、MPCで補償する手法が提案されている [431]。また、P2ATロボットの経路追跡をMPCでモデル化し、LQRを用いて解く方法 [326] もある。さらに、マルチロボット編隊や協調ナビゲーションへの応用も行われており、確率的推論と分散サンプリング型MPCを組み合わせた手法が提案されている [171]。
3.3 深層学習(DL)・強化学習(RL)による経路追従
強化学習(RL)は近年、連続状態空間・連続行動空間の問題にも拡張され、深層学習(DL)のアイデアを取り入れた深層強化学習(DRL)が登場している。DRLは高次元かつ連続制御が必要なロボットにも適用可能である。
例えば、Chengら [62] はDDPG [241] に基づくDRLで経路追従と障害物回避を同時に実現した。経路追従は適切な状態・報酬関数の設計によって学習され、障害物回避ではこれらの関数に障害物までの距離や角度を組み込む。提案手法はシミュレーションで評価された。
クアッドコプター型UAVの経路追従は、風などの外乱の影響を強く受けるため困難である。Weiら [407] は、予測制御とニューラルネットワークによる外乱推定を組み合わせ、持続的外乱に適応可能な手法を提案した。
地上移動ロボットにおいても、タイヤのスリップや横滑りといった外乱があり、動作モデルや自己位置推定に影響する。これに対処するため、RBFN(Radial Basis Function Network)を用いてロボット動力学や外乱の不確実性をモデル化する手法が提案されている [375]。
さらに、KristantoとIklima [214] はAlexNetを用いて「左側障害物あり」「右側障害物あり」「自由走行可能」の3クラス分類を学習し、衝突回避しながらの道路追従を実現した。
7 今後の研究課題(Future Work)
本章では、自律移動ロボットに関する将来の研究方向性を示す。
7.1 マルチロボット構成
複数のロボットを活用して作業をより迅速に完了させることは自然な発想である [289]。将来の重要な研究課題は、作業のどの部分を集中管理(中央集権型)で行い、どの部分を分散管理(分散型)で行うべきかを決定することである [113]。また、特定の作業を遂行するために各ロボットに搭載すべきツールの選択を効率的に行う意思決定も必要である [113]。
自律航法は、自律船(MASS: Maritime Autonomous Surface Ships)の開発にも利用されている。将来的には、自律度D3(乗員なしの遠隔操縦)やD4(完全自律)のMASS間で協調行動を確立することが重要である [301]。さらに、人間と機械の相互作用における安全性の分析も必要である [196]。
7.2 オフロード自律航法
都市環境向けの自動運転車は近年集中的に研究されてきたが、オフロード自律航法は依然として成熟度が低く、さらなる研究が必要である [411]。都市環境向け技術は、構造化された道路やインフラを前提としているが、オフロード環境ではこうした前提は通用せず、より高度な認識・計画モジュールが求められる。
7.3 プライバシー
自動運転車(AV)は効率的な運用のために、センサー情報、利用者の嗜好、位置情報などを収集する。また、AVはインターネット接続、交通管制システムや他のAVとの通信が必要である。スマートフォンやウェアラブル端末をAVネットワークに接続することは利便性を高めるが、これらの端末がマルウェアに感染している可能性があり、セキュリティリスクとなる。深刻なサイバー攻撃 [322] はAVシステムを破壊し、重大な事故や人命損失を引き起こす可能性がある。さらに、無断のデータ収集、情報漏えい、追跡といったプライバシー侵害の懸念もある。こうした懸念を解消し、社会的信頼を得ることが将来の重要課題である。この点はDagstuhl Seminar 23242 [183] でも強調されている。
7.4 不確実性
センサー計測や制御コマンドの実行は常にノイズを伴い、不確実な結果をもたらす。自律航法システムでは、ノイズや不確実性を考慮することが性能確保に不可欠である。状態推定器やセンサーフュージョンアルゴリズムは、不確実な環境下で重要な役割を果たす。例えば、RGB画像と疎なLiDARデータを融合し、未知のオフロード地形の鳥瞰視点での高密度なセマンティックセグメンテーションを生成する研究 [194] がある。
7.5 リアルタイム認識
安全性が重要なシナリオ(自動運転車など)では、一瞬の判断の遅れが事故に直結する。リアルタイムかつ高精度な環境認識は、効果的な意思決定に不可欠である [356]。例えばApolloでは、カメラ・LiDAR・RADARごとに障害物検出、分類、追跡を行い、それらを融合して高信頼な環境認識を実現している [202]。Cruiseでは、長距離RADARの視野制限を補うため、可動式のRADARをサイドミラーに搭載している(図18(a))。
7.6 一般化能力
自動運転車は、学習段階で経験していない多様なシナリオにも対応する必要がある。しかし、データ駆動型手法は過学習や一般化性能の低下により、未知のシナリオで失敗しやすい [228, 305]。さらに、こうした手法は「ブラックボックス」であり、安全性が重要な用途では説明可能性が求められる。この課題に対して、人間の知識や常識を活用し、新たな状況にも適応可能な知識ベース型手法が注目されている [238]。これらはオブジェクト検出、意味理解 [283]、環境内の関係性推論 [108] などを含む。
7.7 倫理的課題
自動運転車は、他の無謀運転や交通渋滞によって生じる危険に直面した際、重大な意思決定を迫られる。どれほど高度でも、死亡事故の可能性はゼロにならない。この場合、損害の責任が製造者、開発者、AI設計者、またはAIそのもののいずれにあるのかは明確でない [218]。
7.8 安全性とシステム検証
自動運転車は安全性が最優先の応用分野であり、わずかな誤認識や意思決定ミスでも大惨事につながる。このため、安全性を担保するための専用ハードウェア・ソフトウェアによる検証が必要である [61]。その手法として、ソフトウェアインザループ(SIL)、ハードウェアインザループ(HIL)、ビークルインザループ(VIL)[232] がある。
-
SIL:数値モデルのみで構成される仮想試験環境 [208]。開発初期のテストに有効。
-
HIL:ソフトウェアを実機ハードウェア上で動作させる。SILより精度・信頼性が高い [128, 310]。
-
VIL:実車を含む複合的な仮想・実環境テスト。仮想車両、仮想センサーモデル、仮想環境、実車、道路条件シミュレーターなどで構成される [61]。
小規模スタートアップにとって高度な検証環境は高コストで困難なため、Cruiseに買収されたVoyageは「open autonomous safety (OAS)」をオープンソースで提供している [47]。Apolloにも専用の安全モジュールがあり、Dynamic model CIL [418] によって迅速な検証を行っているが、MLベース部品は安全要件を完全には満たしていない [202]。
7.9 センサー冗長性
異なる種類のセンサーで同様の計測を行うことは、以下の利点がある。
-
信頼性・耐久性向上(故障時のバックアップ)
-
ノイズ低減(複数センサーの融合による)
-
認識性能向上(センサーごとの長所を補完し合う)
例:CruiseやWaymoは複数のLiDARとRADARを搭載。LiDARは高精度だが天候に弱く、RADARは天候に強いが解像度が低い。組み合わせることで全距離域で高精度な障害物検知が可能になる [3]。
7.10 インフラ依存
自動運転車は自車のセンサーに依存する一方、V2X(Vehicle-to-Everything)などのインフラ連携技術も有用である。V2Xは車両を関連する全てのエンティティと接続し、事故や渋滞、大気汚染を低減する [323]。用途例として、車線変更警告、前方衝突警告、工事警告などがある。ただし、路側インフラとの通信が攻撃される危険もある。
7.11 SLAM
SLAMの効率的実行には、新規探索(exploration)と既知領域の再訪(exploitation)のバランスが重要であり、これはActive SLAMのテーマである [383]。今後の課題として、動的環境への対応、セマンティックSLAM、LiDARとDLベース手法の統合、リアルタイム性と精度の両立、組込みデバイスでの実行などが挙げられる [57]。
7.12 未知環境ナビゲーション
未知環境での自律航法は望ましい機能である。Shahらは18か月にわたり収集した多様な実環境データでRLを訓練し、RECON(Rapid Exploration Controllers for Outcome-driven Navigation)を提案した [351]。また、ViKiNG(Vision-Based Kilometer-Scale Navigation with Geographic Hints)[352] は不正確な地図情報を利用し、トポロジーマップ表現のみで数km先の目標に到達可能な手法として提案されている。
8 結論(Conclusion)
本論文では、自律移動ロボットの分野における幅広いテーマ――センサーの種類、移動ロボットプラットフォーム、シミュレーションツール、経路計画と追従、センサーフュージョン、障害物回避、SLAM――を包括的にレビューした。さらに、深層学習や強化学習などの最新技術の応用についても詳細に取り上げた。
既存の総説の不足点を補う形で、従来法から最新手法まで体系的に整理し、各分野の代表的手法、利点・欠点、適用例を提示した。また、自動運転車の事例を通じて、現実世界での実装課題や安全性、プライバシー、倫理、将来の研究課題についても議論した。
自律航法は今後も急速に発展する分野であり、リアルタイム性、一般化能力、安全性、インフラ連携など、多岐にわたる課題が存在する。本論文で示したレビューと将来展望が、研究者・技術者がこの分野の発展に貢献するための指針となることを期待する。
用語
SLAMとは何ですか
SLAMとは?
SLAM は Simultaneous Localization and Mapping の略で、日本語では 自己位置推定と地図生成の同時実行 と呼ばれます。
ロボットや自律移動体(自動運転車、ドローン、掃除ロボットなど)が、 未知の環境の中で「自分がどこにいるか」を推定しながら、同時にその環境の地図を作成していく技術 です。
SLAMの目的
-
自己位置推定(Localization)
GPSが使えない屋内や地下でも、センサー(カメラ、LiDAR、IMUなど)を使ってロボット自身の位置を推定する。 -
地図生成(Mapping)
周囲の障害物や地形を認識して、ロボットが走行可能な地図(占有格子地図や特徴点マップ)を構築する。
SLAMの基本的な流れ
-
センサー(カメラ、LiDAR、IMUなど)で環境を観測する
-
観測データから特徴点やランドマークを抽出する
-
その特徴を用いて、自分の位置を推定する
-
推定した位置情報をもとに地図を更新する
-
新しい観測が入るたびに、①〜④を繰り返す
SLAMの種類
-
視覚SLAM(Visual SLAM, V-SLAM)
カメラ画像を利用する(例:ORB-SLAM, LSD-SLAM) -
LiDAR SLAM
レーザースキャナを利用する(例:Cartographer, LOAM) -
マルチセンサーSLAM
カメラ・LiDAR・IMUを組み合わせる(センサーフュージョン型)
SLAMが使われる場面
-
掃除ロボット → 家の地図を作りながら効率的に掃除する
-
自動運転車 → GPSが使えないトンネルや市街地での自己位置推定
-
ドローン → 屋内や森の中などでの自律飛行
-
探査ロボット → 災害現場や宇宙探査での未知環境の地図化
👉 まとめると、SLAMは 「ロボットが未知の環境を探索しながら、自分の位置と地図を同時に推定する技術」 であり、自律移動ロボットの中核技術のひとつです。
ご希望なら、SLAMの代表的なアルゴリズム(EKF-SLAM、FastSLAM、Graph-SLAMなど) についても詳しく解説できますが、そちらも知りたいですか?