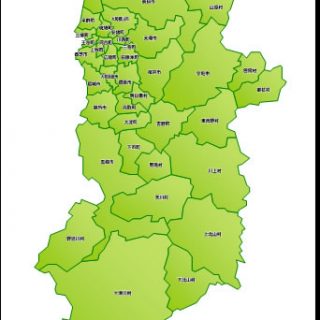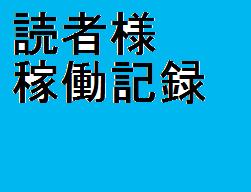承知しました。成人における斜視の治療に関する研究論文を調査し、手術療法、非手術療法(プリズム眼鏡、視能訓練、ボツリヌス療法など)の効果や適応、予後、合併症などについてまとめます。
少々お時間をいただきますので、準備が整い次第ご報告いたします。
成人斜視治療の最新研究レビュー
成人斜視は4–5%の有病率とされ、立体視障害や複視のみならず、心理社会的な症状や生活の質(QOL)の低下とも深く関連することが知られている。成人斜視の管理では、眼位を揃えて視覚的・心理的症状を軽減することが主目的とされる。以下では、成人斜視に対する
主要な治療法とそれぞれの効果・適応、副作用、手術と非手術治療の比較、治療後のQOLへの影響、さらに最新の治療動向・ガイドラインを臨床研究やレビュー論文に基づいて概説する。
主要な治療法
成人斜視の治療法には大きく分けて
外科的治療と
非手術的治療がある。外科的治療は偏位角が大きい場合や複視の改善を目的として行われる。一方、非手術的治療には
プリズム眼鏡、
視能訓練(オルソプティックス)、
ボツリヌス毒素注射、および屈折矯正(眼鏡)などが含まれる。日本弱視斜視学会の解説によれば、小さい斜位ではプリズムや視能訓練が適用され、大きな斜位では手術が検討される。以下、それぞれの治療法を詳述する。
外科的治療
- 適応: 大きな斜視角や複視のある症例、眼球運動麻痺(神経麻痺斜視)や先天性・特発性斜視の矯正、整容目的など。日本では年齢制限はないが、一般に全身麻酔が必要なため健康状態を考慮する。
- 効果・成功率: 一般に、水平筋手術の成功率は60–80%と報告されている。特に間欠性外斜視(IXT)では、術直後の一次成功率が80–85%に達するとの報告もある。しかし、術後の斜視角は年月とともに増大することが多く、12.1%が再手術を必要とするというデータもある。このため、術後経過観察中に筋緊張の戻りや外転不足が起こる場合が多く、術式(調節縫合の有無)や手術時期を慎重に検討する必要がある。
- 合併症・副作用: 通常の手術合併症(術後感染、出血、瘢痕形成、眼球穿孔の稀なリスク)に加え、過矯正・低矯正(残存斜視または逆転斜視)、複視の悪化や発生、筋肉の滑脱・剥離、麻酔リスクなどがある。手術直後は疼痛や腫脹を訴える患者もいる。眼科医師の経験にもよるが、細心の術前検討と術式選択が重要である。
プリズム眼鏡療法
- 適応: 斜視角が小さく(例えば数プリズムディオプター程度)、主訴が複視に限られる症例で用いられる。手術適応外の高齢者や僅かな偏位角の例、手術待機中の一時的措置としても用いられる。
- 効果・成功率: 成人斜視患者で複視を訴える例では、プリズム眼鏡による矯正成功率は約50–70%程度と報告されている。例えばHattらの研究では、中等度複視を有する成人34名に対しプリズムを処方し、68%で読書・遠見時の複視頻度が「ほとんど出現しない」レベルに改善した(プリズム成功)。別の研究でも、48名中22名(51%)でプリズムのみで複視が軽減し、視力関連QOLが有意に改善したとされる。
- 副作用・注意点: フレネルプリズムまたはグラウンディングプリズムの使用に伴い、視覚的歪みや像の不鮮明、レンズの重量感、頭痛・眼精疲労などを生じることがある。また、高度な斜位や非協調的斜視では効果不十分なことが多い。加えて、片側プリズムは融像感を得にくいため、両眼視機能が乏しい場合は使用困難となる。妊娠や発汗によるプリズム滑落にも注意が必要である。
視能訓練(オルソプティックス)
- 適応: 主に両眼視機能(融像や輻輳機能)の強化を目的として行われる。具体的には収束緩慢症(CI)や間欠的斜視の維持訓練、術後残存複視の改善、視覚神経プラスティシティを利用した訓練などに適応される。成人でも脳の可塑性を期待して幼少期発症斜視の後療法として実施されることがある。
- 効果: 成人のランダム化試験は限られるが、ケースシリーズでは一定の改善例が報告されている。前述の研究では、プリズム治療が奏功しなかった成人斜視患者20名中13名(65%)が追加視能訓練により両眼視(融像)を回復し、QOL指標が改善したとされる(視能訓練併用群)。一方、視能訓練単独の無作為比較試験は少なく、成人斜視に対する視能訓練のエビデンスはまだ不確実である。一般には、視能訓練は安全性が高く副作用はほとんどないが、効果が不確実で長期的継続が必要とされる。
ボツリヌス毒素注射
- 適応: 外眼筋へのA型ボツリヌス毒素(Botoxなど)注射は、特に急性の麻痺性斜視(例:6番神経麻痺)、代償性斜視、後天的内斜視、診断的用途(試験的融像評価)などで有用とされる。また、直視時複視の救済や手術併用時の補助手段としても利用される。日本のガイドラインでは、12歳以上の水平・垂直斜視に適応とされる(共同性・非共同性問わず)。
- 効果・成功率: 注射後は数週間で筋麻痺が生じ、3–6ヵ月程度効果が持続する。複数回注射により斜視角が減少し、融像を回復した症例もある。成功率は斜視型によって異なるが、一般に手術に比べやや低いとされる。実際、最新のコクランレビューでは、ボツリヌス注射に比べて手術のほうが斜視改善の可能性が高い(相対リスク0.72;95%CI 0.53–0.99)という低確度のエビデンスが示された。
- 副作用・合併症: 注射部位の副作用として、一時的な眼瞼下垂(軽度:16–37%)、垂直斜位の増強(5–18%)などが報告される。ボツリヌス毒素の作用は一時的で数か月で薄れ、多くは自然消失する。重篤な合併症は稀だが、過量投与による全身性筋弛緩や抗体形成による再投与効果減弱の可能性もあるため、使用量と注射技術に注意が必要である。
- 最新の知見: 海外の報告では、スクリーンの長時間使用による急性内斜視に対しボツリヌス注射を第一選択とする戦略が提案されている。例えばRameshら(2023)は、過度な近業による発症眼位異常に対し注射療法が有効と報告している。
合併症・副作用
各治療法に共通・固有のリスクがある。主なものを以下に示す:
- 手術: 頻度の高いものに過矯正または低矯正がある(術後斜視の残存や逆転斜視)。筋肉の術中滑脱・脱臼、結膜下血腫、感染のリスクもある。過少矯正の場合は再手術が検討される。眼球穿孔は極めて稀だが重篤な合併症。全身麻酔下手術のため全身的リスク(出血、呼吸循環器系合併症)も考慮すべきである。
- プリズム眼鏡: 基本的に侵襲はないが、装用感に起因する不快感(レンズの重さ、歪み感、両眼視時の乖離感など)が副作用に当たる。強度プリズムや長時間装用で眼精疲労や頭痛を来すことがある。プリズム板の角度調整誤差やずれにも注意。
- 視能訓練: 基本的に安全だが、過度な訓練で眼精疲労やストレスを生じることがある。重大な身体的副作用は通常ない。
- ボツリヌス注射: 注射部位の疼痛・腫脹、注射後の眼瞼下垂(ほとんどは一過性)、外反位(頑固な外斜位が増強する)、眼圧上昇、一過性の複視悪化などがある。稀に誤注射や過量注射による眼球運動障害が生じる。
手術治療と非手術治療の比較
比較試験は限られるが、
手術治療は斜視角の恒久的改善に優れている一方、
非手術的治療は侵襲が少なく、短期的な症状改善や患者の好みに応じて選択される。コクランレビュー(2023年)では、年齢や斜視タイプを含めた検討で、手術のほうが斜視改善に有利であるとする低確度エビデンスが示された。具体的には、ボツリヌス注射群と比べて手術群の方が6か月後までに斜視角が10PD以下に改善する割合が高かった(リスク比0.72;95%CI 0.53–0.99)。また、成人の複視を対象とした他の研究でも、1回の手術で約80–85%に治療成功が得られる(主要術後アライメント達成)と報告されている。一方、プリズム療法は長期的に持続する斜視改善をもたらすわけではなく、一時的に複視を緩和する手段である。視能訓練は補助的役割と考えられ、単独療法の成功率データは乏しい。したがって、複視や生活障害の有無、大きさなど患者条件に応じて、手術と非手術を組み合わせる(例えば「複視緩和にプリズム→成功しなければ手術」など)柔軟な戦略が推奨される。
予後と生活の質(QOL)への影響
成人斜視治療の最終目標は見かけの改善のみでなく、視機能やQOLの向上である。研究によれば、成人斜視患者は抑うつや社会的回避といった精神的負担を抱えている場合が多く、斜視治療によりQOLが大きく改善することが示されている。特に、
複視のある患者では眼位の整列により日常機能(読書や車の運転など)が改善し、
複視のない患者では視線ずれ自体の心理的影響が軽減されると報告されている。Hattらの研究では、プリズム矯正成功例でAS-20という斜視特異的QOLスコアが有意に改善し、補助的に視能訓練を行った群でもQOL向上が示された。また、Strabismus Surgery for Psychosocial Reasons(文献レビュー)では、手術後にAS-20などのQOL指標が顕著に改善する報告が多数引用されている。AAOガイドラインも、手術やプリズムなど適切な治療後には成人患者のQOLが機能面・心理面の双方で改善すると強調している。
最新の治療動向・ガイドライン
近年、成人斜視治療の重要性が世界的に再認識され、エビデンスに基づく指針が整備されつつある。米国眼科学会(AAO)は2024年2月に成人斜視のPreferred Practice Patternを更新し、成人斜視がQOLに及ぼす深刻な影響と、適切な治療介入によるQOL改善の重要性を強調している。同ガイドラインでは、患者それぞれの目的(複視の解消か整容的改善か)に応じて、診断・治療計画を立てることが推奨されている。日本では日本弱視斜視学会が2019年に斜視に対するボツリヌス療法ガイドラインを発表し、12歳以上の斜視患者での薬剤使用基準や安全性への留意点を示している。このガイドラインでは、拘束型斜視や50PD以上の大偏位などではボツリヌス注射の効果が証明されておらず慎重な適応判断が必要とされている。
最新研究では、デジタルデバイスの長時間使用に伴う「近見内斜視」への対応や、加齢による眼球周囲結合組織の緩み(高齢者に多い下眼瞼斜視)への外科的アプローチ、視機能プラスティシティを活用した新たな訓練法などが注目されている。例えばRameshら(2023)は、過度なスクリーン使用による急性調節内斜視に対してボツリヌス注射を有効な初期治療とした症例を報告している。また、成人特有の術式(調節縫合や可動縫合の利用)、術後リハビリテーションの取り入れなど、手術成績向上を目的とした工夫も進められている。今後の研究やガイドラインでは、これらの最新知見を取り入れつつ「成人患者に最適化された斜視治療」がさらに発展すると期待される。
参考文献: 各節で引用した文献に示した著者名・発表年・掲載誌等を参照のこと。例えば、斜視手術の成功率に関してはGroverら(2017)、間欠外斜視の手術成績ではKopmannら(2024)、ボツリヌス毒素のエビデンスではRoweらのコクランレビュー(2023)、プリズム療法効果ではHattら(2014、2023)、QOLへの影響ではAAOガイドライン(2024)およびZhangらのレビュー(2023)などがある。
斜視角が30程度ある場合の効果的な治療は何ですか?
30 PD程度の水平斜視(中等度~大偏位)では、以下のような治療戦略が一般的に勧められます。
外科的治療(筋手術)を第一選択
成人水平斜視では、エソ偏位15 PD以上、エクソ偏位20 PD以上で外科的矯正が適応とされます
ウィキペディア
。
偏位30 PDは「中等度偏位(11–30 PD)」の上限にあたり、単一筋手術(片側のみの筋後転/再建)では再手術率や不十分矯正のリスクが高まるため、両側水平筋2筋手術(両側内直筋後転または両側外直筋後転)が標準的です
etd.ohiolink.edu
PMC
。
可動縫合(adjustable suture)を用いることで、術後早期に眼位微調整が可能となり、最終的な一次成功率(術後6週以内に10 PD以下)を高める手法も広く用いられています。
プリズム療法は補助的にのみ
プリズム眼鏡(フレネルプリズム含む)は、主に急性取得性斜視や小偏位(≤25 PD程度)で複視緩和を目的に用いられます。しかし30 PDをフル補正するプリズムはレンズ厚・歪みが大きく、装用性・視覚歪みのため実用的ではありません
PMC
。
ボツリヌス毒素注射は限定的
A型ボツリヌス毒素注射は、麻痺性斜視や手術待機中の一時的措置、診断的目的(融合能の有無確認)などで使われることがありますが、30 PDもの大偏位を単独で恒久的に矯正するには適しません(効果は数か月で消退、必要量・注射回数が増え安全性・快適性の点で課題)
EyeWiki
。
視能訓練は補助的役割
融像機能や輻輳力の強化を狙う視能訓練(オルソプティックス)は、安全性は高いものの、大偏位の恒久矯正手段にはならず、手術前後の両眼視機能維持・向上の補助療法と位置づけられます。
まとめ
斜視角約30 PDの成人では、まずは「両側水平筋2筋手術」を検討するのが最も効果的です。プリズムやボツリヌス毒素注射、視能訓練はそれぞれ短期的・補助的な役割にとどまり、根治的な整列を得るにはやはり筋手術が中心になります。具体的な術式(後転量や可動縫合の有無など)は、患者さんのタイプ(エソかエクソ、神経麻痺の有無、既往手術歴など)に応じて術前検討が必要です。
エソかエクソとはなんですか?
「エソ(eso)」と「エクソ(exo)」は、水平斜視の方向を表す略語です。
エソ(esotropia/内斜視)
眼が鼻側(内側)に向いている状態。
英語では esotropia と呼びます。
例:遠視により過度に調節して眼が内側に寄る「調節性内斜視」や、眼球運動神経麻痺による「麻痺性内斜視」などがあります。
エクソ(exotropia/外斜視)
眼が耳側(外側)に向いている状態。
英語では exotropia と呼びます。
例:近業で融像負荷が高まり時々外側へずれる「間欠性外斜視」や、遠視緩解性に対立して起こる「近見外斜視」などがあります。
プリズムディオプター(PD)
斜視角の大きさはプリズムディオプター(PD)で表し、
正の値(+)が「エソ(内方偏位)」、
負の値(-)が「エクソ(外方偏位)」
として扱うのが一般的です。
──要するに、
エソ=眼が内側に寄っている(内斜視)
エクソ=眼が外側に開いている(外斜視)
と覚えていただければ結構です。
内斜視、神経麻痺なしだとどのような手段がとられますか?
思考時間: 10 秒
非麻痺性内斜視(エソ/esotropia)が成人で認められる場合、以下のような段階的アプローチが一般的です。
1. 屈折矯正(メガネ・コンタクトレンズ)
適応:遠視など屈折異常による「調節性内斜視」(accommodative esotropia)では、完全矯正(+レンズ)をまず装用。
効果:遠視の完全補正によって、輻輳‐調節連関を軽減し、眼位が改善することが多い
Wikipedia
。
2. プリズム療法
適応:残存偏位が小さい(おおむね10 PD以下)場合や、複視の自覚を緩和したい場合に用いる。
留意点:プリズム度数が大きくなるとレンズの厚み・歪みが増し、装用コンプライアンスが低下しやすい
Wikipedia
。
3. 視能訓練(オルソプティックス)
適応:両眼視機能(融像・輻輳能力)の向上を狙う補助療法。
役割:主に術前・術後の両眼視機能維持改善や、軽度内斜視の自己管理的治療として用いる
NCBI
。
4. ボツリヌス毒素注射
適応:
急性発症の非麻痺性内斜視(例:急性取得性共同性内斜視)
手術待機中の一時的措置/診断的試験注射
特徴:
3~6ヵ月の効果持続後に徐々に消退
約70–80%で一時的な眼位改善が得られる報告あり
American Academy of Ophthalmology
注意点:眼瞼下垂などの一過性合併症、複数回注射による効果減弱リスクなど。
5. 外科的治療(筋手術)
適応:
偏位角がおおむね15 PD以上(内斜視)で、非手術療法で十分な改善が得られない場合
術式:
両側内直筋後転術が標準的。偏位が大きい(20–30 PD以上)場合は後転量を調整/可動縫合(adjustable suture)併用で術後微調整を行うのが有用。
効果:術後6週間以内に10 PD以下のアライメント達成率は70–85%程度とされる
medlink.com
。
合併症:過矯正・低矯正、結膜下血腫、感染、極めて稀に眼球穿孔など。
治療アルゴリズムの例
初期検査・診断 → 屈折異常の有無を確認し、完全矯正
経過観察(2–4週)→ 偏位残存・複視の自覚を評価
第2ステップ
偏位10 PD以下かつ複視のみ → プリズム装用
10 PD以上、またはメガネ+プリズムで不十分 → 筋手術検討
補助療法として 視能訓練/ボツリヌス注射を適宜併用
成人非麻痺性内斜視では、まずは屈折矯正とプリズムで可能な限り症状緩和を図り、残存偏位が中等度以上(≥15 PD)であれば外科的筋手術を第一選択とするのが標準的な戦略です。