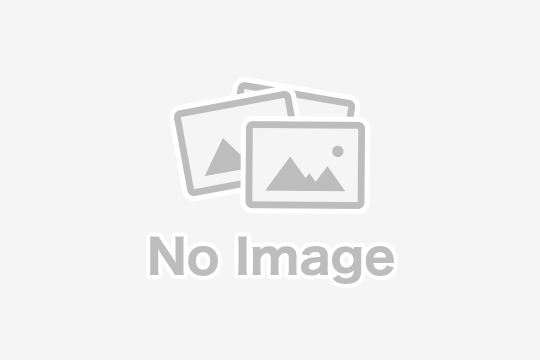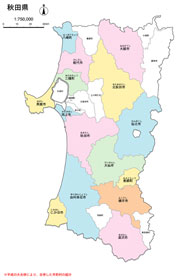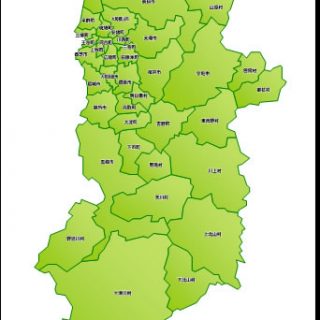成人複視の治療・リハビリの最新動向
成人の複視(二重視)は主に眼筋の斜視や神経障害などが原因であり、その治療・リハビリには多様な方法がある。近年の研究ではプリズム眼鏡やボツリヌス療法、手術療法だけでなく、視覚訓練(オルソプティクス)や仮想現実(VR)を活用した新しいリハビリテーション法も注目されている。本稿では過去5年程度の論文を中心に、成人複視の最新治療法・リハビリテーション法の動向をまとめる。プリズム眼鏡
- 概要: プリズムは光の経路を屈折させて両眼視野を整合させ、複視を軽減する。Fresnelプリズムやレンズ埋め込み型プリズムが用いられる ( Prisms in the treatment of diplopia with strabismus of various etiologies - PMC )。
- 効果例: 31例の複視患者を対象とした研究では,プリズム(うち71%はFresnelプリズム)の処方により複視が完全消失した症例が87%に達し、96.8%がプリズムを継続使用したと報告されている ( Prisms in the treatment of diplopia with strabismus of various etiologies - PMC )。特に破綻性斜視や第4, 第6脳神経麻痺で高い効果が見られた ( Prisms in the treatment of diplopia with strabismus of various etiologies - PMC )。
- 限界・適応: 大きな眼位ズレや複合方向の斜視では強度プリズムが必要となり、貼付プリズムでは視界のゆがみが大きくなる。従来、大振幅斜視や斜め斜視にはプリズムが不向きと考えられていたが、本研究ではFresnelプリズムで複合斜視にも対応可能であると示された ( Prisms in the treatment of diplopia with strabismus of various etiologies - PMC )。ただし,かなりのプリズム度数を要する場合や両眼のズレ方向が大きい例では、適用が難しい場合がある。
- その他の知見: Graves眼症(甲状腺眼症)では眼筋麻痺を伴う複視が生じ、眼筋の安定化までの間プリズムや遮蔽が用いられることもある ( 2022 Update on Clinical Management of Graves’ Disease and Thyroid Eye Disease - PMC )。
ボツリヌス療法
- 概要: ボツリヌス毒素注射は眼筋の収縮を弱め、斜視の角度を一時的に矯正する非外科的手段である。手術の代替として小〜中等度斜視に適応される。
- 効果例・エビデンス: 近年のCochraneレビュー(2023年)では、ボツリヌス注射と斜視手術を比較した4件のRCT(計242例)の結果が報告されている。その結果、短期的には手術が斜視矯正に優れる傾向を示したが、6か月以上のフォローでは結論は不明瞭であった ( Botulinum toxin for the treatment of strabismus - PMC )。ボツリヌス注射群では16–37%に一過性の眼瞼下垂、5–18%に縦ずれ(上転・下転偏倚)が観察された ( Botulinum toxin for the treatment of strabismus - PMC )。一方、ボツリヌス群は再手術の割合が高いが、この点の証拠は不確かとされている ( Botulinum toxin for the treatment of strabismus - PMC )。
- 限界・適応: 効果の持続期間は数か月程度であり、角度が再び戻れば再注射が必要となる。大きな斜視角や長年放置された斜視(慢性麻痺性斜視)では効果が限定的で、手術や他の治療を検討する場合が多い。副作用として一過性の眼瞼下垂や異常頭位が起こる可能性がある。ボツリヌス療法は短期的な複視緩和手段としては有効だが、長期的な両眼視の獲得には手術療法が優先される場合が多い ( Botulinum toxin for the treatment of strabismus - PMC )。
- 応用例: 一部の斜視手術では、術中にボツリヌス毒素を併用し拮抗筋の収縮を一時的に緩和する工夫が報告されている ( Delhi Journal of Ophthalmology )。また、眼内病変の存在する場合や明らかな原因がない複視においても、ボツリヌス注射が対症療法として試みられることがある。
外科(斜視)療法
- 概要: 持続的な斜視による複視には外科的矯正(眼筋移動術)が行われる。成人では両眼視機能がある例でも、ズレが大きい場合は手術適応となりうる。
- 効果・研究例: 成人の斜視手術は、眼位の修正だけでなく機能的・心理的QOLの改善が認められる ( Diplopia after strabismus surgery for adults with nondiplopic childhood-onset strabismus - PMC )。実際、2017–2019年の研究では成人の小児期発症斜視患者79名を追跡し、術後6週・1年で複視発生率を評価したところ、術後6週では81%が「全く複視なし」になり、1年後でも84%で複視が消失していた ( Diplopia after strabismus surgery for adults with nondiplopic childhood-onset strabismus - PMC ) ( Diplopia after strabismus surgery for adults with nondiplopic childhood-onset strabismus - PMC )。新規の恒常性複視は極めて稀であり(報告では0.8–4%) ( Diplopia after strabismus surgery for adults with nondiplopic childhood-onset strabismus - PMC )、術後に複視が発生してもしばしば軽度であり、QOLは術前より改善することが多い ( Diplopia after strabismus surgery for adults with nondiplopic childhood-onset strabismus - PMC )。
- 限界・リスク: 術後早期には腫脹等で一時的な複視が生じるが、多くは自然軽快する。手術前にプリズムテストで術後複視のリスク評価を行うことが推奨される ( Diplopia after strabismus surgery for adults with nondiplopic childhood-onset strabismus - PMC )。また、手術には他の眼科手術と同様に合併症(感染、出血、過矯正・アンダーコレクションなど)のリスクがある。高齢者(80歳以上)の報告でも、手術は複視の解消・視野改善に有効で大きな合併症なく行われている例がある。術後の頭位異常や眼瞼下垂にも注意が必要である。
薬物療法
- 概要: 複視そのものを直接治す薬物は少ないが、原因疾患に対する薬物治療は重要である。
- 免疫抑制療法: 重症筋無力症ではピリドスチグミン(抗コリンエステラーゼ薬)や免疫抑制剤を使用する ( Management of diplopia - PMC )。甲状腺眼症(Graves眼症)では活動期にステロイドパルス療法や免疫抑制薬が用いられる。最近ではIGF-1受容体阻害薬テプロツマブ(米国FDA承認 2020年)が導入され、中等症以上の活動期眼症で突出眼・炎症のみならず複視の改善効果も報告された (New Data from Teprotumumab Phase 3 OPTIC Study Shows Significantly Reduced Double Vision and Improved Quality of Life for People with Active Thyroid Eye Disease - BioSpace) (Teprotumumab Promising as Treatment For Proptosis, Diplopia)。OPTIC試験ではテプロツマブ群の68%で複視程度が1段階以上改善し、プラセボ群(29%)を大きく上回った (New Data from Teprotumumab Phase 3 OPTIC Study Shows Significantly Reduced Double Vision and Improved Quality of Life for People with Active Thyroid Eye Disease - BioSpace)。
- 血管障害性神経麻痺: 糖尿病性や高血圧性の動眼神経麻痺など微小血管障害性麻痺では、多くの場合6か月以内に自然回復する。これらの症例では原疾患の内科管理を行いながら経過観察し、複視の緩和にはプリズム・遮蔽・ボツリヌス注射などの対症療法を用いる ( Diplopia: Diagnosis and management - PMC )。
- その他: 脳腫瘍、外傷、MSなどの中枢性原因が疑われる場合は原因疾患の治療(例えばステロイド投与、放射線治療、抗腫瘍薬など)を優先し、複視は一時的対症療法(プリズム・遮蔽)で対処する。薬剤性複視として、抗てんかん薬・抗不安薬・抗うつ薬(ラモトリギン、ガバペンチン、セルトラリンなど)や抗生物質(フルオロキノロン)の副作用で複視が起こることがあり、該当薬の中止が必要な場合がある(頻度は低い)。
遮蔽療法(眼帯・視野遮蔽)
- 概要: プリズムや訓練では対応しきれない重度の複視では、一時的に片眼を遮蔽して症状を緩和する。眼帯、遮光眼鏡、レンズのすりガラス化などが用いられる。
- 使用法: 通常は視機能の弱い方の眼を遮蔽する。若年者では遮蔽による弱視(アイシヨス)発症を防ぐため、左右を交替で遮蔽することもある ( Management of diplopia - PMC )。
- 適応・注意点: 虚血性神経麻痺で自然治癒を待つ間や、一時的に目を休める必要がある場合に有効 ( Management of diplopia - PMC )。ただし遮蔽は片眼視になるため両眼視機能が失われるデメリットが大きい。可能な限り短期間の使用にとどめ、患者の生活への影響(運転、作業の可否)を検討する必要がある。
リハビリテーション・新しいアプローチ
- 従来型視覚訓練(オルソプティクス): 両眼協調性を高める訓練が行われる。ブロックストリング、シノプトフォアやアンバドの立体視教材、プラス・マイナスレンズを使った集中・開散訓練などが代表的である。近年の研究では、プリズム治療で複視が不完全に改善した症例に対し視覚訓練を追加することで、生活の質(QoL)がさらに向上することが報告された ( Successful treatment of diplopia using prism correction combined with vision therapy/orthoptics improves health-related quality of life - PMC )。眼科用VR装置を用いたゲーミフィケーション(ゲーム要素を取り入れた訓練)も試みられ、被験者の協調訓練中の反応をモニター可能なシステムが実用化されつつある ( Successful treatment of diplopia using prism correction combined with vision therapy/orthoptics improves health-related quality of life - PMC )。
- 仮想現実(VR)・拡張現実(XR): ヘッドマウントディスプレイ等を用いて両眼に異なる視覚刺激を提示し、立体視や協調眼球運動訓練を行う研究が進んでいる ( Applications and implications for extended reality to improve binocular vision and stereopsis - PMC )。VRは「高精度シノプトフォア」として各眼に色・コントラスト・位置の異なる映像を投影でき、従来器具よりも没入感の高い訓練を可能にする。VR視覚訓練の有用性は提案段階ながら、疾患特異的なプログラムの開発が進みつつある ( Applications and implications for extended reality to improve binocular vision and stereopsis - PMC )。 ( Successful treatment of diplopia using prism correction combined with vision therapy/orthoptics improves health-related quality of life - PMC )
- 遠隔(テレ)リハビリ: 新型コロナ禍以降、遠隔診療や遠隔視覚訓練の利用が増えている。オンラインで視能訓練士や医師の指導を受けられるソフトウェアやアプリが開発されており、通院困難な患者のリハビリ機会を広げている。具体的なエビデンスはまだ限られるが、遠隔での眼運動トレーニングやプリズム処方フォローアップの試みが報告されている。
- 神経リハビリテーション: 脳外傷や脳卒中後に複視を呈する例では、神経眼科学的アプローチが用いられる。眼球運動障害や両眼視機能低下に対し、症候学的に原因(前庭・脳幹・皮質レベル)を検討し、必要に応じてリハビリテーション(視覚優位環境での運動訓練など)を組み合わせる。現状ではランダム化比較試験は少なく、訓練効果の証明は不十分だが、眼球運動の追従訓練や融像訓練が症状緩和に寄与するとされる ( Consensus Statement on Visual Rehabilitation in Mild Traumatic Brain Injury - PMC )。
効果・限界・適応のまとめ
- プリズム眼鏡: 比較的小角度の斜視や不完全な麻痺性斜視で高い効果が得られる(87%で複視消失 ( Prisms in the treatment of diplopia with strabismus of various etiologies - PMC ))。しかし大角度・複合斜視や回旋成分のある複視にはプリズムの度数が過度になり使いにくい。プリズムを使えない症例では遮蔽や手術へ移行する。
- ボツリヌス療法: 手術と異なり組織損傷が少なく繰り返し可能だが、効果は一時的である。即効性があり麻痺筋の伸張抑制に有効な一方、半年以上の長期維持には向かない。副作用として短期的な眼瞼下垂や立体視障害が起こる。医学的には小〜中度斜視や、手術困難例(基礎疾患、手術リスク等)での選択肢となる。
- 手術療法: 最も確実に矯正効果が期待できるが、予測誤差により過矯正や新規複視のリスクが伴う。適応は大角度斜視や複視持続例で、患者の両眼視機能(融像能力)も考慮する。術後の新生複視発生率は低く、むしろQOLや顔貌改善効果が大きい ( Diplopia after strabismus surgery for adults with nondiplopic childhood-onset strabismus - PMC )。高齢者でも手術により複視解消例が報告されており、体力許容範囲であれば年齢だけで否定はされなくなっている。
- 薬物療法: 原因疾患によるが、直接的に複視を治癒させる薬は乏しい。疾患特異的治療の進歩(例:TEDでのテプロツマブ、MGでの新しい免疫療法など)は複視改善につながる。対症的にはステロイド、免疫抑制剤、抗コリン剤などが使われる。薬物療法単独での複視解消は限定的で、他の治療と組み合わせて用いる。
- 遮蔽療法: 簡便だが基本的に一時的対処法で、両眼視機能は得られない。就学前・学童期の患者には弱視誘発に注意する。成人でも運転・読書など機能低下が生じるため、最終手段的に用いられる。
注目トピックと今後の方向性
近年はデジタル技術と遠隔医療の応用が注目されている。VR/AR装置を使った眼筋訓練プログラムや、スマホ・タブレットで行うホームビジョントレーニングの開発が進む。AIによる斜視評価や、患者自身の複視評価を簡易化するツールも研究中である。また、眼筋や神経の再生・可塑性に着目した研究や、新たな分子標的薬(例:眼瞼下垂や外眼筋線維化への介入薬)の開発も今後の方向性として挙げられる。COVID-19以降、リモート診療の拡大に伴い、テレ検査・テレリハビリのエビデンス構築も急務である。患者個々の病態に応じた個別化治療と、QOL改善に焦点を当てた包括的アプローチが今後ますます重視されるだろう。参考文献・重要論文例
- Anilkumar et al., Indian J Ophthalmol. 2022: 31例の複視患者に対するプリズム治療の成績を報告し、87%で複視が消失したと報告 ( Prisms in the treatment of diplopia with strabismus of various etiologies - PMC )。
- Portela-Camino et al., PeerJ 2024: プリズム処方後に視覚訓練(オルソプティクス)を併用した結果、健康関連QOLがさらに改善したと報告 ( Successful treatment of diplopia using prism correction combined with vision therapy/orthoptics improves health-related quality of life - PMC )。
- Rowe et al., Cochrane Database Syst Rev. 2023: ボツリヌス注射と斜視手術を比較した系統的レビュー。手術が斜視改善では優位な可能性を示したが、エビデンスレベルは低いと結論 ( Botulinum toxin for the treatment of strabismus - PMC )。
- Smith et al., N Engl J Med 2020: 活動性甲状腺眼症に対するテプロツマブの第III相試験(OPTIC試験)の結果。複視改善率はテプロツマブ群68%、プラセボ群29%であった (New Data from Teprotumumab Phase 3 OPTIC Study Shows Significantly Reduced Double Vision and Improved Quality of Life for People with Active Thyroid Eye Disease - BioSpace)。
- Lee et al., JAMA Ophthalmol. 2021: 小児期発症の成人斜視患者79例を前向き観察し、術後1年時点で84%に複視消失が認められ、新規恒常的複視は稀と報告 ( Diplopia after strabismus surgery for adults with nondiplopic childhood-onset strabismus - PMC )。
- Subramanian et al., Neurology Clin Pract. 2022: TBI後の視覚障害リハビリに関するコンセンサス声明。複視も含め視覚リハビリの現状とエビデンス不足を論じている ( Consensus Statement on Visual Rehabilitation in Mild Traumatic Brain Injury - PMC ) ( Consensus Statement on Visual Rehabilitation in Mild Traumatic Brain Injury - PMC )。