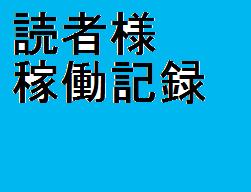職場で高い成果を出す方法:学術研究からの知見
職場で優れた成果を出すためには、個人の行動・思考パターンと周囲の環境の両面が重要であり、多くの研究がこれらの要因を調査しています。以下では、信頼性の高い学術論文の知見に基づき、成果向上につながる個人のスキルや習慣、成果に影響を与える要因、効果的な介入策・制度・組織文化、および実証されたモデルについて整理します。
成果を出すための行動・思考パターン・スキル
職場で成果を上げる個人に共通する行動様式やスキルには、以下のようなものがあります。
-
明確で挑戦的な目標設定: 自分に対して具体的で難易度の高い目標を設定することは、パフォーマンス向上の最も確立された方法の一つです。ロックとレイサムの目標設定理論によれば、困難だが達成可能な目標は個人の努力と成果水準を高め、容易すぎる目標や漠然と「ベストを尽くせ」という指示では効果が劣ることが示されていますmed.stanford.edumed.stanford.edu。明確な目標は注意を重要な課題に集中させ、努力を増加させるメカニズムを通じて業績を押し上げますmed.stanford.edumed.stanford.edu。
-
効果的なタイムマネジメント(時間管理): 時間の使い方を最適化するスキルも成果に直結します。2021年のメタ分析では、タイムマネジメント能力は職務パフォーマンスおよび主観的な幸福に中程度の正の関連を持つことが確認されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。計画的に業務を構成し、優先順位をつけて時間を配分できる人ほど、生産性が高くストレスも低い傾向があります。
-
プロアクティブな行動(主体的な取組み): 指示待ちではなく自ら積極的に動くプロアクティブ行動は、業務改善や新たな価値創出につながります。大規模調査による因果モデル分析でも、プロアクティブに動く社員ほど自己成長や職場への良い影響に対する確信が高く、組織変革を推進する原動力となることが示唆されていますjri.co.jp。主体性を持って問題解決や提案を行うことは、個人の評価や業績向上に寄与します。
-
「成長マインドセット」と学習志向: 成長マインドセットとは、自分の能力は努力や学習によって向上できると信じる考え方です。研究によれば、この思考を持つ人は困難や失敗に直面しても粘り強く挑戦を続け、フィードバックから学習して能力を高めていきますnvca.orgnvca.org。一方、能力は固定的だと考える固定マインドセットの人は困難な環境でパフォーマンスが伸び悩む傾向がありますnvca.org。したがって、逆境でも学び続ける姿勢や学習目標志向(タスクの習熟やスキル向上に焦点を当てる目標志向)は、長期的に高い成果を支える重要な思考パターンです。
-
レジリエンス(心理的回復力)とグリット(やり抜く力): 失敗やプレッシャーに負けずに持続的に努力できる力も成果に影響します。近年の研究では、**グリット(情熱と粘り強さ)**の高い人ほど職務成績が安定的に高いことが報告されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。レジリエンスが高い従業員はストレス状況下でもパフォーマンスを維持しやすく、挫折から早く立ち直って再挑戦することで成果を積み上げます。
-
良好な対人スキルとコラボレーション: チームで働く現代の職場では、コミュニケーション能力や協調性も重要なスキルです。他者と知識を共有し助け合う組織市民行動(OCB)は、直接の職務遂行だけでなく組織全体の生産性や士気向上に貢献することが多くの実証研究で示唆されています(例えば Organ, 1988 の理論と後続研究群)。同僚や上司との信頼関係を築き円滑に協働できる人は、仕事の質と量の両面で成果を出しやすくなります。
成果に影響を与える個人特性と環境要因
仕事上の成果(パフォーマンス)は、個人の能力・特性と職場環境の相互作用によって決まります。研究は以下のような主要因を明らかにしています。
1. 個人特性(能力・パーソナリティなど):
-
一般的な知的能力(認知能力): 過去100年の人事心理学研究によれば、**一般的認知能力(GMA)**は多くの職種において職務遂行と学習能力の最も強力な予測因子ですhome.ubalt.edu。認知テストで測定される問題解決力や学習の速さが高い人ほど、新しい知識を早く習得し成果を上げやすい傾向があります。
-
パーソナリティ(人格特性): ビッグファイブと呼ばれる五つの性格特性のうち、特に誠実性(勤勉で責任感が強い傾向)と情緒安定性(ストレス耐性・ポジティブな安定した気質)は、ほぼすべての職種で高業績と安定した関連を示すことがメタ分析で報告されていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。誠実性が高い人は目標に向け計画的に努力し、締め切りを守り信頼されるため高い評価を得やすいと考えられます。他の特性も職務によって影響があり、例えば外向性は営業など対人場面の多い職種で有利に働く傾向があります(Barrick & Mount, 1991)。一方で経験への開放性や協調性は職種によっては創造性やチームワークを通じて成果に寄与しますが、汎用的な予測力は上記2特性より低いとされていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
-
仕事に対する動機づけ(モチベーション): 内発的動機づけ(仕事それ自体に興味・やりがいを感じること)とエンゲージメント(仕事への熱意・没頭)は、生産性の向上や創造性と正の相関があることが広く知られていますjww.iss.u-tokyo.ac.jp。例えば、日本を含む国際調査では、仕事が「面白い」と感じている従業員ほど職務満足度が高く、学習意欲やタスクパフォーマンスも向上し、離職率が低いことが示されていますjww.iss.u-tokyo.ac.jp。仕事への興味関心のマッチ度や社会的意義の認知が高いことが、その「面白さ」を感じる主な要因でありjww.iss.u-tokyo.ac.jp、ひいては成果向上につながると考えられます。
-
健康・ストレス耐性: 個人の肉体的・精神的健康も安定した成果に不可欠です。過度のストレスや燃え尽き(バーンアウト)は注意力や判断力を低下させ業績悪化を招くため、自己管理(適度な休養・運動・メンタルヘルスケア)も長期的なパフォーマンス維持の要因といえます。実証研究でも、職場の幸福度が高い従業員ほど生産性が高いことが示唆されています。例えばイギリスで行われたフィールド実験では、幸せな従業員は不幸な従業員に比べて13%も生産性が高いという結果が報告されており、因果的に幸福が業績を高める可能性が示されましたox.ac.uk。
2. 環境要因(組織・チームの条件など):
-
リーダーシップ(上司の影響): 上司やリーダーのマネジメントスタイルは部下のパフォーマンスに大きな影響を与えます。特に変革型リーダーシップ(ビジョンを示し、部下を鼓舞し成長を促すリーダー)は、多くの研究で部下の業績や組織への貢献度を高めることが確認されていますresearchgate.net。変革型リーダーは従業員のモチベーションを喚起し、自発的な努力や創意工夫(いわゆるコンテクシュアル・パフォーマンスやOCB)を引き出すため、結果的にチーム全体の成果向上につながります。一方、取引型リーダーシップ(成果に報酬や罰で応じるタイプ)も明確な目標設定とフィードバックを通じてタスクの遂行度合を高める効果がありますresearchgate.net。総じて、上司からのサポート(困難時の支援や相談しやすさ)や適切なフィードバック、期待水準の明確化は、従業員の安心感と努力を引き出し業績を押し上げる重要な環境要因です。
-
目標の明確さとフィードバック: 組織全体で目標や評価基準が明確になっている環境では、従業員は自分に求められる成果を理解しやすく、努力の方向性が定まります。目標管理制度(MBO)などで上司と部下が合意した目標を設定し進捗を定期的にレビューする仕組みは、パフォーマンス向上に有効な手法として広く採用されています。目標達成度についてのフィードバックや業績評価が定期的に行われると、従業員は自らの業績水準を把握し不足を補おうとするため、成果の継続的改善につながります。研究によれば、フィードバックは一般に中程度の正の効果を業績に持ちますが(Kluger & DeNisi, 1996)、具体的で建設的なフィードバックが特に効果的です。
-
職務資源(裁量度・サポートなど): 従業員に与えられる裁量権(仕事の進め方や順序を決められる自由度)や利用できる資源(必要な道具・情報・人員)、および周囲からのサポートは、パフォーマンスに大きく影響します。【Job Demands-Resourcesモデル】の研究では、十分な職務資源がある環境では従業員のワークエンゲージメント(仕事への熱意と集中)が高まり、それが高い業績につながることが示されています(Bakker & Demerouti, 2008)。例えば、人手不足で業務量過多の職場では一人あたりの成果が頭打ちになりますが、適切に人員が補充された場合に生産性が向上するケースも確認されていますrieti.go.jp。また、従業員が仕事の進め方に創意工夫を凝らせる自由度があると、効率的な方法を試行でき成果が上がりやすくなります。
-
組織文化・職場風土: 組織全体の文化も従業員の行動やパフォーマンスを左右します。挑戦を奨励し失敗から学ぶ文化がある職場では、従業員は新しいアイデアに積極的に取り組み、結果的にイノベーションや業績向上が促進されます。一方、失敗を過度に罰する風土や不公平な文化は、萎縮やモラル低下を招き成果に悪影響を与えます。適応力が高く従業員参加を重視する企業文化を持つ企業は、長期的に見て競合他社より高業績を上げる傾向があるとの報告もあります(Kotter & Heskett, 1992)。具体的には、心理的安全性が高いチーム(メンバーが自由に意見でき失敗を共有できる雰囲気)では、学習と問題解決が活発になりパフォーマンスも向上することが実証されています (Edmondson, 1999)。
-
従業員の幸福とワークライフバランス: 先述のように幸福な従業員は生産性が高い傾向がありますが、組織としても従業員のワークライフバランスを支援することは成果向上策の一つです。長時間労働や過度のプレッシャーは一時的に成果を上げるように見えても持続可能性が低く、疲弊した従業員は創造力や注意力が低下してミスや生産性低下を招きます。逆に、働き方改革などで適正な労働時間管理や有給取得の奨励、柔軟な働き方(テレワークやフレックスタイム制等)を導入した企業では、従業員の満足度や創造性が上がり、結果的に生産性が向上する可能性があります。ただし、日本における近年の働き方改革の検証研究では、その効果は施策により様々であることが示唆されています。たとえば、業務プロセスの見直しや非効率業務の削減といった施策は企業の労働生産性を押し上げる効果が見られた一方rieti.go.jp、単に残業時間を減らすだけでは必ずしも生産性向上につながらないケースも多く、平均的には柔軟な勤務制度導入など単独の施策の効果は限定的だったと報告されていますrieti.go.jp。組織文化や現場の運用と組み合わせて、従業員の健康と生産性の両立を図る総合的な取り組みが重要といえます。
成果を高める介入策・制度・組織文化
上記の要因を踏まえて、実務的に職場で成果を高めるための介入や制度設計、文化づくりには以下のようなものが効果的とされています。
-
目標管理と成果評価制度の整備: 代表的なものに**目標による管理(MBO: Management by Objectives)があります。これは組織の目標と個人の目標を連動させ、各従業員が何を達成すべきかを明確にした上で定期的に振り返りを行う仕組みです。適切な目標設定とフィードバックサイクルは、従業員のモチベーションと集中度を高めることで、多数の研究がパフォーマンス向上に効果があると支持していますmed.stanford.edu。最近では、より機動的に目標を管理する手法としてOKR(Objectives and Key Results)**を採用する企業も増えており、これも目標設定理論に基づくアプローチです。
-
高業績を促す人事施策の一貫導入(ハイパフォーマンス・ワークシステム): 人材の採用・育成・評価・報酬・職務設計などを戦略的に一貫させて従業員の能力と意欲を最大化しようとするハイパフォーマンス・ワークシステム(HPWS)は、組織パフォーマンス向上策として広く研究されていますpmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov。具体的には、厳選採用と徹底した訓練、成果に応じた報酬や昇進、公平で透明性の高い評価制度、従業員参加や協働を促す組織設計などのプラクティスを組み合わせて導入するものです。メタ分析によれば、HPWSを導入した企業はそうでない企業に比べ中程度ではあるが一貫して高い業績(財務業績や生産性)を示すことが確認されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。例えば、従業員への定期的なスキル訓練やキャリア開発支援は仕事の質を高め、生産現場ではチームによる問題解決活動(QCサークルなど)が不良率の低減や効率化に寄与するという報告があります。一方で、単に制度を導入するだけでなく、現場で従業員がそれらを実感し活用できるように運用することが重要であると指摘されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。制度と従業員体験のギャップを埋めるため、ラインマネージャーのリーダーシップや実践が鍵となります。
-
インセンティブ(報奨制度)の活用: 適切なインセンティブ制度も成果を押し上げる手段です。初期の研究から、生産量に応じた出来高給与や業績連動賞与は、短期的には労働者の生産性を高める有効な方策であることが示されていますjil.go.jp。目標達成に報奨(金銭的・非金銭的)を結びつけると、従業員は努力を惜しまず成果を上げようとする傾向があります(期待理論の文脈でも説明されます)。ただし、インセンティブ設計には注意が必要で、何をもって成果とするかを慎重に定義しないと不適切な行動(例えば短期成果を優先するあまり品質や倫理がおろそかになる等)を誘発するリスクも指摘されています。近年は金銭報酬だけでなく、表彰制度やキャリア上の機会提供といった非金銭的インセンティブも、内発的動機づけを高める観点から重視されています。
-
リーダーシップ開発とマネジメント研修: 組織として管理職に対し効果的なリーダーシップ研修を行うことも、部下の成果向上に間接的に効きます。変革型リーダーシップのスキル(ビジョン提示、コーチング、知的刺激の提供、公平な扱い等)は訓練可能であり、研修によりマネージャーがこれらを実践できるようになると職場の雰囲気や部下のパフォーマンスが改善します。また、最近注目されるコーチング型リーダーシップやサーバント・リーダーシップ(部下支援に徹するリーダーシップ)も、従業員の自主性と成長を促し成果につなげる有効なアプローチです。優れた上司を育てることは、組織全体の生産性向上策として極めて重要です。
-
働き方改革と職場環境の見直し: 前述のように、長時間労働の是正やテレワーク導入、フレックス勤務などの働き方改革も、生産性向上のポテンシャルを持ちます。例えば、ある調査では在宅勤務の活用により通勤時間が削減され集中できる時間が増えた結果、生産性が上がったという報告もあります。一方で、単に働く時間や場所を変えるだけでは十分でなく、**業務プロセス自体の効率化や不要な業務の削減(業務の選別)**が伴って初めて顕著な成果改善につながるとされていますrieti.go.jp。したがって、制度導入と並行して業務フローの改革やIT活用、権限委譲など総合的な取り組みを行う必要があります。組織文化としても、生産性向上の基本として無駄な会議の削減や仕事の優先順位付けの徹底など、「働き方」に対する意識改革を全社員で共有することが成果に結びつきます。
-
継続的改善(カイゼン)と知識共有: 日本発の経営手法である**カイゼン(継続的改善)**も、高い成果を維持する組織文化として注目されます。日々現場で小さな改善を積み重ねる企業は、停滞せず生産性や品質を向上させ続ける傾向があります。また従業員が自分の仕事をより良くするアイデアを提案し実行できる仕組み(提案制度やQC活動など)は、現場レベルでの効率化と士気向上につながり、結果的に大きな成果差となって現れます。こうした文化を根付かせるには、経営層が改善提案を奨励し成功を称賛すること、失敗を咎めず学びの機会とすることが重要です。
実証された有効な手法・モデルの例
最後に、仕事で成果を高めるための理論モデルやフレームワークの中で、特に実証研究で有効性が確認されているものをいくつか挙げます。
-
目標設定理論(Locke & Latham): 前述の通り、具体的で困難な目標を設定し、進捗に対してフィードバックを与えることで動機づけと業績向上が図れるという理論ですmed.stanford.edu。この理論は世界中の職場で応用され、MBOやOKRの基本原理ともなっています。
-
変革型リーダーシップ理論(Bass): リーダーがビジョンを示し、個々の成長に配慮し、知的刺激を与えることで、従業員の越境的な努力(単に与えられた仕事をこなす以上の自主的な貢献)を引き出せるというモデルです。メタ分析により、そのようなリーダーの下で部下のタスク遂行能力だけでなく文脈的パフォーマンス(創造性・協調行動など)が特に向上することが確認されていますresearchgate.netresearchgate.net。
-
自己決定理論(Deci & Ryan): 報酬や命令による他律的な動機づけよりも、自律性・有能感・関係性という基本的欲求が満たされた時に人は最も意欲的に創造的に働けるとする動機づけ理論です。この理論に基づき、社員にある程度の裁量と成長機会を与え、同僚や上司との良好な関係性を築くことができる環境を整えることで、内発的動機づけが高まり持続的な高パフォーマンスにつながることが示唆されています。例えばGoogle社が20%ルール(業務時間の一部を自主プロジェクトに充てる制度)を導入しイノベーションを生んだのは、自己決定理論の考え方と合致します。
-
仕事要求-資源モデル(JD-Rモデル): 職場の**ストレッサー要因(仕事上の要求)と活力源(仕事の資源)**のバランスが従業員の燃え尽きやエンゲージメントを規定し、それが業績に波及するというモデルです。要求過多で資源が少ないと疲弊して成績が落ちますが、資源(裁量、サポート、フィードバックなど)が豊富だと高いエンゲージメントを生み出し成果向上につながるとされています。このモデルは職場環境の診断と介入策(例えば業務負荷の是正や支援制度の充実)に広く用いられています。
-
働き方改革関連モデル: 日本における働き方改革では、長時間労働の是正やテレワーク推進、同一労働同一賃金など様々な施策が包括的に導入されました。これらは総じて従業員の多様な事情に対応し、健康と生産性を両立することを目指すものです。学術的検証によれば、一部の施策(例えば業務プロセス改善や人員適正化)は生産性指標の向上に有意な効果を持つもののrieti.go.jp、他の施策は短期的な効果が限定的であったり企業間でばらつきがありますrieti.go.jp。重要なのは、これら制度を企業文化の変革とセットで実行し、管理職の意識改革や現場の主体性向上と組み合わせることです。例えば「ノー残業デー」を形だけ導入しても成果は出ませんが、業務効率化と仕事の優先度見直しを徹底しつつ導入すれば生産性向上と社員の満足度向上の双方が得られます。
-
その他のモデルや手法:
-
リーン生産方式・シックスシグマ: 製造業発の手法ですが、ムダを省き品質を高めるプロセス改善手法として他業種にも応用されています。業務プロセスの継続的改善により成果を上げるモデルです。
-
アジャイル型の仕事の進め方: ソフトウェア開発から広がった手法で、小さなチームが短いサイクルで計画・実行・振り返りを繰り返す働き方です。これにより迅速なフィードバックと適応が可能となり、変化の激しい業務環境下で成果を上げやすくなるとの報告があります。
-
メンター制度・コーチング: 経験豊富な人が後進を指導する制度や、専門のコーチが個人の目標達成を支援するプログラムも、スキル向上と成果改善に寄与することが実証されています。従業員が自らの潜在力を発揮できるよう支援するこれらの取り組みは、人材育成と業績向上を両立する手法です。
-
以上のように、個人の主体的な行動・スキル習得と組織の制度・文化的支援の双方が相まって、職場で高い成果を生み出すことが多くの研究で示されています。特に、「明確な目標」「高い意欲と能力」「良質なリーダーシップと環境」が揃ったとき、個人も組織も最大限のパフォーマンスを発揮できると考えられますmed.stanford.eduresearchgate.net。これらの学術知見を踏まえて、人と組織の在り方をデザインすることで、持続的な成果創出につながるでしょう。
参考文献(一部):
-
Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57(9), 705-717med.stanford.edumed.stanford.edu.
-
Aeon, B., & Aguinis, H. (2021). Does time management work? A meta-analysis. PLoS ONE, 16(1), e0245066pmc.ncbi.nlm.nih.gov.
-
Salgado, J. F. (1997). The five factor model of personality and job performance in the European Community. Journal of Applied Psychology, 82(1), 30-43pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.
-
Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology. Psychological Bulletin, 124(2), 262-274home.ubalt.edu.
-
Wang, G., Oh, I-S., Courtright, S. H., & Colbert, A. E. (2011). Transformational leadership and performance across criteria and levels: A meta-analytic review. Group & Organization Management, 36(2), 223-270researchgate.net.
-
明日山陽子 (2021). 「仕事の面白さの決定要因:日本とその他高所得国の比較」『Labour Economics』73号の和訳jww.iss.u-tokyo.ac.jpjww.iss.u-tokyo.ac.jp.
-
池田浩 (2017). 「ワークモチベーション研究の現状と課題」『日本労働研究雑誌』7月号jil.go.jp.
-
RIETI (2021). 「働き方改革の広がりと実効性」RIETIディスカッションペーパーrieti.go.jprieti.go.jp.
-
日本総合研究所 (2023). 「プロアクティブ行動が組織パフォーマンスにつながる因果モデル」調査レポートjri.co.jp.
-
De Neve, J.-E., et al. (2019). Happiness at work. Saïd Business School & BT調査ox.ac.uk.