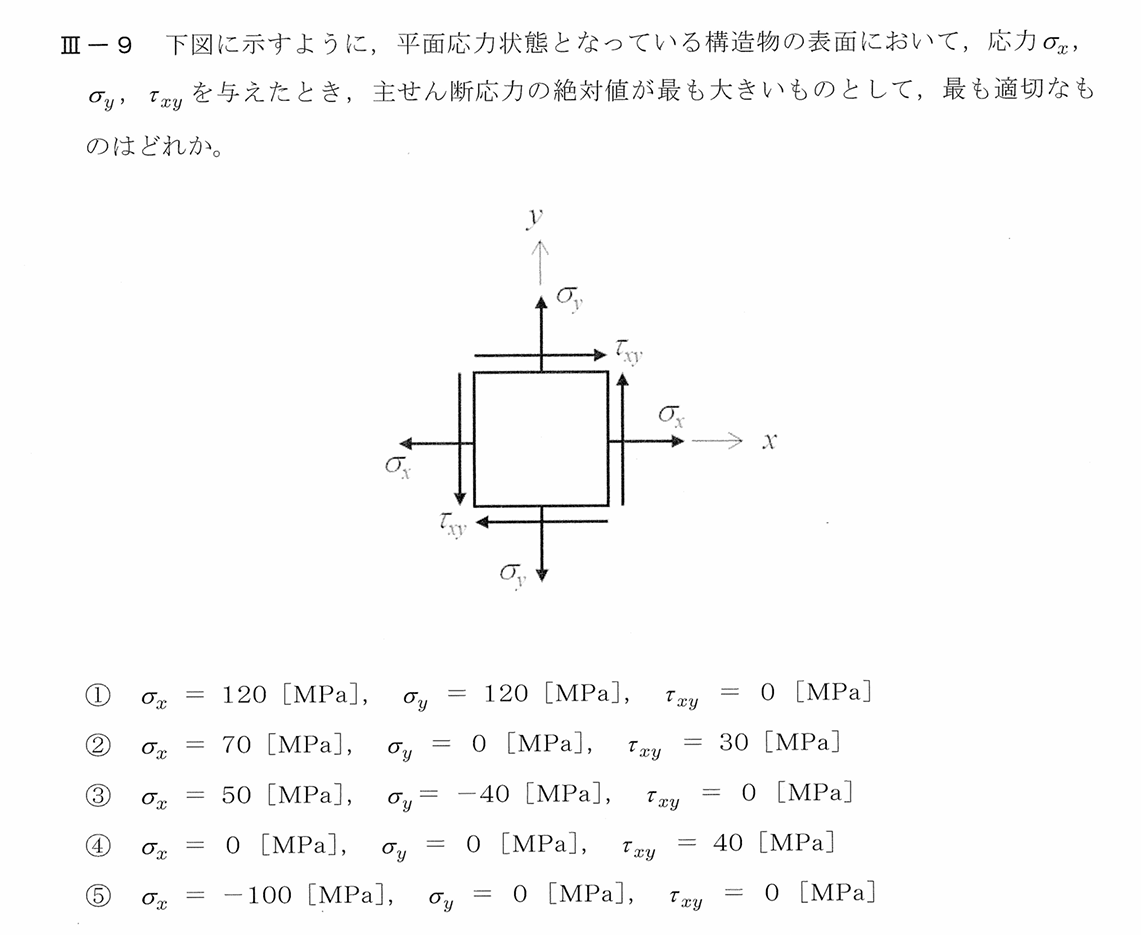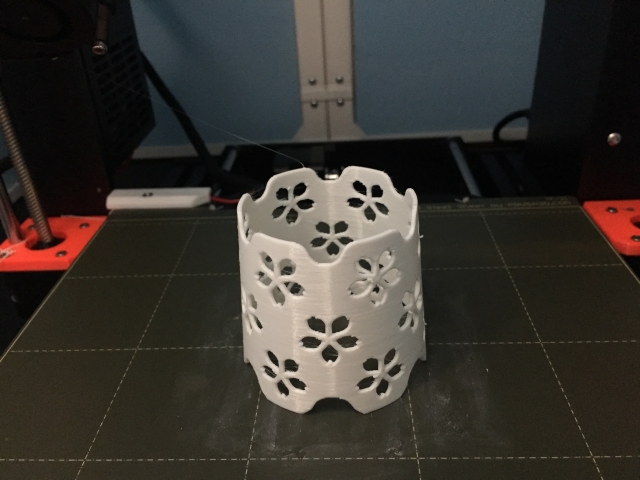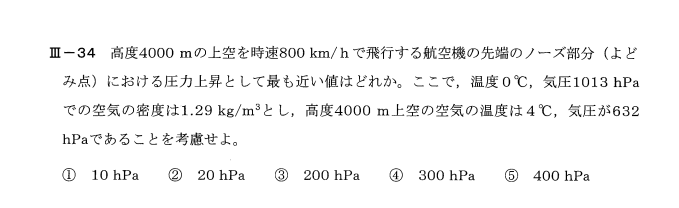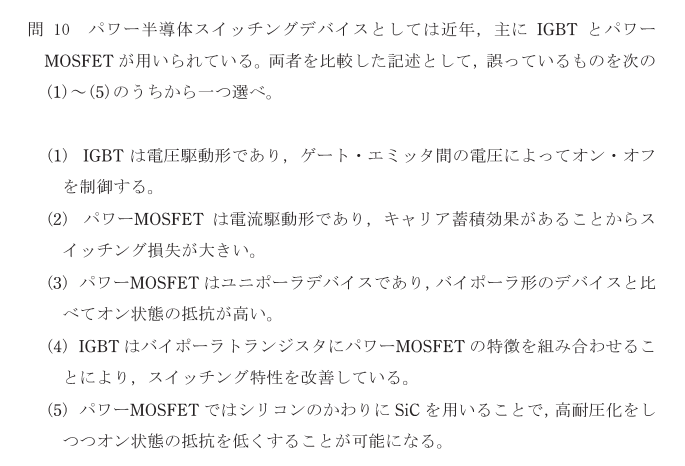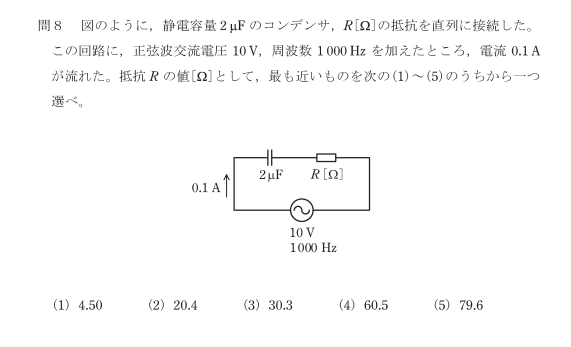これは2次元流れの z 成分の渦度(xy 平面に直交する方向の渦度)で、
与えられた
ゆえに
答え:⑤ 0
参考:技術士第一次試験-令和2年度機械部門Ⅲ-32解答例 | 技術士のたまご
渦 | 副業の宮殿【PR】
これは2次元流れの z 成分の渦度(xy 平面に直交する方向の渦度)で、
与えられた
ゆえに
答え:⑤ 0
参考:技術士第一次試験-令和2年度機械部門Ⅲ-32解答例 | 技術士のたまご
渦 | 副業の宮殿【PR】
Z方向の渦度にはZ方向の速度ベクトルは関係がないのですか?
その通り、z方向の渦度( )の式には z 方向の速度成分 は現れません。一般の三次元速度ベクトル に対して渦度ベクトルは で、各成分は だから (=z軸周りの局所的な回転)は の x,y に関する変化だけで決まり、 の大小や分布は直接関係しません。 直感的には: は xy 平面内での回転(z軸を中心とした渦)を表すので、その原因は横方向成分 のせん断であり、軸方向の流れ 自体はその回転を生まない、ということです。 ただし が や で変化すると、 には寄与し、それらの成分を通じて渦の構造全体に間接的な影響(たとえば渦の伸長・捻じれなどのダイナミクス)を与えることはあります。Z方向の渦度とは、Z軸まわりの渦度ということですね
その通りです。 は z 軸まわりの回転の強さ(渦度の z 成分)で、式で言うと です。これは xy 平面内の局所的な回転(z 軸を中心とした渦)の度合いを表します。 補足すると、渦度ベクトル は流体要素の局所的な角速度の 2 倍に相当し、右ねじの法則に従って向きが決まります。たとえば なら、正の z 軸方向から見て流れが 反時計回り に回っていることを意味します。x 方向に進むにつれて、y 方向の速度がどう変化するか。 をu=A(x+y)とu=A(x+dx+y)みたいにしなくていいのですか?
とても鋭い質問です。 結論から言うと、あなたが書いたような [ u = A(x + y), \quad u = A(x + dx + y) ] のような「2点を比較する考え方」は微分の出発点として正しいです。 ただし、実際の式((\frac{\partial v}{\partial x}) など)では、その 差分を極限的に小さくした結果(1点での傾き) を表しています。🔹 1. 微分の定義から見ると
偏微分は「他の変数を固定して、ある方向にほんの少し進んだときの変化率」です。 たとえば、 [ \frac{\partial v}{\partial x} ] の定義は [ \frac{\partial v}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{v(x + \Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x}. ] つまりあなたの言う(v(x, y)) と (v(x + dx, y)) の差を取るのはまさにこの式の出発点です。
🔹 2. 渦度式の「2つの偏微分」はこう理解できます
[ \omega_z = \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x}}_{\text{x方向の変化(vの傾き)}}
\underbrace{\frac{\partial u}{\partial y}}_{\text{y方向の変化(uの傾き)}} ] それぞれは「隣り合う微小領域の速度差を極限でとったもの」なので、 「2点での差」ではなく「1点での変化率(傾き)」として扱います。🔹 3. 例:(u = A(x + y), v = A(x - y)) の場合
まず、各偏微分を普通に計算します: [ \frac{\partial v}{\partial x} = A,\quad \frac{\partial u}{\partial y} = A. ] だから (\omega_z = A - A = 0)。 でも実際の定義に戻ると、 [ \frac{\partial v}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{v(x + \Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{A[(x + \Delta x) - y] - A(x - y)}{\Delta x} = A. ] 同様に (\frac{\partial u}{\partial y} = A)。 これが偏微分の「2点比較」的な出発点の形です。🔹 4. まとめ
| 概念 | 数式 | 物理的意味 |
|---|---|---|
| あなたの式(2点) | (v(x+dx,y)-v(x,y)) | ある小さな距離でどれだけ速度が変わるか |
| 偏微分の式 | (\frac{\partial v}{\partial x}) | その差を dx→0 にした極限(1点での傾き) |
| 渦度の式 | (\omega_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}) | 流体要素の回転率(x・y方向の変化の差) |
したがって、
「2点の微分が必要では?」 という感覚はとても正しいです。 数学的には、その2点の差を極限的に近づけて1点での変化率にしたのが偏微分であり、 渦度の式はその結果を使って局所的な回転を評価しています。