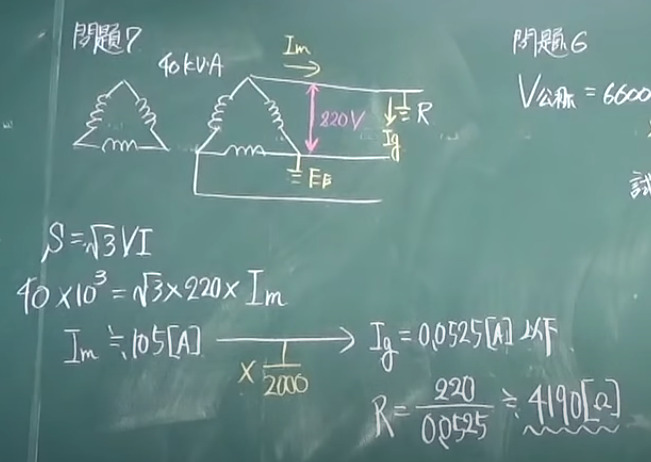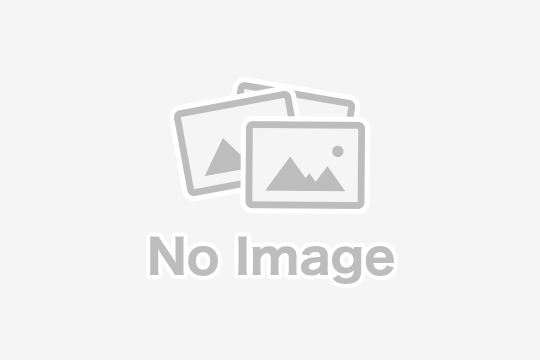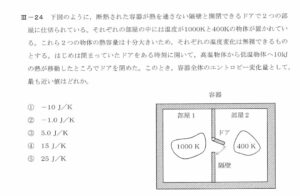
はい。解きます。
問題の要点
- 断熱された全体の系(ドアを開けて熱交換が起きた後閉じる)で、高温側(1000 K)から低温側(400 K)へ 10 kJ の熱が移動した。
- 各物体の温度は熱容量が十分大きいため変化しない(定温過程とみなせる)。
- 全系のエントロピー変化を求めよ。
解法
熱が高温側から低温側へ移るときのエントロピー変化は:
ここで
が高温→低温に移動した量なので、
- 低温側(400K)に入る熱:
- 高温側(1000K)から出る熱:
よって:
答え
④
15 J/K
参考:
技術士第一次試験-令和2年度機械部門Ⅲ-24解答例 | 技術士のたまご
エントロピーとは何ですか?
もちろんです。エントロピーの概念を直感的・定量的に分けて説明します。
1. 直感的なイメージ
エントロピーは「系の取りうる状態の数の多さ」や「広がりや乱雑さの度合い」を測る量です。たとえば:
- 熱が高温から低温に自然に流れるのは、エントロピー全体が増える方向だから(自然な進行方向=時間の矢)。
- 粒子が一か所に集まっているよりも、ばらけている方が取りうる内部状態が多く、エントロピーが大きい。
- 「秩序」→「無秩序」に見える変化は、マクロでエントロピーが増える現象と関係がありますが、「単なる乱雑さ」だけではなく、取り得る微視的状態の数の増加が根底にあります。
2. 熱力学的定義(マクロな系での定義)
可逆(理想的な)過程で系に与えられた微小な熱
を温度
で割ったものを積分したものがエントロピーの変化:
例:温度
の系に可逆的に
の熱を入れると、
単位はジュール毎ケルビン(J/K)。
孤立系では、エントロピーは減らない(増大するか一定)。これが熱力学第二法則の一部です。
3. 統計力学的な定義(微視的な解釈)
系が取り得る微視的状態の数を
とすると、エントロピーは:
ここで
はボルツマン定数(
)。
状態の数が増える(可能性が広がる)と
が増え、結果として
も大きくなる。
4. 情報理論との類似(シャノンエントロピー)
確率分布
を持つ選択肢の不確実性(情報の平均量)はシャノンエントロピーで:
物理のエントロピーと形式的に似ていて、確率的に「どれだけの情報(不確実性)」があるかを測る。
熱力学的エントロピーは確率分布(微視的状態の重み)を自然対数で扱った形に対応します。
5. よくある誤解の整理
- エントロピー = 単なる「乱雑」ではなく、「可能な内部状態の数の対数的な広がり」。
- エントロピーが増える方向が「自然な時間の進み方」だが、局所的に減ること(冷却や秩序化)は外部とのやり取り(全体ではエントロピー増大)によって可能。
- 熱が高温から低温へ流れるのは、全体のエントロピーが増えるから起きる(自発的な過程)。
まとめ
- 定義(可逆熱):
- 統計解釈:
(状態数の対数)
- 性質:孤立系でエントロピーは増えるか一定(第二法則)。
- 単位:ジュール毎ケルビン(J/K)。
必要なら、具体例(気体の膨張、混合、熱エンジン効率との関係など)や問題演習も出せます。どちらがよいですか?
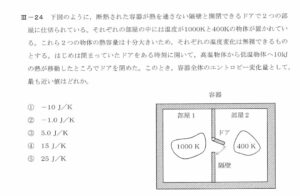 はい。解きます。
はい。解きます。