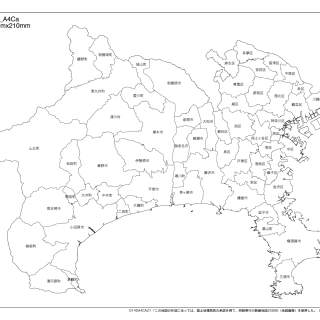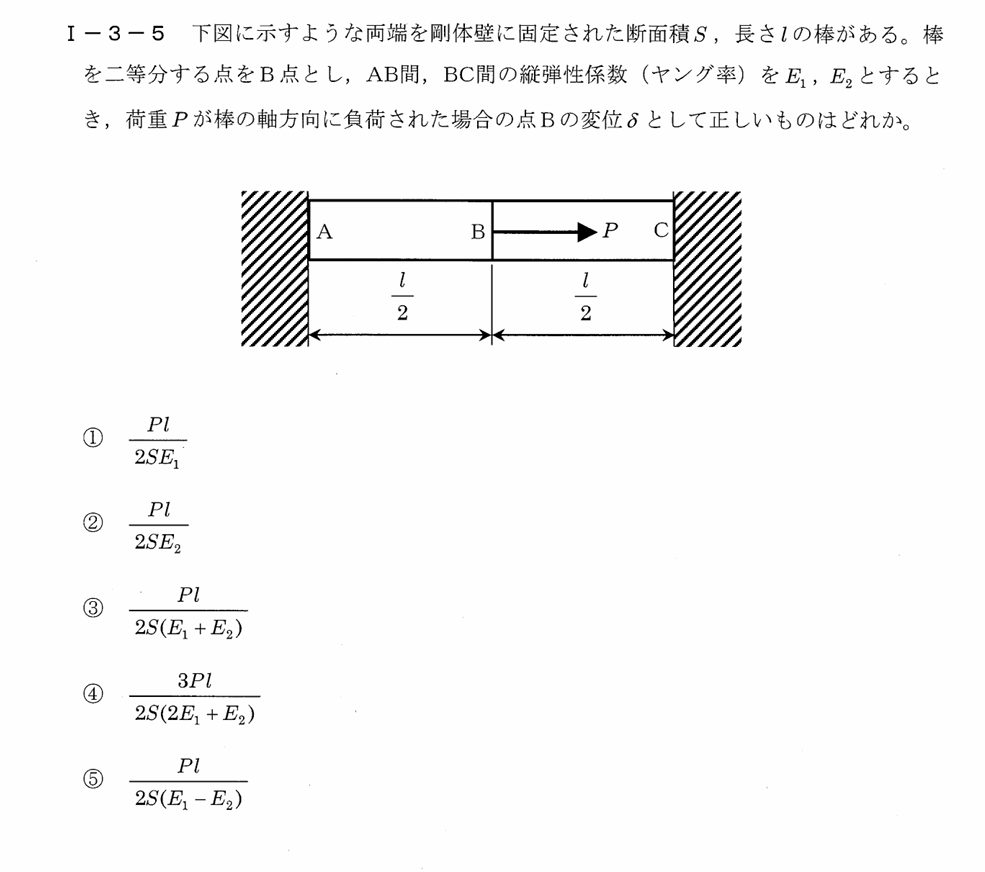子どもの食後腹痛に関する包括的レビュー
はじめに
食後腹痛とは、食事をとった後に生じる腹痛を指します。小児の慢性的あるいは反復性の腹痛の大半は機能性腹痛(器質的な異常がない腹痛)ですが、中には治療を要する器質的疾患が原因となっている場合もあります。本レビューでは、子どもの食後腹痛の代表的な原因とそれぞれの病態生理、診断アプローチ、治療法、予後および再発傾向、疫学データについて、国内外の最新の知見を交えて整理します。
代表的な原因と病態のメカニズム
機能性消化管障害(FGIDs)と過敏性腸症候群(IBS)
機能性消化管障害とは、慢性的または再発性の消化器症状があるにもかかわらず、十分な医学的評価でも原因となる器質的疾患が認められない疾患群です。代表的なものに過敏性腸症候群(IBS)、機能性ディスペプシア、腹部片頭痛、機能性腹痛症候群などが含まれ、小児の反復性腹痛の最も一般的な原因を占めます。IBSは特にその中核をなす疾患で、腹痛とそれに関連する便通異常を特徴とします。小児のIBS有病率は調査によりおよそ6~14%と報告されています。
IBSの病態生理には、内臓知覚過敏(腸の痛み刺激に対する過敏性)と消化管運動障害が基本にあり、遺伝素因・環境要因・腸管の軽度炎症・食物アレルギー・不安やうつ傾向・ストレスなど多因子が関与します。ストレスなど心理社会的要因により脳と腸の双方向のやり取り(脳腸相関)が乱れ、痛みが引き起こされると考えられています。実際、小児の慢性腹痛は新学期など心理的ストレスが契機となったり、親の注意を引きたい状況で誘発されることがあり、IBS患児の約半数では先に腸の異常が起こりそれが精神的苦痛を招く例(腸炎後IBSなど)も報告されています。食事もIBS症状の誘因となりやすく、食後に腹痛や便意切迫が増強することがあります。これは食事による消化管反射(胃・結腸反射など)が過敏に働くためと考えられます。またIBS患者では特定の食品(脂肪分の多い食事やガス産生しやすい食事など)で症状が悪化することも知られています。
**機能性ディスペプシア(FD)は食後の上腹部痛やもたれ感を主症状とする機能性障害で、小児でも思春期を中心に認められます。Rome IV基準では食後の不快感(満腹感や膨満感)が持続する食後愁訴症候群(PDS)と、空腹時~食間の心窩部痛が中心の心窩部痛症候群(EPS)**に分類されます。食後腹痛としてはPDSタイプが該当し、胃の運動機能低下(胃排出遅延)や胃の知覚過敏が病態に関与します。IBSと同様にストレスで悪化しやすく、小児ではIBSとFDがオーバーラップすることもあります。
腹部片頭痛も小児特有の機能性腹痛の一つです。これは数時間~数日持続する間欠的な激しい腹痛発作で、間欠期には無症状となるのが特徴です。チョコレートなど特定の食品やストレスが誘因となることがあり、偏頭痛の一種と考えられています。腹痛発作に嘔気・嘔吐や皮膚蒼白を伴うことが多く、家族歴として片頭痛持ちの家族がいる場合に疑われます。腹部片頭痛も器質的検査で異常がなく診断される機能性腹痛の一類型です。
食物不耐性(乳糖不耐症・その他の吸収不良)
食物不耐性とは、特定の栄養素を消化・吸収できずに症状を来す状態です。代表的なものに乳糖不耐症があります。乳糖(ラクトース)を分解する酵素ラクターゼが不足すると、大腸で乳糖が発酵・ガス産生して腹部膨満や腹痛、下痢を引き起こします。乳糖不耐症による腹痛は乳製品摂取後30分~数時間以内に生じ、程度は摂取量に依存します。遺伝的背景により思春期以降にラクターゼ活性が低下する「一次性ラクターゼ欠損」が世界人口の約70%にみられ、特にアジア人では成人までにほぼ100%が乳糖不耐になると報告されています。ただし小児期(5歳以下)に乳糖不耐症が症状を起こす頻度は低く、フィンランドの小児では2%程度ですが、米国南部の小児では24%との報告もあり人種・地域差があります。一方、腸炎後やセリアック病などで二次的にラクターゼが低下する続発性乳糖不耐症も小児ではあり、ロタウイルス腸炎などの後に一時的に乳糖摂取で下痢が続くことがあります。
乳糖以外にも、フルクトース(果糖)やソルビトールなど特定の糖類の吸収不良は腹痛・下痢の原因となります。果汁や清涼飲料の過剰摂取で小児の腹痛が誘発されることがありますが、これも浸透圧性下痢とガスによる腹部症状が機序です。フルクトース不耐症の診断には呼気水素試験がありますが、小児では偽陽性も多く乳糖・果糖不耐症のスクリーニング検査は信頼性が限定的と指摘されています。そのため疑わしい場合は一定期間の除去食試験が有用です。
グルテン不耐性(セリアック病)も重要な食物不耐性です。セリアック病は小麦や大麦に含まれるグルテンに対する自己免疫反応で、小腸粘膜に炎症・絨毛萎縮を起こします。症状は腹痛・下痢・腹部膨満に加え、体重減少や発育不良、貧血、皮疹(Dermatitis herpetiformis様の発疹)など多彩です。食後に症状悪化しやすい点では「食後腹痛」の一因となり得ます。セリアック病は欧米に多く日本では稀とされますが、近年診断例が報告されており注意が必要です。診断には抗tTG-IgA抗体スクリーニングが有用で、陽性であれば内視鏡生検で確定診断します。無治療では成長障害や骨粗鬆症、腸リンパ腫などのリスクがあるため、確定すれば厳格なグルテンフリー食による管理が必要です。
そのほか、小児では稀ですがスクロース-イソマルターゼ欠損症(先天性の砂糖・デンプン分解酵素欠損)により砂糖やデンプン摂取後に腹痛・下痢をきたす場合があります。またFODMAP(発酵性オリゴ糖・二糖・単糖・ポリオール)と総称される難消化性の糖類はIBSを含む機能性腹痛症候群で症状を悪化させることが知られ、近年低FODMAP食が思春期以降のIBS患者で試みられています。
食物アレルギー・過敏症
食物アレルギーでも食後の腹痛が生じます。典型的なIgE介在性食物アレルギー(即時型アレルギー)では、原因食品摂取後数分~1,2時間以内にじんま疹や喘鳴、嘔吐などが出現しアナフィラキシーを呈することがありますが、腹痛もこれら全身症状の一部として起こり得ます。ただしこうした急性型では腹痛より蕁麻疹や呼吸器症状が目立つ傾向があります。
一方、非IgE依存性の食物過敏症として食物たんぱく誘発胃腸症候群(FPIES)が知られます。FPIESは乳児に多く、原因食摂取後1~4時間ほどで激しい嘔吐、下痢、顔面蒼白や低血圧(ショック)をきたす重篤な反応です。腹痛も顕著ですが低血圧や嘔吐によりぐったりするため表現されにくいことがあります。原因食は米や牛乳・大豆が欧米では典型ですが、日本では鶏卵が原因の半数以上を占めるとの報告があります。FPIESではアレルギー検査(IgE抗体)は陰性で、症状から診断します。治療は原因食の除去と、誤食時の迅速な輸液・ステロイド投与など救急対応です。多くは3歳頃までに寛解します。
さらに、消化管に好酸球が浸潤する好酸球性消化管疾患(EGID)も食物抗原が関与する慢性アレルギー性疾患です。代表的な好酸球性食道炎(EoE)では食後の胸やけや嚥下困難が主症状ですが、小児では腹痛や嘔吐で発症することもあります。好酸球性胃腸炎では腹痛・下痢・蛋白漏出性腸症など多彩な症状を呈します。EGIDは内視鏡生検で診断され、治療は除去食(原因となる食品群の除去)やステロイド投与です。近年、EoE患者の多くで典型的なIgE型ではない食物アレルギー機序が関与していることが明らかになってきました。IBS患者の一部にも軽度の食物過敏反応(非IgE型)が症状に関与する可能性が示唆されています。
腸閉塞など器質的な消化管通過障害
食後に痛みが悪化する疾患として、**腸閉塞(イレウス)**やその一歩手前の状態が挙げられます。食事により消化管内容が増えると、狭窄や閉塞の部位で内圧上昇し痛みや嘔吐が誘発されるためです。小児の慢性的な腸閉塞原因には以下が考えられます:
-
上腸間膜動脈症候群(SMA症候群): 十二指腸の第三部(水平部)が上腸間膜動脈(SMA)と大動脈の間で圧迫され、胃・十二指腸の通過障害を起こす疾患です。著明な体重減少で腸間膜脂肪が減少することなどが誘因となります。頻度は極めて低く、一般集団で0.013~0.3%程度と報告されています。小児では先天的な腸間膜の角度異常や長期臥床のほか、思春期の急激な身長増加に体重増加が追いつかない場合に発症した例もあります。症状は食後の心窩部痛、嘔吐、早期満腹感、体重減少で、重症化すると飲食が困難になります。診断は造影検査やCT/MRアンギオグラフィーでSMAと大動脈の角度狭小化を確認します。治療はまず保存的治療(高カロリー食・体位工夫)で体重回復と症状改善を図り、難治例では十二指腸空腸バイパス術などの外科治療を検討します。
-
中弓靭帯症候群(MALS): 腹部大動脈から最初に分岐する腹腔動脈が、ダイアフラムの繊維性構造である中弓靭帯によって圧迫されることにより起こる症候群です(別名腹腔動脈圧迫症候群、ダンバー症候群)。食後の上腹部痛、悪心・嘔吐、著しい体重減少、食事への恐怖(食べると痛むため食事を避ける)といった症状が典型です。10万人に約2人と稀な疾患ですが、若年女性に多く(女性:男性比約4:1)、小児でも思春期の女児に発症することがあります。機序は食後に増加する腸管血流需要に対し、圧迫された腹腔動脈では十分な血流が供給できず腸管虚血が起こるという説と、腹腔動脈近くの神経叢が圧迫され神経性の痛みを生じるという説があります。実際には両者が関与する可能性もあります。MALSは診断が難しく、「腹痛の原因不明」で長く経過した後に発見されることが多い疾患です。診断にはCTAや腹部超音波ドプラでの腹腔動脈狭窄の確認、さらに確定のため腹腔神経節ブロックが有用です。治療は腹腔動脈を圧迫している靭帯の外科的切離(MALS手術)で、報告によっては術後84%で症状寛解との成績もあります。小児のMALSでは腹腔鏡下手術による痛みの劇的な軽快が報告されており、器質的疾患が否定された難治性の食後腹痛では念頭に置く必要があります。
-
便秘による腸管内圧亢進: 意外かもしれませんが、便秘(慢性的な便の貯留)も小児腹痛の極めて一般的な原因です。食事をすると消化管の蠕動が活発になり(胃結腸反射)、満杯の大腸が刺激されて痛みを生じることがあります。小児急性腹痛症の原因としても便秘は最も多い鑑別であり、慢性でも腹痛を訴える小児の多くに程度の差はあれ便秘が関与します。固い便塊が腸管を部分閉塞することでも食後の疝痛が起こりえます。便秘自体は機能的な要因と考えられますが、治療しないと器質的合併症(糞便性腸閉塞や糞石など)を招くため、腹痛患児では必ず便秘の評価と対応が必要です。
-
その他の部分的通過障害: 先天性の腸回転異常(Ladd靭帯による十二指腸圧迫)や、腹腔内癒着、腸重積の反復発症なども考慮されます。腸重積は通常乳幼児の急性疾患ですが、まれに一過性に整復されて繰り返すことがあります。また潰瘍性大腸炎やクローン病といった**炎症性腸疾患(IBD)**で腸管狭窄や炎症性ポリープによる狭窄が起これば、食事のたびに狭窄部で痛みが生じる可能性があります(IBD自体の腹痛はしばしば食事と関連なく出現しますが)。消化性潰瘍(胃潰瘍・十二指腸潰瘍)も食後痛の代表原因です:胃潰瘍では食後すぐ痛み、十二指腸潰瘍では空腹時~次の食事前に痛む傾向があります。ピロリ菌感染のある学童で潰瘍が見つかることも稀ながらあり、腹痛の持続や夜間痛がある場合は考慮されます。
血流異常(腸管虚血など)
先述のMALSは血流異常による腹痛の代表ですが、それ以外にも腸間膜の血流障害は激烈な食後腹痛を来すことがあります。成人では動脈硬化による慢性腸間膜動脈閉塞症(いわゆる腹部アンギーナ)が知られ、食後30分ほどで耐え難い腹痛発作が起こり体重減少と食事恐怖を呈します。しかしこの疾患は小児では極めてまれです。小児では血管炎(川崎病やIgA血管炎[ヘノッホ・シェーンライン紫斑病])で一過性に腸管虚血や腸重積を起こし腹痛が出現する場合があります。また先天的な血管奇形(中腸軸捻転に伴う異常や門脈圧亢進症など)でも、食事に関連して腹痛が誘発されることがあります。こうした血流異常による腹痛は診断が難しいため、他の原因で説明できない激しい腹痛や身体所見に比して痛みが強い場合には留意すべき鑑別診断です。
その他の原因
膵・胆道系の疾患も食後腹痛の重要な鑑別です。胆石症は思春期以降の肥満傾向のある小児や溶血性貧血を持つ小児で起こり得て、脂肪食後の右上腹部痛・肩甲骨部への放散痛(胆石疝痛)を呈します。慢性膵炎は小児ではまれですが、特発性や遺伝性膵炎では小児期から再発性の激しい腹痛発作が起こり、食事(特に脂肪食)が誘因であることがあります。膵炎は背部痛を伴い、血清アミラーゼ・リパーゼ上昇で診断できます。
また腹痛を訴える子どもの中には、原因が消化器以外の場合もあります。尿路結石や尿路感染症、婦人科疾患(思春期の月経困難症や卵巣嚢腫の捻転など)、腹壁筋損傷なども、食後に症状悪化する場合は腹痛と錯覚され得ます。さらに心理的要因も痛みに大きく影響します。不安障害や学業・家庭ストレスによる心因性の腹痛では、食後に限らず状況に応じて痛みが変動しますが、時に「学校に行く前の朝に痛み、休日はけろりとしている」といったパターンが見られます。純粋な心因性腹痛の場合、食事との関連性は必ずしも高くありませんが、過度のストレスで自律神経が乱れると食後の消化管運動も影響を受けるため、ストレスと食事の双方が絡んで痛みが誘発されるケースもあります。
診断アプローチ
症状の評価と診察
食後腹痛の診断では、まず詳細な問診と診察によって機能性か器質性かのあたりを付けます。問診では痛みの具体的な様子(部位、性状、強さ、持続時間)、食事との時間的関連、伴う症状(吐き気・嘔吐、下痢・便秘、発熱、発疹など)、生活への支障の程度、ストレス要因の有無、家族歴(IBSやIBD、セリアック病など)を確認します。身体所見では成長曲線(体重増加不良がないか)、腹部診察(圧痛部位や腫瘤の有無、腸雑音の亢進や減弱)、肛門周囲の視診(痔瘻や裂肛があればCrohn病疑い)、皮疹(IgA血管炎による紫斑など)に注意します。また思春期の女児では月経や妊娠の可能性も評価します。
警戒すべき症候と追加検査
小児の慢性腹痛の大部分は機能性ですが、次のような警告徴候(赤旗所見)があれば器質的疾患の可能性が高まります:
-
局所的な持続痛(特に右上腹部痛や右下腹部痛が慢性的に続く場合) – 胆道系疾患や虫垂炎など局所疾患を示唆
-
夜間(睡眠中)に目が覚めるほどの腹痛 – 潰瘍や重度の炎症性疾患の可能性
-
不明熱・原因不明の発熱の反復 – 慢性感染症や炎症性疾患を示唆
-
関節痛の合併 – 炎症性腸疾患(関節炎を伴うことがある)や結合組織疾患を示唆
-
嚥下困難や持続的な嘔吐 – 重篤な上部消化管病変(狭窄や高度の食道炎)の可能性
-
肛門周囲の病変(痔瘻や膿瘍) – Crohn病に特徴的
-
消化管出血(吐血・下血・黒色便) – 潰瘍、IBD、ポリープなど
-
夜間の下痢 – IBDに多い症状
-
体重減少・発育障害、思春期遅発 – 慢性的な消化不良(吸収不良)や慢性疾患の示唆
こうした所見があれば積極的な検査が必要です。一方で警戒所見が全くなく、日中に限定された腹痛で成長が順調な場合は機能性痛の可能性が高くなります(絶対ではありませんが)。ただし心因反応による痛みでも学校欠席や活動制限が生じることがあるため、日常生活への支障=器質疾患とは限らない点に留意します。
基本的検査としては以下を考慮します:
-
血液検査: 全血球計算(貧血、白血球増多)、炎症反応(赤沈やCRP)、肝胆膵酵素、アミラーゼ・リパーゼ(膵炎疑い時)、血中電解質や尿素窒素(嘔吐・下痢による脱水評価)など。必要に応じて甲状腺機能(甲状腺機能亢進症でも腹痛ありうる)やカテコールアミン(褐色細胞腫は極めて稀だが)も検討。
-
尿検査: 尿白血球・亜硝酸塩(尿路感染)、尿中血(結石やIgA血管炎で腎障害の可能性)。
-
便検査: 便潜血反応(陽性なら消化管出血評価へ)、寄生虫卵検査(ランブリア症などは慢性下痢・腹痛の原因)、便中カルプロテクチン(消化管の炎症マーカーで、IBDスクリーニングに有用。陰性なら重症IBDの可能性が極めて低いとされます)。
-
腹部超音波: 小児の腹痛では放射線被曝のないエコー検査が有用です。腸重積や胆嚢結石、腎結石、水腎症、膵腫大(膵炎)などがないか評価します。超音波所見は明らかな警戒所見のある場合に有用性が高く、そうでない慢性腹痛児では異常検出率は低いですが(<1%)、腹痛部位が偏っている場合や発熱・体重減少などを伴う場合には施行を検討します。
-
呼気試験: 乳糖不耐症や果糖不耐症を疑う場合、水素呼気試験で糖負荷後の呼気中水素上昇を見ることができます。ただし小児では症状との関連がはっきりしない偽陽性例も多く、陽性でも直ちに診断とはせず除去食による検証が望ましいです。
-
食物アレルギー検査: 即時型アレルギーを示唆する所見(じんま疹や喘鳴を伴う腹痛など)があるなら特異的IgE抗体検査を行います。ただし非IgE型(FPIESやEGID)は検査では検出できないため、症状日誌や除去試験が重要です。疑わしい食品は2~4週間除去し、その後負荷して症状が再現されるか確認することがあります(医療機関管理下で実施)。
セリアック病のスクリーニングは、腹痛に加えて下痢・体重減少・貧血などがある場合に抗tTG-IgAおよび総IgA検査を行います。抗体価が高値なら消化管内視鏡と十二指腸生検で確定診断します。IgA欠損症例ではIgGベースの抗体検査を用います。日本人小児では可能性は低いものの、「成長曲線が下降してきた」「原因不明の貧血や肝機能障害がある」などの所見があれば念のためチェックします。
内視鏡検査(上部内視鏡・大腸内視鏡)は、小児では侵襲が大きいため慎重に適応判断します。明らかな警戒徴候がある場合や、半年~1年以上にわたり腹痛が持続・増悪し、他検査でも原因不明の場合に考慮されます。ある研究では、1年以上腹痛が続く子どもに上部消化管内視鏡検査を行ったところ37%に何らかの診断がついたと報告されています。見つかった疾患は逆流性食道炎(21%)、好酸球性食道炎(4.5%)、好酸球性胃腸炎(4.1%)、Helicobacter pylori感染(2.8%)、セリアック病(0.6%)、消化性潰瘍(0.6%)などでした。大腸内視鏡では潰瘍性大腸炎やCrohn病の診断が期待できます。内視鏡で疾患が見つかっても、その治療で腹痛が必ずしも消失しないケースもあり(機能性痛を合併するため)、検査適応は専門医と相談の上で決定します。
MALSやSMA症候群の評価には、造影CTやMRアンギオでの血管像評価、エコーによる腹腔動脈の血流速度測定(呼気時ピーク速度>350cm/sかつ角度変異>50°で高い疑い)が行われます。確定的には動脈造影や腹腔神経叢ブロック試験で診断します。こうした特殊検査は専門施設で行われます。
心理社会的評価も見逃せません。腹痛が学校や家庭環境と密接に関連する場合、児や家族への丁寧な問診でストレス因子や二次的利得の有無を探ります。必要に応じて心理士や精神科医と連携し、心理検査や面接を行います。小児では親の心配度が症状に反映されることも多いため、親への対応も含め包括的に診断を進めます。
最後に、小児慢性腹痛は診断そのものに時間がかかることが少なくありません。期間中は子どもと家族の不安を和らげ、生活の質を維持する支援が必要です。原因不明の段階でも「重い病気の可能性は低い」ことを伝え学校生活への復帰を促すなど、診断アプローチと並行して対応していきます。
治療法・対応策
機能性腹痛・IBSに対する一般的対応
機能性腹痛と診断された場合、治療の目標は症状の完全消失ではなく生活の質(QOL)の改善に置かれます。まずは子どもの痛みを否定せず「本当に痛いこと」を認めた上で、「命に関わる病気ではない」ことを安心させます。その上で、痛みで学校を休む・注意を引くといった二次的利得が続かないよう、可能な範囲で通常生活に戻すことが重要です。親にも過度に心配しすぎず見守る姿勢を持ってもらうよう指導します。
生活習慣の改善も基本です。十分な睡眠と規則正しい食事、適度な運動は消化管機能を安定させます。便秘があれば排便習慣の指導や食物繊維・水分摂取の工夫を行います。食事内容では、子ども本人や親が「これを食べると痛い」と感じるものは一旦避けます。ただし必要以上に食事制限すると栄養不足になるため、除外は最小限にし、除外した分の代替食品で栄養を補うよう指導します。一般的に脂肪分の多い食事や炭酸飲料・ガムなど空気嚥下を増やすものは腹部膨満感を悪化させるため控えめにします。逆に水溶性食物繊維(果物・オーツ麦・大麦など)や発酵食品は腸内環境を整え症状改善に有用なことがあります。IBSでは食事誘発の症状悪化を感じる患児も多いため、思春期以降であれば専門医の管理下で低FODMAP食を試してみることもあります(効果には個人差が大きいですが、一部のIBS患児で痛みの軽減が報告されています)。
食事療法・栄養管理
原因に応じた食事療法は有効です。乳糖不耐症であれば乳糖制限(低乳糖ミルクの利用や、ヨーグルト・チーズなど比較的乳糖の少ない乳製品を選ぶ)、または食前に乳糖分解酵素製剤を内服する方法があります。セリアック病であれば厳格なグルテン除去食が必須で、生涯にわたり継続します。FPIESなど食物過敏症の場合、原因食品の除去が基本で、代替ミルク(アレルギー用ミルク)やアミノ酸フォーミュラで栄養を補います。多くは数年で耐性を獲得するため、適切な時期に医療機関で負荷試験を行い解除できるか評価します。
好酸球性消化管疾患では、6大アレルゲン(乳・卵・小麦・大豆・魚介・ナッツ等)除去食がしばしば行われ、症状改善すれば一品ずつ戻して原因を特定します。原因が特定できない場合はアミノ酸製剤による栄養療法に移行することもあります。
便秘がある場合、食物繊維と水分の増量が第一です。難治の便秘には乳糖・マルツエキスや酸化マグネシウム、ポリエチレングリコール(PEG)製剤などの緩下剤を用いて排便回数を確保します。便秘が改善すると腹痛発作が劇的に減る例も多く経験されます。
薬物療法
機能性腹痛・IBSに対する薬物治療はあくまで対症療法で、エビデンスは限定的です。近年のガイドラインでは、小児IBS/機能性腹痛に最も強く推奨されるのは心理療法であり、薬物は補助的位置づけとされています。それでも症状が強い場合、以下のような薬物を症状に応じて検討します:
-
鎮痙薬(腸管のけいれんを抑える薬): 日本では臭化ブチルスコポラミン(ブスコパン®)やメペンゾラート(トランコロン®)などが使われます。腹痛発作時に頓用し、特にIBS-下痢型で有効との報告があります。ただ、プラセボ対照試験で明確な効果が示されていない薬もあり、2025年の国際ガイドラインではメベベリン(チアトン®)など一部の鎮痙薬は効果不十分とされています。しかし個々の患児で効果を示すこともあるため、慎重に試みることがあります。
-
消化管運動調整薬・酸分泌抑制薬: 食後の上腹部症状が強い機能性ディスペプシアには、消化管運動促進薬(ドンペリドン[ナウゼリン®]や、成人ではアコチアミドなど)やH<sub>2</sub>ブロッカー/PPI(胃酸過多が疑われる場合)を試すことがあります。小児のFDに対する明確な治療薬は確立していませんが、2025年ガイドラインではドンペリドンやシプロヘプタジン(抗ヒスタミン薬で食欲増進・胃腸運動促進作用がある)の使用が提案されています。
-
整腸剤・プロバイオティクス: 乳酸菌やビフィズス菌製剤は小児機能性腹痛に広く用いられてきました。エビデンスも徐々に蓄積しており、例えばL.ラクティス(ラクトミン)などのプロバイオティクスは痛みの頻度・強度を軽減し安全であると報告されています。シンバイオティクス(プロバイオティクス+プレバイオティクスの併用)も試みられており、あるランダム化試験ではBacillus coagulans+フラクトオリゴ糖のシンバイオティクスで一時的な痛み改善効果が見られました(12週後には差が消失)。2025年ガイドラインでもプロバイオティクス(特にLactobacillus rhamnosus GG**)や食物繊維補充**はIBSの補助療法として推奨されています。
-
ハーブ製剤(ペパーミントオイル): 腸管の平滑筋を弛緩させる作用があり、IBSの痛みに有効との報告があります。小児では小児用カプセル製剤(日本未承認)を用いた試験で有効性が示され、pH依存型のコーティングペパーミントオイル製剤が腹痛改善に有用だったとの研究があります。ガイドラインでもペパーミントオイル内服はエビデンス弱ながら使用が支持されています。
-
低用量抗うつ薬: 難治性の強い腹痛には、三環系抗うつ薬(アミトリプチリンなど)の低用量が有効なことがあります。抗うつ薬は鎮痛補助的な中枢作用や抗コリン作用で腸管の痛み伝達を抑制すると考えられます。小児IBSにおいてアミトリプチリン低用量で症状改善を示した試験もありますが、エビデンスは中程度です。選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)の有効性は明確でなく、シタロプラム(SSRI)は推奨されないとされています。
-
その他薬剤: IBS-下痢型では頓用のロペラミドや、胆汁酸吸着剤(コレスチラミンなど)が下痢による腹痛に有用です。慢性の下痢では整形外科的な生活への影響を減らす目的で処方することがあります。逆にIBS-便秘型では、小児ではまず食物繊維や浣腸で対応し、場合によりPEG製剤や酸化Mgを用います。新規の腸管モチベーター薬(ルビプロストンやリナクロチド)は日本の小児では未承認です。なおCBDオイル(カンナビジオール)は近年疼痛緩和で注目されますが、小児機能性痛に対しては推奨しないとの勧告があります(有効性不明な上、安全性も十分でないため)。また原因不明の腹痛に安易な外科手術を行うことも厳に慎むべきであり、ガイドラインでは診断目的や治療目的の不必要な手術は強く反対されています。
心理的アプローチ・疼痛緩和
心理社会的アプローチは小児腹痛治療の中核です。とりわけ認知行動療法(CBT)と催眠療法は、複数の臨床試験で有効性が示されており、ガイドラインでも強く推奨されています。CBTでは痛みに対する認知の歪みを修正し、ストレス対処法やリラクゼーション法を習得させます。これにより痛みの頻度・強度の減少やQOLの向上が報告されています。特に小児では親子双方への認知行動的支援(痛みに過剰に注目しすぎない等の指導)が有効です。
**腹部への暗示療法(腸管に働きかける催眠療法)**も注目されています。これは子どもにリラックスした状態で腹痛が和らぐイメージを持たせる手法で、自宅で聞ける音声ガイドを用いた自己催眠も効果が示されています。催眠療法を受けた児童では、プラセボ群より有意に腹痛が改善し、その効果が半年以上持続したとの報告があります。熟練の小児催眠療法士は限られますが、可能であれば導入を検討します。
家族療法やバイオフィードバックも補助的に用いられます。バイオフィードバックでは腹式呼吸や筋弛緩法を学習させ、自律神経バランスを整えることで痛みを軽減します。学校生活上のストレス(いじめや不登校など)への介入も不可欠で、スクールカウンセラーや教員とも連携して環境調整をします。
痛みが強い発作時には、生活上の工夫も大切です。安静にして腹部を温める、背中をさする、お腹を軽くマッサージするなどで子どもが安心できれば痛みは幾分和らぎます。小児では痛み止め(鎮痛剤)の使用は慎重にすべきですが、急性虫垂炎などの鑑別が除外された後であれば、アセトアミノフェンの頓用は比較的安全です。NSAIDsはかえって消化管障害を起こす可能性があるため避けます。漢方薬では、腹部の冷えや緊張があるタイプに小建中湯、ストレスの強いタイプに柴胡加竜骨牡蛎湯などが経験的に用いられることがありますが、科学的根拠は十分ではありません。
器質的疾患への対応
腹痛の器質的原因が特定された場合は、その治療を行います。例えば**炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・Crohn病)**であれば5-ASA製剤やステロイド、免疫調節薬、生物学的製剤などによる寛解導入と維持療法を行います。寛解すれば腹痛も軽快しますが、狭窄が残存する場合は食事を少量頻回にするなどの工夫も必要です。
胆石症で痛み発作を繰り返す場合は胆嚢摘出術が考慮されます。慢性膵炎では低脂肪食と酵素補充、鎮痛薬で対応し、膵石や狭窄があれば内視鏡的除去を検討します。SMA症候群は先に述べた通りまず高カロリー食で体重増加を図り、難しければ外科的手術となります。MALSは根本治療は手術ですが、心疾患合併など手術ハイリスクなら腹腔神経節ブロックで保存的に対処する選択もあります。
腸重積など急性疾患の場合は緊急整復術で対処し、原因となるポリープや腫瘍があれば切除します。寄生虫感染(ランブル鞭毛虫症など)が確認されたら駆虫薬で治療します。
以上のように、子どもの食後腹痛の治療は原因により多岐にわたります。重要なのは、子どもの発するサインを包括的に捉え、必要な治療と不要な治療を適切に見極めることです。とくに機能性腹痛では過剰な検査や投薬を避けつつ、子どもと家族の不安を取り除き自力で痛みを乗り越える力を育むことが長期的な改善につながります。
予後・再発傾向
機能性腹痛の予後は概して良好で、時間とともに症状は改善する傾向があります。ある前向き研究では、一次医療機関を受診した小児腹痛患者の多くが2年以内に腹痛頻度の減少を認めました。しかし一部では腹痛が慢性的に持続し、成人期まで症状が残存するケースがあります。古典的にはApleyの報告(1958年)で「小児反復性腹痛の約1/3は成人後も何らかの症状を抱える」とされ、その後の追跡調査でも3割前後の症例で慢性疼痛や頭痛などが成人期にみられるとの結果があります。2010年のある研究では、小児期に機能性腹痛を経験した人は、経験しなかった人に比べ成人期に慢性疼痛(例えば過敏性腸症候群、線維筋痛症など)を発症するリスクが高いことが示されました。また不安障害との関連も指摘されており、児童期の腹痛持ちの子は成人早期に不安傾向が強い傾向があったとの報告もあります。
もっとも、小児期の機能性腹痛が必ずしも将来の病的状態を意味するわけではありません。多くの子どもは思春期に症状が消失し、問題なく成長します。一方で、思春期・成人期に再燃する場合、しばしばIBSや機能性ディスペプシアとして再診断されることがあります。すなわち小児機能性腹痛は同じ素因を持った症候群がライフステージで形を変えて現れたものとも考えられます。これは脳腸相関やストレス対処能力、痛覚過敏性といった個体の特性が年齢によって症状表現を変えるためと推測されます。
IBSの予後について言えば、小児IBSは慢性の経過をたどることが多いですが、適切な生活指導とストレスマネジメントで症状をコントロール可能な場合がほとんどです。IBS自体は生命予後に影響を与える疾患ではなく、成長や発育も正常に遂げられます。ただし症状が長引くことで学校欠席やQOL低下が問題となり、将来的な医療費負担も増える可能性があります。したがって小児期からのきめ細かな対応が望まれます。
器質的疾患の予後は原因により様々です。セリアック病は食事管理さえ守れば正常な生活を送れますが、生涯の自己管理が必要です。炎症性腸疾患は再発寛解を繰り返す慢性疾患ですが、生物学的製剤の登場で予後は改善しつつあります。SMA症候群は体重が戻れば再発しませんが、極端な食事制限などで再度体重減少するとぶり返す可能性があります。MALSは手術成功例では著名な症状改善が得られますが、完全には痛みが取れない患者も一定数います。FPIESは前述の通りほとんどが学童期までに耐性を獲得し卒業できます。好酸球性胃腸炎は慢性の経過をとりがちで、ステロイドの反復や栄養療法が必要になることもあります。
再発傾向について言えば、機能性腹痛の場合ストレスイベント(受験や環境変化)の際に一過性に再燃することがあります。これはかつて腹痛を経験した子はストレス時に腹痛として症状が出やすい「疼痛記憶」のようなものが形成される可能性があります。一方で、親や本人が痛みへの対処法を身につけていれば、再発時も過度に医療に依存せず乗り越えることができます。したがって治療過程でコーピングスキル(対処技能)を養うことが大切です。
疫学データ(年齢別・性別傾向)
小児の慢性・反復性腹痛は古くから10~15%程度の子どもにみられると報告されています。特に**学童期から思春期前半(おおよそ6~14歳)**に好発し、幼児期(5歳以下)では比較的まれです。5~16歳の小児の約8~12%が慢性的な腹痛を経験するとする疫学データもあります。男女差は小児期にはさほど大きくありませんが、やや女児に多いとの報告が多いです。思春期以降になるとIBSなどは女性に多くなっていくため、その前段階として小児でも高学年~中学生くらいから女児優位が目立ってきます。
腹痛の原因の内訳に関しては、大多数が機能性であり、器質的原因が見つかるのは10%以下というのが従来からの定説です。実際、ある報告では3か月以上腹痛が続いて受診した小児のうち、詳しい検査をしても明確な器質疾患が見つからないケースが90%以上を占めたといいます。したがって**中枢介在性腹痛症候群(旧称: 機能性腹痛)**が診断される割合が非常に高いのが小児慢性腹痛の特徴です。
一方、各年代で注意すべき器質的疾患もあります。乳幼児期では腸重積、食物アレルギー(牛乳・大豆アレルギーなど)、腸回転異常症、先天代謝異常(ガラクトース血症による乳糖不耐など)といった疾患が腹痛の原因となり得ます。学童期では虫垂炎やH. pylori感染症も鑑別に入ります。思春期になると機能性ディスペプシアやIBSが台頭し、加えて潰瘍性大腸炎・Crohn病などIBDの発症もみられるようになります。また女子では月経関連の疼痛が加わります。こうした年齢ごとの頻度の差はありますが、総じて機能性腹痛がどの年齢層でも最多であることに変わりありません。
興味深いデータとして、小児の反復性腹痛には親も腹痛経験者であることが多いという報告があります。親が過去にIBSなど機能性胃腸症状を持っていると、その認知や対処の仕方が子にも影響し、腹痛訴えが持続しやすいとの指摘があります。また親の不安傾向が強いと子の症状強度が増すともいわれます。このように家庭環境や遺伝的背景も小児腹痛の疫学に関与するため、診療では家族全体を見る姿勢が重要です。
最後に、慢性腹痛を持つ小児は医療機関受診も増えがちで、医療費や学校欠席日数の面で負担が大きいことが示されています。しかし適切な診断と包括的ケアにより、これらは軽減できる可能性があります。実際、家庭医の報告では小児機能性腹痛患者の多くは一般診療で管理でき、長期予後も良好だったとされています。したがって現場の医療者は最新のエビデンスを踏まえて適切に介入し、子どもたちが健やかに日常生活を送れるよう支援することが求められます。
参考文献・出典: 子どもの食後腹痛に関する国内外の論文・ガイドラインより (※本文中に示した【†】内の番号は該当情報源を示しています)