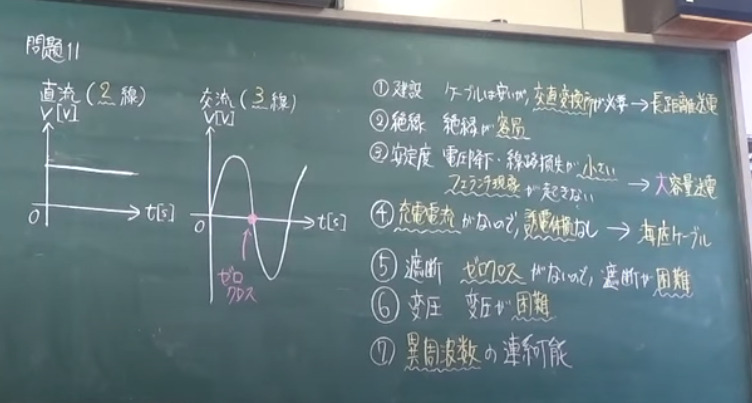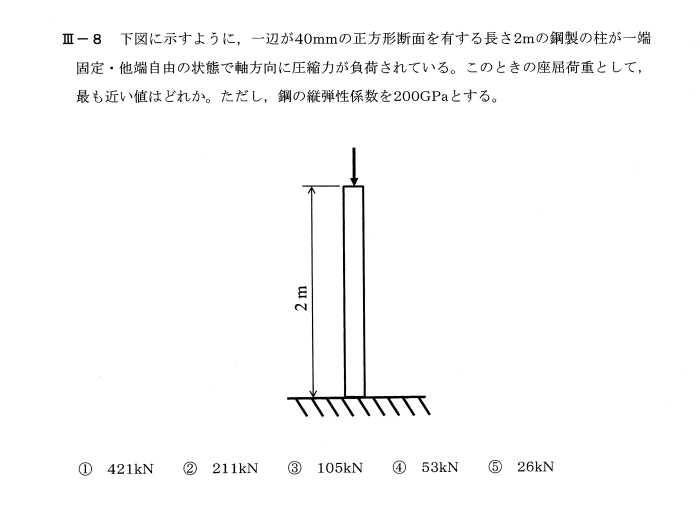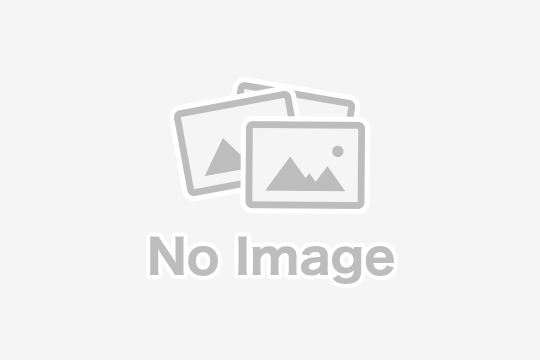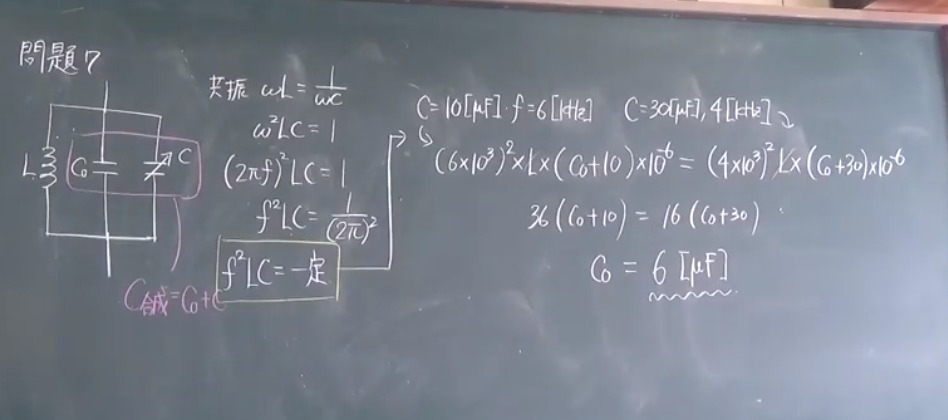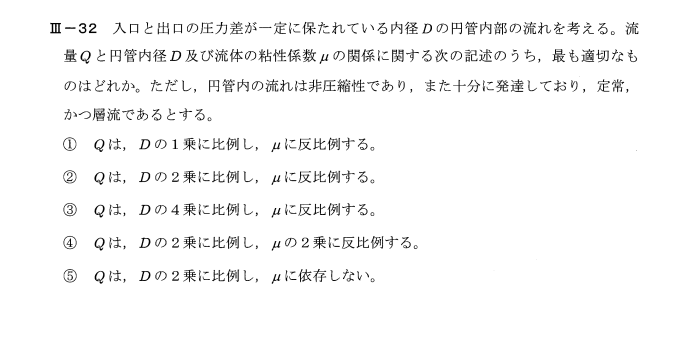3D光弾性トモグラフィーの研究動向
はじめに
3D光弾性トモグラフィー(Three-Dimensional Photoelastic Tomography)は、透明材料内部の3次元応力分布を非破壊で可視化・定量化する手法ですepj-conferences.org。材料に荷重が加わると生じる複屈折現象(光弾性効果)を利用し、偏光光学的に内部応力を捉えます。従来、3次元内部応力を測定するには、模型を負荷下で硬化させスライスして観察する応力凍結法が用いられてきましたbssm.org。しかし応力凍結法は試料の破壊や手間を伴うため、これを克服する**統合光弾性法(光弾性CT法)**として3D光弾性トモグラフィーが提案されましたbssm.org。本レポートでは、本手法の代表的研究と研究者、技術的進展、主な応用分野、発展の歴史と近年のトレンド、および使用される装置構成について、論文の発表年や引用関係にも留意しつつ概観します。
3D光弾性トモグラフィーの概要と原理
光弾性トモグラフィーでは、試料を偏光光源で様々な方向から透過照明し、透過光の偏光状態(位相差や偏光面の方向)を計測しますbssm.org。内部を通過した偏光光は、その光路上の応力状態に応じて位相が遅れ、偏光面が回転します。この光学的積分効果による観測量から、逆問題を解いて各点の応力テンソルを再構成するのが目標ですbssm.org。しかし応力は2階のテンソル場であり、光路ごとの測定値との関係が非線形で複雑なため、従来のX線CTのような直線積分(ラドン変換)手法を直接適用できませんbssm.org。特に主応力の大きさと方向が厚み方向に沿って変化する場合、測定データとの対応付けが難しく、トモグラフィー再構成は非線形逆問題となりますbssm.org。この問題に対し、光学モデル上で試料内部を等価的に「遅延板+回転子」の連なりとして表現し、位相差2Δ(主応力差に比例)、遅延板軸方位θ(主応力軸方向)、回転光学効果γなどの特性パラメータに分離して測定・解析する手法が開発されていますbssm.org。これにデジタル写真弾性(位相ステッピング法やフーリエ解析)を組み合わせることで、非線形性の克服に道が拓かれました。
代表的な研究論文と研究者
3D光弾性トモグラフィーの黎明期には、1940年代のFrochtによる基礎研究pmc.ncbi.nlm.nih.govや、1952年のFrocht & Guernseyによる3次元光弾性法の一般手法検討が見られます。また1970年代に入り、インドのSrinathとBhave (1974年) は3次元応力場の断層測定の可能性を指摘しresearchgate.net、米国のDoyleとDanylukは実験力学分野で統合光弾性による応力トモグラフィー実験を報告しました(1978年)researchgate.net。1980年代後半にはエストニアのHillar Abenらが弱い二重屈折の場合の統合光弾性理論を確立しpmc.ncbi.nlm.nih.gov、Optics and Lasers in Engineering誌に発表しています(1989年)pmc.ncbi.nlm.nih.gov。さらに1990年代には、ロシアのAndrienkoらがカー効果を利用した軸対称応力場の光テンソル場トモグラフィーを提案しました(1992年)pmc.ncbi.nlm.nih.gov。ドイツのDietrich SchuppはSPIE会議(1999年)で光学テンソル場トモグラフィーによる3D応力テンソル同定法を発表しpmc.ncbi.nlm.nih.gov、欧州を中心に注目を集めました。2004年にはAinolaとAbenがJOSA A誌で光弾性トモグラフィーの光学理論を体系化しpmc.ncbi.nlm.nih.gov、2005年にはAbenらがOptical Engineering誌にてガラス製品内部の残留応力を測定するトモグラフィー技術を報告していますspie.org(同内容はSPIE Proc. Vol.5457にも招待論文掲載)。日本では小國健二・堀宗朗ら(JAMSTEC/東大)がテンソル場トモグラフィーの手法を開発し、Journal of Mechanics and Physics of Solids誌に論文を発表しました(2008年)pmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov。この研究pmc.ncbi.nlm.nih.govでは非破壊・無接触で3次元応力を同定するトモグラフィー法を提案し、先行研究(Srinathら1974、Doyleら1978、Abenら1989、Schupp 1999など)の流れを踏まえた画期的成果として引用されていますresearchgate.net。また2008年にはイタリアのPietralungaらがJOSA A誌で反射型光弾性トモグラフィーにより光導波路中の応力分布計測を報告しましたopg.optica.org。近年では、デジタル写真弾性の第一人者であるインドのK. Rameshが2021年に総説「Photoelasticity: A Renaissance」を著し、デジタル技術により光弾性解析が再興していると述べていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。さらにMITやRice大学のグループ(R. Raskarら)は**Neural Stress Tensor Tomography (NeST)**と称する手法を開発し、ニューラルネットワークによる応力場の連続体表現を用いて偏光画像から内部応力を再構成する研究を発表しました(2024年)openreview.net。以上のように、エストニア・ロシア・日米など各国の研究者が本手法の発展に寄与しており、その引用関係からも各時代の主要な論文が互いに位置づけられていることがわかりますresearchgate.net。
技術的進展と解析手法
光学的アプローチの進展
光弾性トモグラフィーの実現には、高度な光学計測手法の発展が不可欠でした。基本的なアプローチは、試料を等方液体中に浸漬(屈折率マッチング)し、直進する偏光光が試料内部で屈折せず進むようにすることですpmc.ncbi.nlm.nih.gov。これにより測定される干渉縞(積分インターフェログラム)は、応力場に沿った積分情報となりますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。標本を回転ステージに載せ、多軸からの透過像を取得することで、応力場の投影データ(プロジェクション)を集めますopenreview.net。光源には単色レーザー光が用いられることも多く、偏光子・検光子(偏光解析器)や1/4波長板を組み合わせた偏光計(ポラリスコープ)によって、各方向の位相差と偏光面角度を計測しますbssm.org。例えば典型的な装置構成は、レーザー+スペーシャルフィルタ+レンズで平行光を生成し、偏光子を通して試料を照射、試料は液槽内でモーター駆動により所定角度だけ回転されます。透過光は検光子を経てカメラに結像され、必要に応じて光学フィルタや絞りで調整しますbssm.org。最近では、偏光情報を一度に取得できる偏光カメラも活用されており、これにより高速現象の連続撮影が可能となっていますarxiv.org。特殊なアプローチとしては、ホログラフィック・トモグラフィーも提案されています。Zhu (1992年) は光散乱のボルン近似に基づき、様々な角度から平面波で照明し干渉縞を記録することで3D応力分布を再構成する手法を示しましたopg.optica.org。この方法では偏光状態の変化を考慮しつつ応力場による散乱を解析し、低周波成分ではあるものの応力テンソル場を非破壊で再構成できることが示されていますopg.optica.org。他にも、試料片面からの反射偏光を利用して内部応力を断層再構成する反射光弾性トモグラフィーが開発されており、光導波路基板中の応力測定など特定用途で有効性が報告されていますopg.optica.org。近年のLiらの研究 (2024年) では、干渉光投影トモグラフィー(IOPT)と称して干渉計による高感度検出と3D光弾性効果を組み合わせ、粒状体内の力学的つりあい鎖(フォースチェーン)の可視化に成功していますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
逆解析と再構成アルゴリズムの進歩
計測した偏光データから応力場を計算する逆解析アルゴリズムも、この分野の重要な技術課題です。初期の研究では、複屈折が弱い場合に応力差による光学厚さの線形化が可能となり、比較的単純な再構成が試みられましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。しかし一般には非線形性が避けられないため、さまざまなアプローチが検討されています。一つの流れはハイブリッド法とも呼ばれ、光学計測と弾性力学の方程式を組み合わせて不足する情報を補う手法ですepj-conferences.org。Abenらは、取得した断層プロジェクションからまず断面内の法線応力差分布を直接復元し、そこに力のつり合いや連続条件(応力の整合条件)を適用することで全応力テンソルを求めるアルゴリズムを提案しましたepj-conferences.org。外力による応力場であれば平衡方程式と相容条件を使い、残留応力の場合は物体に固有の総和則(たとえば軸対称熱応力状態に対する特別な関係式)を導入することで、不足方程式を補完していますepj-conferences.org。別の流れとして、Oguniら(2008年)は増分型の支配方程式を導入することで非線形性を抑制し、観測値の変化に応じて応力場を反復的に更新するテンソル場トモグラフィー手法を開発しましたresearchgate.net。数学分野からも貢献があり、Sharafutdinov (1994年)やHammer & Lionheart (2005年)らはテンソル場の断層復元理論を深化させ、偏光トモグラフィー問題を解くための数理的枠組みを提供していますresearchgate.net。計算アルゴリズム面では、特性値問題として主応力方向を決定するステップや、位相が2πを超えるフリンジの巻き戻し(位相アンラッピング)処理などが課題となります。これに対し、デジタル画像処理による位相ステッピング干渉法bssm.orgやFFT解析で高次の縞位相を抽出する技術が取り入れられました。さらに近年では、分析-by-シンセシスの思想で自動微分可能な光伝搬モデルを組み込み、観測データとの差異が最小となる応力分布を逐次最適化する計算手法が登場していますopenreview.net。Daveら(2024年)のNeSTがその代表例で、Jones行列による複屈折の厳密な前進モデルをニューラルネットワーク内に実装し、位相のアンラッピングとトモグラフィー再構成を同時に解決していますopenreview.net。この非線形最適化手法により、従来の線形近似では困難であった複雑な形状や荷重条件の試料に対しても、整合性の高い内部応力分布の再構成が可能であることが示されていますopenreview.net。
主な応用分野
3D光弾性トモグラフィーは、多様な分野で応力解析に応用されています。古くから盛んなのは材料加工品の残留応力評価で、特にガラス工業においては瓶やレンズなど複雑形状ガラス内部の残留応力を非破壊で測定する手段として注目されてきましたspie.orgcs.ioc.ee。Abenらによるガラス製品への適用研究(2005年)では、トモグラフィー再構成アルゴリズムを実装しガラス容器内の応力分布計測に成功していますws.lib.ttu.ee。機械工学・土木分野でも、試験片内部の応力を可視化することで設計や解析を支援する応用があります。例えばギアモデルの応力解析に3D写真弾性を利用した研究bssm.orgや、コンクリート構造物模型の内部応力評価などが報告されています。また粒状体力学では、従来2次元平面内でしか直接観察できなかったフォースチェーン(粒子間力の連鎖構造)を3次元で可視化するため、光弾性トモグラフィーが用いられ始めましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。Liらの最新の研究 (PNAS, 2024年) は、砂粒や多面体粒子集合体に三軸荷重を加えた際の力学的な力鎖ネットワークを、干渉光投影トモグラフィーによって直接観察していますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。この成果は、従来2D実験から推測するしかなかった粒状体のせん断帯形成や崩壊機構を粒子レベルで検証するもので、地滑りや地震時の破壊現象の解明に繋がる知見を提供しましたpmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov。さらにバイオメカニクスや軟質材料分野への応用も期待されています。Tagawaら(2022年)は、軟質ゲル中に球を圧入する3Dヘルツ接触問題をモデルに、光弾性パラメータ(位相差・方位角)を偏光カメラで計測し理論解と比較することで、生体軟組織等の応力解析への有用性を示しましたresearchgate.netresearchgate.net。この研究ではゲル材料の光弾性係数も実測し、組織工学や細胞プリンティング領域での内部応力計測手法として3D光弾性が役立つ可能性を報告していますresearchgate.net。他にも光通信分野での光導波路内部の応力分布測定opg.optica.orgや、複合材料の残留応力評価、加えて加熱・冷却に伴う内部応力のリアルタイム観察など、光弾性トモグラフィーの応用範囲は広がりつつあります。researchgate.net
発展の歴史と近年のトレンド
3D光弾性トモグラフィーの発展は、おおまかに次のような流れで推移しています。1950年代までに基本的な写真弾性法の枠組みが整えられ、3次元化への萌芽が見られました。1970年代に統合光弾性によるトモグラフィーの概念実証が提唱されresearchgate.net、1980年代には理論面でテンソル場の積分幾何学や弱複屈折理論が進展しましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。1990年代前半には実験装置・手法の高度化が進み、ホログラフィーやレーザー干渉計の導入、軸対称モデルでのデータ取得法の工夫などが相次ぎました。例えばAmarnath & Simha (1998年)は軸対称試料のための投影データ取得法を提案し、限られた視角からでも安定した再構成ができる可能性を示していますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。1990年代後半~2000年代初頭にかけて、エストニアのAbenらによる研究がピークを迎え、非破壊3D応力計測システムの実証やガラス材料への実用展開が行われましたws.lib.ttu.ee。また2004年のAinola&Abenによる光学理論論文opg.optica.orgや、2005年のHammer&Lionheartによるテンソルトモグラフィー数理論文は、以後の研究の基盤となりましたresearchgate.net。2000年代後半には、日本からOguni・堀らのJMPSolids論文(2008年)pmc.ncbi.nlm.nih.govやイタリアからの反射法論文(2008年)opg.optica.orgなど、新規手法の提案が続きます。2010年代に入ると、デジタルカメラと計算機の性能向上により実験の高精度化・自動化が進展しました。例えばTomlinson&Patterson (2002年) は位相ステッピング技術で統合光弾性の特性パラメータを測定する手法を確立し、従来手動だった解析をデジタル化しましたbssm.org。2010年前後にはAbenらがInverse Problems in Science & Engineering誌(2010年)に一連の研究を展開し、大規模な逆解析に耐えるアルゴリズム改良を報告していますepj-conferences.org。近年(2015年~現在)のトレンドとして特筆すべきは、高速・動的な応力可視化と計算手法の高度化です。高速度カメラと偏光撮影技術の融合により、時間的に変化する3D応力場の逐次再構成が可能となりました。横山佑斗らはソフトマテリアル中のヘルツ接触衝撃における応力波の伝播を、高速偏光カメラとトモグラフィー技術で捉え、せん断波と軸方向応力波の同時観測に成功していますarxiv.orgarxiv.org。この研究では$10^{-1}$~$10^{1}$kPaという広範囲の応力を実時間で計測し、理論予測と良く一致することを示しましたarxiv.org。また計算分野では、前述のNeSTのように機械学習や最適化技術を取り入れた新しい再構成手法が登場し、複雑な試料形状や大きな位相ラップがある状況でも安定した結果が得られていますopenreview.net。総じて、この10年ほどで非破壊3D応力解析の実用性は飛躍的に向上しており、研究分野も材料・機械から地球科学、バイオまで広がっています。K. Rameshが指摘するように、デジタル技術との融合で写真弾性は再び盛り上がりを見せておりpmc.ncbi.nlm.nih.gov、3D光弾性トモグラフィーもその中核として発展を続けていると言えるでしょう。
装置構成と特徴
3D光弾性トモグラフィーに用いられる典型的な装置は、偏光計測システムと回転・位置決め機構から構成されますbssm.org。試料は透明な液槽(通常は試料と同じ屈折率の液体)内に固定され、モーター制御により所定の角度に回転・傾斜できますbssm.org。照明系はレーザーなどの光源から始まり、空間フィルタとレンズで平行で均一な照明光を生成しますbssm.org。この光は偏光フィルタ(偏光子)を通過して直線偏光となり試料に入射しますbssm.org。透過後の光は、検光子(分析器)や必要に応じて1/4波長板を通して偏光状態が強調されたのち、イメージングレンズ系を経て高速カメラやCCDカメラで記録されますbssm.org。近年はカメラ自体が偏光情報を同時取得できるタイプ(各画素に異なる偏光フィルタを配置)のものも利用され、1回の撮影で偏光の方向と位相差を計算できるようになっていますarxiv.org。データ取得は典型的には複数角度から行うため、ステージを等間隔で回転させて各角度の画像を取得します。場合によっては試料を上下反転させて3軸方向から測定することもありますbssm.org。取得画像はPCに送り、画像処理ソフトウェアで前処理(領域抽出やノイズ低減)された後、再構成アルゴリズムに入力されますbssm.orgbssm.org。装置全体としては光学部品の精密な配置と制御が要求されますが、近年は自動化も進んでおり、試料の角度変更を自動で行うシステムや、多自由度ロボットによる試料操作も検討されていますbssm.org。特殊な装置例として、反射法では試料表面に入射した偏光を再度反射偏光として捉えるため、偏光素子を工夫した偏光反射干渉計が用いられます。またホログラフィー法では、参照光との干渉縞を撮影するための光路・スクリーンが追加されるなど、計測原理に合わせた構成となりますopg.optica.org。いずれの場合も、正確なキャリブレーション(光学系の補正や試料材料の光弾性係数測定)が重要であり、専用の校正用試験片やソフトウェアが用意されることが多いです。
おわりに
3D光弾性トモグラフィーは、光学と力学を融合した学際的手法であり、ここ数十年で著しい発展を遂げてきました。代表的な研究者による論文を振り返ると、その進歩は逐次的かつ国際的に積み重ねられており、引用関係にもそれが表れていますresearchgate.net。技術面では、光源・検出器・計算機の進歩が本手法の精度と適用範囲を広げ、近年では動的現象や複雑な解析も可能となりましたarxiv.orgopenreview.net。応用面でも、工業材料から地盤工学、バイオマテリアルまで広がりつつあり、非破壊で内部応力を「見える化」できる利点を生かして様々な知見をもたらしていますpmc.ncbi.nlm.nih.govresearchgate.net。今後はさらなる高速化・高感度化や、大規模データに対するAI支援解析などが進むと予想され、構造物の健全性評価や新素材開発、生体力学の解明などに一層寄与することでしょう。
参考文献:
本稿で言及した論文には以下などが含まれます(発表年順):Frocht (1952)、Srinath & Bhave (1974)researchgate.net、Doyle & Danyluk (1978)researchgate.net、Aben et al. (1989)pmc.ncbi.nlm.nih.gov、Zhu (1992)opg.optica.org、Andrienko et al. (1992)pmc.ncbi.nlm.nih.gov、Schupp (1999)pmc.ncbi.nlm.nih.gov、Ainola & Aben (2004)opg.optica.org、Aben et al. (2005)spie.org、Oguni et al. (2008)pmc.ncbi.nlm.nih.gov、Pietralunga et al. (2008)opg.optica.org、Yokoyama et al. (2024)arxiv.org、Li & Juanes et al. (2024)pmc.ncbi.nlm.nih.gov、Dave et al. (2024)openreview.net等。この分野の最新の総説としてはRamesh (2021)pmc.ncbi.nlm.nih.govがデジタル光弾性の進展を包括的に論じています。各論文の詳細は本文中の引用箇所を参照してください。
一般的な手法になってきているのですか?
いいご質問です。結論から言うと、3D光弾性トモグラフィーはまだ「一般的な手法」とは言いにくい段階です。以下のような理由があります。1. 現状の位置づけ
- 古典的な2D光弾性法や応力凍結法は教育や研究用途で広く定着しています。
- これに対し、3D光弾性トモグラフィーはまだ主に研究室レベルでの開発・応用が中心です。論文の数も増えてきましたが、実験力学の「標準手法」と呼べるほどの普及には至っていません。
2. 制約となっている要因
- 装置が複雑・高価:回転ステージ、偏光光学系、液槽(屈折率マッチング)、高速カメラ、専用ソフトなどが必要。
- 解析が難しい:非線形逆問題であり、一般のCTのように直線的に再構成できない。高度な数理・最適化や最近ではニューラルネットワークが必要。
- 適用材料が限定:透明体(ガラス、ゲルなど)に限られるため、金属や不透明材料では直接使えない。
3. 普及に向けた動き
- 産業応用の芽:ガラス製品の残留応力評価、光導波路の応力評価、バイオ材料(ゲル・組織)などでは実用的に有効。
- 研究トレンド:
- デジタル写真弾性や高速偏光カメラの導入で測定が自動化・高速化
- 粒状体のフォースチェーン観察など、従来できなかった分野への応用
- ニューラルネットワークを用いた逆解析の台頭
まとめ
- 「基礎研究から応用研究へ進みつつあるが、一般的な標準手法と呼ぶにはまだ早い」
- 現状は、特定分野(ガラス工学、バイオメカニクス、粒状体物理など)で有効性が示されている先端技術の位置づけです。
- 今後、装置の簡便化や解析アルゴリズムの標準化が進めば、より一般的な計測法に近づく可能性があります。
ご希望であれば、「この手法が今後どの分野で一番先に“標準化”しそうか」という観点でも整理できますが、そちらもまとめますか?
3D光弾性トモグラフィーを行うためのシステムを構築したいのですが、参考になる論文を教えてください
以下は、装置構築に直結しやすい順での推奨論文セットです。各論文の「何を真似るべきか」を一言で添えました。まず読む(実装に直結)
- Aben et al., 2005, Optical Engineering — Photoelastic tomography for residual stress measurement in glass 自動化ポラリスコープ+回転ステージで多角度取得→再構成までを通しで解説。線形化アルゴリズムと実験系の要点がまとまっており、最短で全体像を掴めます。(spiedigitallibrary.org, ResearchGate)
- Tomlinson & Patterson, 2002, Experimental Mechanics — Phase-stepping in integrated photoelasticity 位相差・主応力軸3特性パラメータの高精度計測。位相ステッピング手順と実装の勘所(露光シーケンス、キャリブレーション)をそのまま流用可能。(スプリンガーリンク, ResearchGate)
- Yokoyama et al., 2024, Optics & Lasers in Engineering — High-speed photoelastic tomography for axisymmetric stress fields 偏光カメラ+高速計測で動的3D(軸対称)を再構成。カメラ選定・フレーミング・材料(ゲル)での実装条件が参考。まずは軸対称課題で成功率を上げたいときに有用。(サイエンスダイレクト, arXiv)
- Dave et al., 2024/2025, NeST(SIGGRAPH系) — Neural Stress Tensor Tomography マルチアクシス・ポラリスコープの実験セットアップを示し、Jones計算の微分可能前向きモデル+同時位相アンラップで一般形状の非線形逆問題を解く最前線。ハード構成とデータ取得の多軸化の設計指針として優秀。(arXiv, ACM Digital Library, VCC Imaging)
基礎理論・逆問題(設計の裏取り)
- Ainola & Aben, 2004, JOSA A — On the optical theory of photoelastic tomography 統合光弾性の逆問題の一般形と、どのときに積分量が応力テンソル成分に結び付くかを整理。装置で得られるデータと再構成の対応関係を理解する基礎。(オプティカ出版グループ, PubMed)
- Hammer & Lionheart, 2005, JOSA A — Reconstruction of spatially inhomogeneous dielectric tensors 弱複屈折近似下でのテンソル場トモグラフィーの数学。6面走査+ラドン型復元の理論枠組みは設計自由度の判断に有用。(arXiv, research.manchester.ac.uk)
- Ainola & Aben, 2007, JOSA A — Factorization of the polarization transformation matrix 前向き計算の高速化(変換行列の因数分解)。自作再構成コードの計算負荷削減に効く。(オプティカ出版グループ, PubMed)
- Aben, 2010, Inverse Problems in Science & Engineering — Abel inversion for tensor fields / Hybrid mechanics 軸対称の場合のAbel逆変換や力学拘束(平衡条件)を併用する“ハイブリッド”方針。軸対称ベンチマークの設計・検証に最適。(Taylor & Francis Online, epj-conferences.org)
バリアント/応用別
- Pietralunga et al., 2008, JOSA A — Reflection photoelastic tomography(導波路・薄膜) **反射配置(表面から)**でのトモグラフィ。厚みが取れない基板・薄膜/導波路応力に。(PubMed, ResearchGate)
- Li et al., 2024, PNAS — Interference Optical Projection Tomography (IOPT) for granular media 干渉計×投影トモグラフィで粒状体の3Dフォースチェーン可視化。干渉計ハードと多角度取得の運用が参考。(PNAS, PubMed)
- Wijerathne et al., 2002/2008 — Tensor/Stress field tomography based on 3D photoelasticity 荷重増分で線形化する実装志向の再構成。逐次載荷が可能な治具を設計する際の考え方に。(Keio University, サイエンスダイレクト)
装置づくりの「設計メモ」(論文に紐づく要点)
- 取得系:回転ステージ+(できれば)多軸照明・受光。多角度投影の自動化と位相ステッピングは Aben 2005 と Tomlinson 2002 を踏襲。(spiedigitallibrary.org, スプリンガーリンク)
- 偏光計:直線/円偏光の切替、1/4波長板の正確なアライメント、暗視野/明視野の切替が要点。高速化・動的現象は偏光カメラ運用(Yokoyama 2024)を参考。(サイエンスダイレクト)
- 媒質:屈折率マッチング槽の運用は古典的手順だが、投影直進性とS/Nに効く(Aben系の実装記述)。(spiedigitallibrary.org)
- 再構成:
- 軸対称の練習台→ Abel系の手法(Aben 2010)で堅実に。(Taylor & Francis Online)
- 一般形→ Ainola 2004/Hammer 2005の理論をベースに、NeSTの分析-by-シンセシスで非線形を直に解く。(オプティカ出版グループ, arXiv)
- キャリブレーション:位相ステッピング/光学軸の直交誤差補正は Tomlinson 2002 を基準に。偏光カメラのキャリブは近年の指針も参照可。(スプリンガーリンク)
使い分けの道筋(構築フェーズ別)
- フェーズ1(まず動かす):Aben 2005(線形近似)+Tomlinson 2002(位相ステッピング)で静的サンプル→ガラス/ゲルの既知ケースで検証。(spiedigitallibrary.org, スプリンガーリンク)
- フェーズ2(動的・高速):Yokoyama 2024の軸対称シナリオ+偏光カメラで秒間数千fps級に対応。(サイエンスダイレクト)
- フェーズ3(一般形3D):NeSTの多軸撮像+微分可能前向きモデルを導入し、非線形逆問題へ。(arXiv)
- 特殊用途:薄膜/導波路は反射トモグラフィ(Pietralunga 2008)、粒状体はIOPT(PNAS 2024)という選択肢。(PubMed, PNAS)
必要なら、これらをベースに部品表(光源・偏光素子・回転/傾斜機構・カメラ・屈折率マッチング槽・制御/再構成ソフト)の最小構成案も組みます。どの応用(残留応力/軸対称動的/一般形3D)から始めるか教えてください。