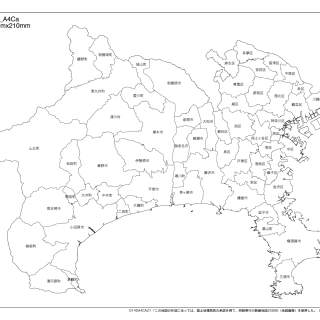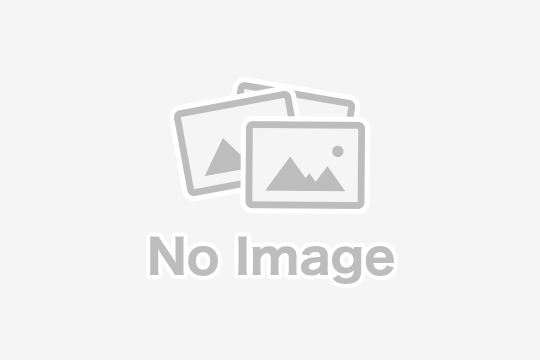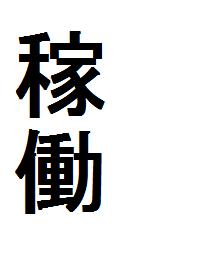はい。対流型(向流)熱交換器の対数平均温度差(LMTD)は次の式:
ここで
よって:
はい。対流型(向流)熱交換器の対数平均温度差(LMTD)は次の式:
ここで
よって:
答え
① 52 Kこの式は何かの公式から導出されたのですか?
はい。あの式(対数平均温度差:LMTD)は、局所的な熱伝達を積分して全体の熱流量を求めたときに出てくる公式で、以下の前提・導出から来ています。前提(向流熱交換器・定常・一定の全体熱伝達率
・物性一定)
- 高温流体と低温流体が逆方向に流れる(向流)。
- 熱交換面積全体を 、単位面積あたりの熱伝達率を として、局所温度差に比例して熱が伝わる(フーリエ型の拡散と同型)。
- 熱容量率(流体ごとの比熱×質量流量)をそれぞれ 、 (hot, cold)。
導出の骨子(対数平均温度差が出る流れ)
局所的な温度差を とすると、微小面積 を通る熱流は: 一方、エネルギー保存(熱容量率との関係)より: (符号は熱が高温流体から低温流体へ流れることを反映) これらを使って温度差の変化を表すと: しかし なので、 これを面積全体 から まで積分すると: ( :入口側の温度差、 :出口側の温度差) 一方、全体の熱流量は(熱容量率の組合せとして) また右辺を整理すると: (ここで という関係が上の対数式から導ける) よって が得られる。これが「対数平均温度差」の由来で、温度差が位置によって指数関数的に変化する結果としての平均的な駆動差です。補足:なぜ単純平均でないのか
温度差が直線的に変わるわけではなく、先ほどの微分方程式から分かるように指数関数的に減衰するため、単純な算術平均( )ではなく、対数的に重み付けした平均を取る必要があり、それが上の式になる。他の流れ(並流)の場合
並流(同方向流)のときも同様の導出をすると同じ形の式が出るが、 、 の取り方が変わる(並流では入口同士と出口同士の差を使う)。ご希望なら並流との比較図付きの導出メモや、熱交換器の効果量(NTU法)との関係、実務で使うときの補正係数(効果的面積のF因子)なども出せます。どれを深掘りしますか?
対数的に重みづけの分母をこのような形にすると平均対数になるというのを詳しく教えてください
いいところに目をつけてます 😊 「なぜ分母が (\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)) みたいな“対数”になるのか?」を、ちゃんと筋道立てて説明します。0. 出発点:「平均とはそもそも何か?」
熱交換器では [ Q = U A ,\Delta T_{\mathrm{lm}} ] と書きたいので、 「面積方向に平均した温度差」 を (\Delta T_{\mathrm{lm}}) と定義しています: [ \Delta T_{\mathrm{lm}} := \frac{1}{A}\int_0^A \Delta T(A'),dA' ] つまり本質的には普通の(面積での)平均値です。 “対数”なのは、(\Delta T(A')) の変化の仕方が指数関数になるせいです。1. 温度差の変化が「指数関数」になる
対向流熱交換器で、- 高温側:質量流量 (m_h), 比熱 (c_{ph}), 温度 (T_h(x))
- 低温側:質量流量 (m_c), 比熱 (c_{pc}), 温度 (T_c(x))
- 位置 (x) における温度差:(\Delta T(x) = T_h(x)-T_c(x))
2. 面積方向の平均をとるとどうなるか?
熱交換器全体の熱量は [ Q = \int_0^A U,\Delta T(A'),dA' ] ですが、(A'=P x) とみなせば [ Q = U\int_0^L \Delta T(x),P,dx = U P \int_0^L \Delta T_1 e^{-Kx},dx. ] 積分すると [ Q = U P \Delta T_1 \left[\frac{1 - e^{-K L}}{K}\right] = U P \Delta T_1 \frac{1 - \frac{\Delta T_2}{\Delta T_1}}{K} = U P \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{K}. ] 一方、LMTD で書きたい形は [ Q = U A ,\Delta T_{\mathrm{lm}} = U P L ,\Delta T_{\mathrm{lm}}. ] 両者を等しいとおくと [ U P L ,\Delta T_{\mathrm{lm}} = U P \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{K}. ] ここで (K L = \ln(\Delta T_1/\Delta T_2)) を使えば [ \Delta T_{\mathrm{lm}} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{K L} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)}. ] これが[ \boxed{ \Delta T_{\mathrm{lm}}
\frac{\Delta T_1-\Delta T_2} {\ln!\left(\dfrac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)} } ] です。 👉 ここで分かる大事なこと:- 分母の (\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)) は 「温度差が指数関数的に減っていく」微分方程式の解から自然に出てきたもの。
- 対数的に重み付けようとしたのではなく、 「面積方向の普通の平均」を ( \int \Delta T,dA) でとった結果、 たまたま指数関数の積分 → 対数が出てきた、という流れです。
3. 「対数的な平均」という別の見方(少し数学寄り)
数学的には、任意の正数 (a,b) に対して [ L(a,b) = \frac{b-a}{\ln(b/a)} ] を**対数平均(logarithmic mean)**と呼びます。 この (L(a,b)) には次の性質があります: [ \int_a^b \frac{dx}{x} = \ln\frac{b}{a} = \frac{b-a}{L(a,b)}. ] つまり [ L(a,b) = \frac{\text{区間長 }(b-a)}{\text{対数的“距離” }\ln(b/a)} ] という「対数スケール上での平均値」になっています。 熱交換器の場合は (\Delta T(x)) が指数分布 (\Delta T_1 e^{-Kx}) なので、 (x) を変数に積分すると自然と「対数平均」の形が出てきて、指数的に変化する量の平均をとると、対数が出る → 対数平均になるというわけです。
4. まとめ(質問への直接の答え)
「対数的に重みづけの分母をこのような形にすると平均対数になるというのを詳しく」✔ 分母の (\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)) は “対数的に重み付けしたくて入れたもの”ではなく、 温度差が指数関数的に減ることと 面積方向の普通の平均 (\frac{1}{A}\int\Delta T,dA) から自動的に出てきたものです。 ✔ その結果として [ \Delta T_{\mathrm{lm}} = \frac{\Delta T_1-\Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)} ] という形になり、数学的には「対数平均」と呼ばれる種類の平均になっています。
もし「算数レベルの具体例(数値を入れて、普通の平均・対数平均・幾何平均の違いを比べる)」みたいな直感的な説明も見てみたければ、それもやります!