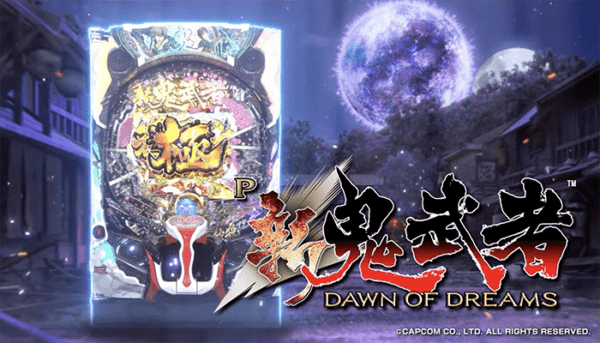IPネットワークの経路制御に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。この問題は、IPネットワークにおける経路制御(ルーティング)に関する知識を問うもので、「最も不適切なもの」を選ぶ問題です。https://kakomonn.com/gijyutushi/questions/80694
- ノードがパケットを受信したとき、次にどのノードに転送するかは、ルーティングプロトコルによって作成されたルーティングテーブルを参照して決定される。 経由ノードで同様の動作を繰り返すことにより、IPパケットは宛先ノードまで転送される。
- ルーティングプロトコルは、リンク状態型と距離ベクトル型に大きく分類される。 どちらのタイプのルーティングプロトコルにおいても、ノードはネットワークトポロジを把握して経路を決定する。
- リンク状態型ルーティングプロトコルでは、リンクの距離等の情報をネットワーク内に広告し、各ノードが、最短経路計算に基づいてルーティングテーブルを作成する。
- 距離ベクトル型ルーティングプロトコルでは、宛先ノードと各ノード間の距離情報がネットワーク内を伝搬し、各ノードが最短距離となる次ホップノードを決定し、ルーティングテーブルを作成する。
- 代表的なリンク状態型ルーティングプロトコルとしてOSPFやIS-ISなどがある。一方、代表的な距離ベクトル型ルーティングプロトコルとしてRIPなどがある。
各選択肢を確認していきます:
選択肢1:
ノードがパケットを受信したとき、次にどのノードに転送するかは、ルーティングプロトコルによって作成されたルーティングテーブルを参照して決定される。経由ノードで同様の動作を繰り返すことにより、IPパケットは宛先ノードまで転送される。✅ 適切な記述です。 IPネットワークではルーティングテーブルに基づき、次のホップ(転送先)を決めてパケットを中継していきます。
選択肢2:
ルーティングプロトコルは、リンク状態型と距離ベクトル型に大きく分類される。どちらのタイプのルーティングプロトコルにおいても、ノードはネットワークトポロジを把握して経路を決定する。❌ 不適切な記述です。これが正解。 この記述の誤りは、「どちらのタイプもネットワークトポロジを把握して経路を決定する」という部分にあります。
- **リンク状態型(例:OSPF, IS-IS)**はネットワーク全体のトポロジを把握して経路を決めます。
- しかし、**距離ベクトル型(例:RIP)**は自分の隣接ノードからの情報(宛先までの距離と方向)だけを元にルーティングを行い、ネットワーク全体の構成を知りません。
選択肢3:
リンク状態型ルーティングプロトコルでは、リンクの距離等の情報をネットワーク内に広告し、各ノードが、最短経路計算に基づいてルーティングテーブルを作成する。✅ 適切な記述です。 リンク状態型は、各ノードがネットワーク全体の構成情報を持ち、ダイクストラ法などで最短経路を計算します。
選択肢4:
距離ベクトル型ルーティングプロトコルでは、宛先ノードと各ノード間の距離情報がネットワーク内を伝搬し、各ノードが最短距離となる次ホップノードを決定し、ルーティングテーブルを作成する。✅ 適切な記述です。 距離ベクトル型では、隣接ノードから得た情報に基づいて、最短距離と次ホップを決定します。
選択肢5:
代表的なリンク状態型ルーティングプロトコルとしてOSPFやIS-ISなどがある。一方、代表的な距離ベクトル型ルーティングプロトコルとしてRIPなどがある。✅ 適切な記述です。 プロトコルの分類は正しいです。
正解:
👉 選択肢2 が 最も不適切なものです。この問題に出てくる専門用語を解説して下さい
もちろんです。以下に、問題文に出てきた専門用語を一つずつ丁寧に解説します。1. IPネットワーク
- 意味:IP(Internet Protocol)を用いて通信を行うネットワークのこと。
- 特徴:データをパケットに分けて送信し、宛先IPアドレスに基づいて経路を選択する。
- 例:インターネットや企業内ネットワーク(LAN)など。
2. ノード(Node)
- 意味:ネットワーク上の中継・終端装置。ルーター、スイッチ、サーバー、パソコンなど。
- 役割:パケットの送受信、中継、ルーティングなどを行う。
3. パケット(Packet)
- 意味:ネットワークで送受信されるデータの単位。IPネットワークではデータを小さな単位に分割して送る。
- 構成:宛先・送信元アドレス、データ本体、制御情報などを含む。
4. ルーティングテーブル(Routing Table)
- 意味:ノード(特にルーター)が、受け取ったパケットをどの経路で転送するかを判断するための表。
- 内容:宛先ネットワーク、次の転送先(ネクストホップ)、使用するインターフェースなどが記録されている。
5. ルーティングプロトコル(Routing Protocol)
- 意味:ルーティングテーブルを自動的に作成・更新するための通信ルール。
- 分類:主に以下の2つに分けられる。
- リンク状態型(Link State)
- 距離ベクトル型(Distance Vector)
6. リンク状態型ルーティングプロトコル(Link State Protocol)
- 特徴:
- 各ノードが**ネットワーク全体のトポロジ(構成図)**を把握。
- ダイクストラ法などで最短経路を計算。
- 通信量は多いが、収束が速くて安定。
- 代表例:OSPF(Open Shortest Path First)、IS-IS(Intermediate System to Intermediate System)
7. 距離ベクトル型ルーティングプロトコル(Distance Vector Protocol)
- 特徴:
- 各ノードは隣接ノードからの情報だけを使って経路を決定。
- ネットワーク全体の構成は把握しない。
- 計算は簡単だが、ループや収束の遅延が課題。
- 代表例:RIP(Routing Information Protocol)
8. ネットワークトポロジ(Network Topology)
- 意味:ネットワークの接続構造のこと。
- 例:バス型、スター型、メッシュ型など。
- ルーティングでは、どのノードがどのノードにどのように接続されているか、という情報が必要。
9. 広告(Advertisement)
- 意味:ルーティングプロトコルで、あるノードが他ノードに自分の持っている情報(リンク状態や経路など)を伝える行為。
- 例:OSPFでLSA(Link State Advertisement)を使ってリンク情報を送信。
10. 次ホップノード(Next Hop Node)
- 意味:パケットを宛先へ送るために、次に転送すべきノード(ルーターなど)。
- 重要性:IPルーティングでは、最終目的地ではなく「次の中継点」を常に見て送る。
必要であれば、それぞれのプロトコル(OSPF、IS-IS、RIP)についても詳しく解説できます。ご希望があればお知らせください。
トポロジとはなんですか?
「トポロジ(Topology)」とは、ネットワークにおいてノード(機器)やリンク(接続)がどのように配置・接続されているかを示す構造や図のことです。🔹 わかりやすく言うと:
トポロジはネットワークの見取り図や設計図のようなものです。 「どの機器がどのようにつながっているか」「経路がどこにあるか」を示します。🔹 トポロジの種類(代表例):
| トポロジ名 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 🌟 バス型 | 1本のケーブルにすべての機器が接続 | 簡単だがトラフィック集中に弱い |
| 🌟 スター型 | 中央のハブ(またはスイッチ)に各機器が個別に接続 | トラブル時の影響が限定的で、現在よく使われる |
| 🌟 リング型 | 各ノードが輪のように接続 | 障害に強いが、設定がやや複雑 |
| 🌟 メッシュ型 | 各ノードが他の複数ノードと接続 | 冗長性が高く、信頼性が高い |
| 🌟 ツリー型 | 複数のスター型が階層構造でつながっている | 大規模ネットワーク向け |
🔹 IPネットワークでの意味:
ルーティング(経路制御)では、トポロジがわかることで「どこを通れば目的地に一番早く届くか」「どこで障害が発生したか」を判断できます。- リンク状態型プロトコルでは、各ノードがこの「トポロジ」を把握し、全体の中から最適な経路を計算します。
- 距離ベクトル型では、トポロジ全体は把握せず、隣接ノードの情報だけで動作します。
🔹 語源的には…
「Topology」は数学の位相幾何学(トポロジー)に由来しますが、IT分野では「接続関係の形や構造」という意味で使われています。必要であれば図解付きで具体的なトポロジ例も作成できます。希望があればお知らせください。
ネットワークの構成はトポロジーとプロトコルとどんな要素できまりますか?
ネットワークの「構成」を考えるとき、トポロジー(どの機器がどう繋がっているか)とプロトコル(どんな通信手順を使うか)以外にも、以下のような要素で成り立ちます。- 物理媒体(Media)
- 有線:光ファイバー、UTP(ツイストペア)、同軸ケーブル など
- 無線:Wi-Fi(IEEE 802.11 系)、Bluetooth、セルラー(LTE/5G)など ネットワークの帯域・伝送距離・コスト・耐障害性を左右します。
- ネットワーク機器(Devices)
- ルーター、スイッチ、ハブ、無線アクセスポイント、ファイアウォール など それぞれが持つ性能(スループット、ポート数、機能)によってネットワーク性能や機能が決まります。
- アドレッシング/ネーミング(Addressing & Naming)
- IP アドレス体系(IPv4/IPv6)、サブネットマスク
- VLAN ID、MAC アドレス、DNS 名 └ これらをどう設計するかで、ルーティングの効率や運用のしやすさが変わります。
- 論理構造(Logical Design)
- サブネット分割、VLAN セグメンテーション、スタティックルート vs. ダイナミックルート
- 仮想ネットワーク(VXLAN、SD-WAN、SDN) └ ネットワークを柔軟かつ安全に拡張・分割するための設計要素です。
- ネットワークサービス(Services)
- DHCP(自動 IP 割当)、DNS(名前解決)、NTP(時刻同期)
- 認証/認可(RADIUS、TACACS+)、プロキシ、ロードバランサー など └ 利便性やセキュリティ、可用性向上のために必須です。
- セキュリティポリシー(Security)
- ファイアウォールルール、IPS/IDS、VPN、アクセス制御リスト(ACL)
- ネットワーク分離(VLAN/VPN/マイクロセグメンテーション) └ 内外部の脅威に対する防御・監査の仕組みです。
- 品質保証(QoS)/パフォーマンス管理
- 帯域制御(Traffic Shaping)、優先制御(DiffServ、IEEE 802.1p)
- 遅延・ジッタ・パケットロスの監視とチューニング └ 音声・映像などリアルタイム通信の安定性を確保します。
- 運用管理(Management)
- SNMP/Syslog/NetFlow による監視、設定自動化(Ansible、Terraform)
- モニタリングツール(Nagios、Zabbix、Grafana など) └ 状況把握・障害検知・設定管理を効率化します。
これらを組み合わせて、目的(企業 LAN/データセンター/ISP バックボーン/IoT ネットワーク など)や要件(帯域、遅延、可用性、コスト、セキュリティレベル)に最適化したネットワーク構成を設計します。