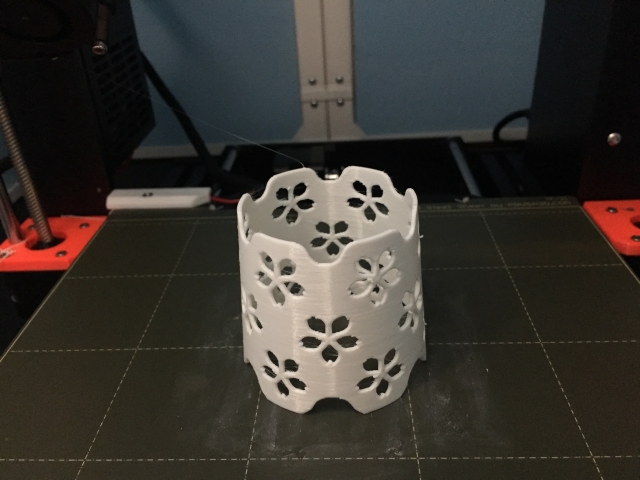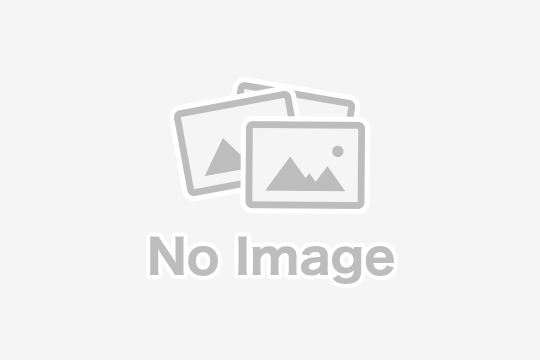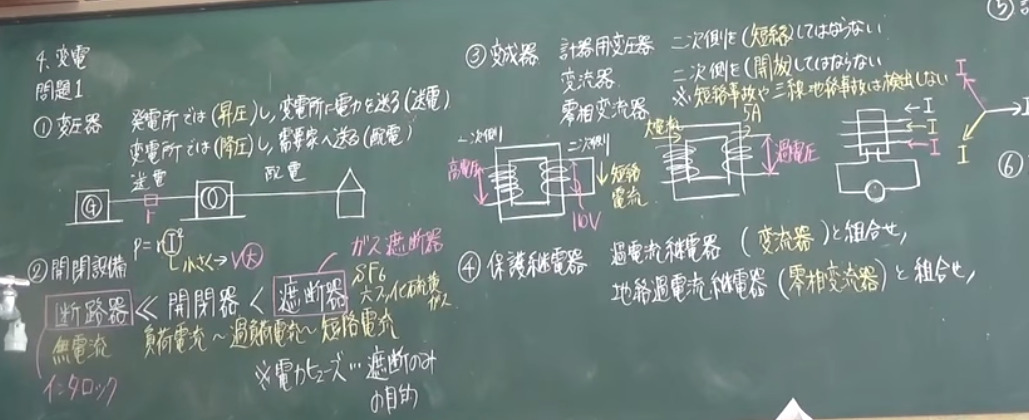電気事業法とその他の法規(まとめPDF:法規1)
電気工作物
〇電気工作物ではないもの
・30V未満で、30V以上の電気設備と接続されていないもの
・船舶、車両、航空機に設置されるもの
〇一般用電気工作物
・600V以下であり、郊外の電気工作物と電気的に接続していない(同一構内は可)
・小出力発電以外の発電設備が設置されていない
・爆発性・引火性のものが存在する場所に設置されていない
〇事業用電気工作物
・電気事業用電気工作物+自家用電気工作物
・高圧または特別高圧 で受電する
・構外にわたる電線路を有する
〇小出力発電設備:組み合わせても50kW未満にする
太陽電池発電設備:50kW未満
水力・風力発電:20kW未満
燃料発電・内燃力発電:10kW未満
※燃料電池は最大資料圧力は0.1MPa未満
保安規定に定めるべき事項
・業務管理者の職務・組織
・従業者の保安教育
・保安巡視・点検・検査
・電気工作物の運転または操作
・発電所停止時の保全方法
・災害・非常の場合に取るべき措置
・保安の記録
・法定自主検査に関わる実施体制と記録の保存
工事計画の事前届出
〇工事計画の事前届出の必要条件
受電設備の場合は、
・設置に関して:電圧1万V以上の受電設備の設置
・遮断器の増設変更:電圧1V以上かつ遮断容量(遮断電流)20%以上の変更
・1万kV・A以上の機器の取換え
太陽光の場合は、出力2000kW以上
〇変更工事の報告が必要な場合
・発電所または変電所の出力を変更した場合
・送電線路または配電線路の電圧を変更した場合
・発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業所または送電線路・配電線路を廃止した場合
電気主任技術者
〇設置者が電気主任技術者を選任義務が免除される場合(保安管理業務外部委託承認制度)
・電圧7000V以下の需要設備
・電圧7000V以下かつ出力が水力・火力・太陽光・風力発電2000kW未満、それ以外の発電1000kW未満
〇第三種電気主任技術者の保安監督ができる範囲
・5万V未満(発電出力は5000kW未満)
電気事故報告の義務
・感電死傷事故:被災者が死亡または治療のために入院した場合の人身事故
・ 電気火災事故・・・電気事故が原因で,建物が半焼または全焼した場合の火災事故
・需要設備の破損事故・・・ 1万V以上の「需要」設備のうち主要電気工作物の破損事故
5万 V 以上の架空送電線路および地中配電線路
・ 公共の用に供する施設等の使用を不可能にさせた事故(支持物倒壊による道路封鎖など)
・一般電気事業者に供給支障を発生させた事故( 3k V 以上)
電気用品安全法
電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動
を促進することにより,電気用品による危険および障害の発生を防止する。
・規制の対象は,一般用電気工作物・これに接続されている機械・器具・材料等
・特定電気用品とは,構造・使用方法が特に危険なもので,PSE と表示する
・電機用品を製造または輸入する事業を行う者は,事業開始の日から30日以内に経済産業大臣に届け出る。
電気工事士法
〇電気工事士の従事できる範囲
・第二種電気工事士 : 一般用電気工作物( 600 V 以下)のみ
・第一種電気工事士 : 一般用電気工作物 + 500 kW 未満の自家用電気工作物
ただし,ネオン用設備,非常用予備発電設備などの特殊電気工事は除く
・認定電気工事士 : 自家用電気工作物のうち 600 V 以下の 簡易電気工事のみ
・特殊電気工事士 → ネオン工事や 非常用予備発電工事 ※免状は工事内容によって違う
電気設備の技術基準~電線の接続,絶縁,接地工事,機械器具・避雷器の施設~(まとめPDF:法規2)
低圧電路の絶縁性能(電技第 58 条,解釈第 14 条)
・低圧配線の絶縁抵抗
電気使用場所の低圧電路の電線相互間,電路-大地間の絶縁抵抗は, 開閉器 または 過電流遮断器 で区切ることのできる電路ごとに,下表の値以上とする。
| 使用電圧の区分 |
絶縁抵抗 |
| 対地電圧 150 V以下 |
0.1 MΩ |
| 300 V以下
その他の場合 |
0.2 MΩ |
| 300 Vを超えるもの |
0.4 MΩ |
・絶縁抵抗測定が困難な場合は,同電路区分ごとの漏えい電流を 1 mA 以下に保つこと。
〇低圧電線路の絶縁抵抗
低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間および電線の線心相互間の絶縁抵抗は,使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の1/2000 を超えないようにする
絶縁耐力試験
下表の試験電圧を加えて, 10 分間耐えて絶縁性能を有するかどうかの試験を行う。
| 電路の種類 |
交流試験電圧Vt |
直流電圧 |
| 最大使用電圧が 7000 V以下 |
最大使用電圧Vmの1.5 倍
|
ケーブル 電路のみ直流試験
が認められている。直流試験は,交流試験の 2 倍
|
| 最大使用電圧が7000V超え~15000V以下
中性点多重接地式路 |
最大使用電圧Vmの0.92倍 |
| 最大使用電圧が7000V超え~60000V以下 |
最大使用電圧Vmの1.25倍 |
※回転変流器を除く交流の回転機では,上記の表と同様な交流試験電圧で試験を行うことができ,また,直流電圧を用いる場合,交流試験電圧の 1.6 倍の直流電圧を 10 分間加える。
〇最大使用電圧 Vm
・公称電圧 1000V 以下では, Vm= 1.15 ×V 公称
・公称電圧 1000V 超~500000V 未満では,Vm=1.15/1.1 ×V 公称
〇充電電流 IC = Vt/XC = 2πfCVt
〇充電容量 P = VIC = 2πfCVt^2
〇変圧器の絶縁耐力試験(解釈第 16 条)
試験される巻線と他の巻線, 鉄心および外箱 間に電圧印加し,上表と同様な交流試験電圧を 10 分間流す。
〇燃料電池,太陽電池,モジュールの絶縁耐力試験
充電部分と大地間に電圧を印加し,最大使用電圧の 1 倍の交流電圧(最低 500 V)もしくは,最大使用電圧の 1.5 倍の直流電圧を連続して 10 分間耐える試験
接地工事
種類
| 種類 |
主な対象 |
接地抵抗上限 |
接地線の太さ下限 |
| A種 |
(外箱)特別高圧・高圧 |
10 Ω |
軟銅線 直径2.6mm |
| B種 |
特高または高圧を低圧に変圧する変圧器の定圧側
300V超:中性点に
300V以下:定圧側の一端子 |
I[A]を1線地絡電流とすると、
2秒経過の遮断 ⇒ 150/I [Ω]
1秒超~2秒以内 ⇒ 300/I [Ω]
1秒以内 ⇒ 600/I [Ω] |
軟銅線 直径4mm
高圧または、35kV以下の特高と低圧を結合する変圧器ならばA種と同じ |
| C種 |
(外箱)300V超過の定圧 |
10 Ω |
ただし、低圧電路の地絡遮断が0.5秒以内のとき、500Ω |
軟銅線 直径1.6mm |
| D種 |
(外箱)300V以下の定圧 |
100 Ω |
軟銅線 直径1.6mm |
※B 種設置工事の目的は,高圧・特別高圧電路と低圧電路が 混触 したとき, 低圧電路の電位上昇 の危険を防止する。
接地抵抗の計算と接地工事の方法・省略条件
〇人が触れるおそれのある場所のA種・B種接地工事の施設方法
・接地極は、地下75cm以上の深さに埋設する
・上記以外の場合は、鉄柱の30cm以上の深さ、または金属体から1m以上離して施設する
・接地線を地下0.75mから地上2mの範囲を合成樹脂管等で覆う
・鉄骨を設置極として代用する場合、2Ω以下でなければならない
*鉄骨はA種、B種のみ
〇接地工事の省略条件
・C種・D種において金属体と大地間の電気抵抗Rが接地抵抗値よりも小さいとき
Rが10Ω以下ならばC種は省略可、Rが100Ω以下ならばD種は省略可
・機械器具を乾燥した木製の床に施設するとき
・人が触れるおそれがないように、木柱の上に機械器具を設置するとき
・使用電圧が直流 300V または対地交流電圧 150 V 以下の乾燥した場所に施設するとき
・鉄台や外箱の周囲に 絶縁 台を設けるとき
・二重絶縁構造の機械器具を施設するとき
・電源側に絶縁変圧器を施設し,かつこの変圧器の負荷側電路を接地しないとき
・外箱のない計器用変成器がゴム,合成樹脂その他の絶縁物で被覆されているとき
・乾燥した場所で 漏電遮断器 (定格感度電流が 15mA 以下,動作時間 0.1 秒以下)を施設するとき
避雷器
雷電圧による電路に施設する電気設備の破損を防止できるように避雷器を施設しなくてはならない。高圧および特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施す
〇避雷器の施設場所
・発電所、変電所の高圧および特別高圧の架空電線引込口および引出口
・35kV以下の特別高圧配電用変圧器の特別高圧側および高圧側
・高圧架空電線路から供給される受電電力500kW以上の需要場所の引込口
・特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口
技術基準(2)~遮断器,遮断器,公害・障害防止,発・変電所,支持物~(まとめPDF:法規3)
過電流遮断器の特性
〇低圧電路の過電流遮断器の特性
①低圧ヒューズ → 定格電流の 1.1 倍の電流に耐え,電流区分に応じて,所定時間内に溶断するもの
②配線用遮断器 → 定格電流の 1 倍の電流に耐え, 1.25 倍の電流で 60 分以内に溶断するもの(50A 以下)
〇高圧電路の過電流遮断器の施設
①包装ヒューズ → 定格電流の 1.3 倍の電流に耐え, 2 倍の電流で 120 分以内に溶断するもの
②非包装ヒューズ → 定格電流の 1.25 倍の電流に耐え, 2 倍の電流で 2 分以内に溶断するもの
地絡
〇地絡遮断器の施設義務がある箇所
①使用電圧が 60 V を超える金属製外箱の機器で人が容易に触れるおそれのある場所のある電路
②高圧・特別高圧電路の変圧器で結合される 300 V を超える低圧電路
③高圧・特別高圧の発電所の引出口,他の者から電気の供給を受ける受電点,配電用変圧器の施設場所 など
〇地絡遮断器の省略条件
①C 種または D 種接地工事の接地抵抗値が 3 Ω以下
②機械器具を 発変電所 ,開閉所に準ずる場所から引き出される電路
③機械器具を 乾燥 した場所に施設する場合
④対地電圧が 150 V 以下で 水気 がない場所に施設する場合(水気がある場所は×)
⑤当該電路の系統電源側に 絶縁 変圧器(機械器具側の電圧が 300V 以下)を施設し,かつ絶縁変圧器の機械器具側の電路を接地しない場合
⑥二重絶縁構造や絶縁変圧器があるときや,ゴム・合成樹脂その他の絶縁物で被覆されている場合
⑦機械器具に 簡易接触防護措置 を施す場合
公害防止
(1)公害などの防止(電技第 19 条)
①変電所,開閉所もしくはこれらに準ずる場所には,電気設備または電力保安通信設備には,「 ばい煙 防止」を図る必要がある。
② 中性点直接 接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には, 絶縁油 の公害への流出,地下への浸透を防止する措置を施さなければならない。
③ ポリ塩化ビフェニル(PCB) を含有する絶縁油を使用した電気機械器具は,電路にしてはならない。
(2)公害防止に関する届出
電気事業者または自家用電気工作物を設置する者は,「公害防止等に関する届出」が必要な場合には,所轄の
産業保安監督部長 に届け出る。
◆公害防止等に関する届出が必要な場合
① ダイオキシン 類に該当する電気工作物の 設置 ,又は排出量を 変更 する場合
②ダイオキシン類に該当する電気工作物の事故により大気中に多量に排出した場合
③使用されている電気工作物に 0.5 ppm を超える ポリ塩化ビフェニル(PCB) を含有する絶縁油を使用
していることが判明した場合
④ポリ塩化ビフェニル(PCB)の含有濃度が 0.5ppm 超過の絶縁油を使用している電気設備を 廃止 した場合
電気的・磁気的障害の防止
①電気設備は,他の電気設備その他の 物件 に 電気的 または 磁気的 な障害を与えないように施設しな
ければならない。
②高周波利用設備(電路を 高周波 電流の伝送路として利用するものに限る)は,他の高周波利用設備の機能
に重大な 障害 を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
③高圧・特別高圧の電気設備は,その 損壊 により電気事業者の電気の供給に著しい 支障 を及ぼさないよ
うに施設しなければならない。
◆誘導障害の防止
① 特別高圧 の架空送電線路の誘導障害では,
地表上1m における電界強度 3 [kV/m]以下になるようにする。
使用電圧 60000V 以下の場合,電話線路のこう長 12km ごとに誘導電流が 2 μA を超えないようにする。
使用電圧 60000V 超えの場合,電話線路のこう長 40km ごとに誘導電流が 3 μA を超えないようにする。
②変圧器などは,電技で定めている条件下では空間の磁束密度の平均値が商用周波数において 200 μT 以下
になるようにする
支持物の施設
通常の状態において断線のおそれがないように施設する→弛度(たるみ)が大きいと断線しにくい。
①安全率 硬銅線・耐熱銅線の場合は, 2.2 以上とし,その他の電線は 2.5 以上とする。
②たるみ D =WS2/8T *T は電線の引張荷重 ÷安全率 で計算
技術基準(3)~架空電線路,引込線,地中電線路,配線の施設~(まとめPDF:法規4)
架空電線路の施設
◆使用する電線にケーブルを用いる場合
①ハンガの間隔を 50 cm 以下とする
②ちょう架用線には,断面積 22 mm2以上の 亜鉛 めっき鉄より線または引張強さ 5.93 kN 以上のもの
③ちょう架用線およびケーブルの被覆に使用する金属体には D 種接地工事を施す
④ちょう架用線の安全率は, 2.5 以上
|
基準 |
低圧 |
高圧 |
| 歩道橋 |
歩道橋路面上 |
3 m |
3.5 m |
| 道路以外 |
地表上 |
4 m |
5 m |
| 鉄道 |
レール面上 |
5.5 m |
| 道路を横断 |
路面上 |
6 m |
架空電線と他物の接近
電線路の電線,電力保安通信設備または 電車線 などは,他の電線, 弱電流電線 などと接近・交さする場合または同一支持物に施設する場合には,他の電線・弱電流電線などを損傷するおそれがなく,かつ, 接触 ,
断線 などによって生じる 混触 による感電または火災のおそれがないように施設しなければならない。
〇接近状態
第一次接近状態→電線路の電線の 切断 ,支持物の 倒壊 などによって,他の工作物に 接触 するおそ
れがある状態
第二次接近状態→架空電線が他の工作物の上方または側方において水平距離 3 m 未満に施設される状態
引込線の施設
〇低高圧架空引込線
①低圧架空引込線 絶縁電線またはケーブルを使用
低圧では,電線はケーブルもしくは,直径 2.6 mm 以上の硬銅線または引張強さ 2.3 kN 以上のもの
ただし,径間が 15 m 以下に限り直径 2.0 mm 以上の硬銅線または引張強さ 1.38 kN 以上のもの
高さは,原則低圧架空電線と同様だが,道路横断は 5 m に緩和される。(技術上やむを得ない→3m)
②高圧架空引込線 絶縁電線またはケーブルを使用
高圧では,電線はケーブルもしくは,直径 5 mm 以上の硬銅線または引張強さ 8.01 kN 以上のもの
高さは,原則高圧架空電線と同様。
③連結引込線
低圧連結引込線は,分岐点から 100 m 以内, 高圧・特別高圧 の連結引込線は,原則施設してはならない。
〇低高圧屋側引込線
①低圧屋側引込線→直径 2.0 mm 以上の軟銅線か硬銅線(絶縁電線)または引張強さ 1.38 kN 以上のもの
①高圧屋側部分の電線は, ケーブル のみ。支持点間を 2 m 以下とし,ケーブル被覆に使用する金属体
には A 種接地工事(接触坊措置を施すと D 種接地工事)を施す。
地中電線路の施設
①地中電線は,他の電線, 弱電流電線 または管と 接近・交さ する場合には,故障時の アーク放電 に
より他の電線などを 損傷 するおそれがないように施設しなければならない。
②地中電線路は, 車両 その他の重量物による 圧力 に耐え,かつ当該地中電線路を埋設している旨の表示
などにより, 掘削工事 からの影響を受けないように施設しなければならない。
③地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには, 防火 措置を講じなければならない。
④電線には, ケーブル を使用し,管路式・暗きょ式または直接埋設式により施設すること。
⑤地中箱は,車両その他の重量物による圧力に耐える構造であること。地中箱のふたは, 施設者以外のもの が
容易に開けられないこと。
⑥ 爆発性 または 燃焼性 のガスが侵入するおそれがある場所に設ける大きさが 1m2 以上の地中箱には,
通風装置 その他のガスを拡散させる装置を設けること。
◆地中電線路の施設方式
①直接埋設式では,地中電線を堅ろうなトラフその他の防護物に収め,地中電線の埋設深さは, 車両 その他
の重質量の圧力を受けるおそれがある場合は 1.2 m 以上,その他の場合は 0.6 m 以上の土冠で施設する。
②管路式では,車両その他の重量物の圧力に耐える管を使用する。
③暗きょ式では,車両その他の重量物の圧力に耐える暗きょを使用し,かつ地中電線に 耐燃措置 を施すか,
または暗きょ内に 自動消火設備 を施設する。
④高圧・特別高圧地中電線路において, 直接埋設式 または 管路式 により施設する場合, 2 m の間隔
で, 物件 の名称, 管理者名 および 電圧 を表示する。ただし,需要場所から 15 m 以下の地点
ではこの規定から除かれる。
低圧配線の施設
〇住宅内電路の施設規則
①住宅の電圧電路の対地電圧は,原則として 150 V 以下とする。ただし, 2 kW 以上の電気機械器具と,
それに電気を供給する屋内配線を以下のように施設する場合, 300 V 以下でも可とする。
②屋内配線・電気機械器具ともに 簡易接触防止 措置を(人が容易にふれないように)施す。
③電気機械器具は,屋内配線と 直接 接続する。
④専用の 開閉器 および 過電流遮断器 を施設する。
⑤ 地絡 を生じたときに自動的に遮断する装置を施設する。
〇低圧幹線の施設
電動機の定格電流の合計 IM,他の電気使用機械器具の合計電流を IHとすると,幹線許容電流 IA[A]は,
①IM≦IH のとき,IA = IM + IH
②IM>IH のとき,IM≦ 50 のとき,IA = 1.25IM + IH
IM> 50 のとき,IA = 1.1IM + IH
低圧屋内幹線の分岐回路では,原則として分岐点から 3 m 以下の箇所に開閉器および過電流遮断器を施設
しなければならない。ただし,許容電流が定格電流の 35%以上 55 %未満の場合は 8 m 以下,許容電流
が定格電流の 55%以上の場合は制限なしとする。
過電流遮断器の定格電流 IB の上限値
3IM + IH もしくは 2.5IA のうち 小さい 方の値を採用する。
まとめPDF
【学習動画:電験合格】電験3種 法規のおすすめの勉強先リンク