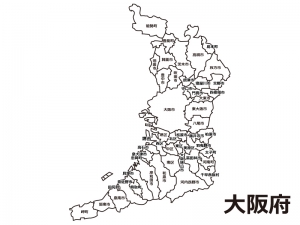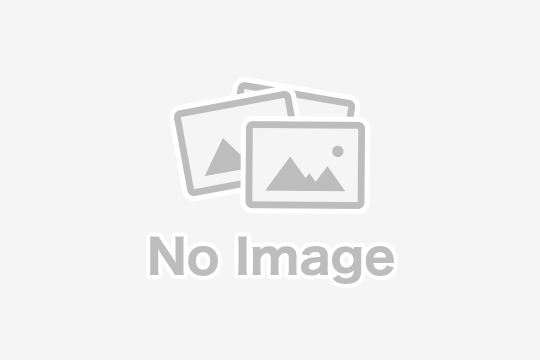野生チンパンジーの攻撃性に関する研究レビュー
集団間攻撃
- Issaバレー調査(Drummond-Clarke et al. 2023): タンザニア西部のサバンナ・モザイク生息地に暮らすIssa群で初めて観察された集団間の致死的攻撃事例を報告している。オス8頭のグループが離れた群の雌とその幼獣(2–3歳)に襲いかかり、幼獣を殺害・去勢した(死体は約1時間保持された)。この事例は、乾燥地帯のチンパンジー群では攻撃性が低いとの従来仮説を否定し、資源が局所的に豊富な場所(例:小さな食物集中地)が存在すると、低密度でも激しい群間攻撃が誘発されうる可能性を示唆している。
- Gabon・Loango公園(Martínez-Íñigo et al. 2021): 中部亜種(P. t. troglodytes)の単一群(Rekambo群)を24年間観察し、周辺群との遭遇や殺害事例をまとめた。群間遭遇は年平均で他地域より少なかったが、殺害率は東部亜種並みに高かった。オスが境界パトロールや攻撃の主役で、記録された攻撃的遭遇12件のうち少なくとも5件に雌も参加していた。特にオス主導での集団的防衛行動が顕著で、見張り・襲撃では雌とその幼獣も同行しながら攻撃が実行されることが示された。
- ナンゴゴ(Watts et al. 2014): ウガンダ・キバレ国立公園のナンゴゴ群では、境界パトロール中に少なくとも4例の集団間インファンティサイド(オスによる幼獣殺し)を記録した。これらは豊凶周期の果実(mast fruiting)に伴って隣接群との遭遇頻度が増した時期に発生し、犯行後に攻撃群が攻撃地点周辺を占拠したため、攻撃群側のメスの餌場拡大につながる「テリトリー拡張仮説」を支持する結果となった。この研究は、複数例の境界パトロール時の致死攻撃にもとづき、野生チンパンジーにおける集団間殺傷は珍しくない共通の特徴であると結論付けている。
集団内の暴力
- 支配順位争いと攻撃性: 高位オスは集団内での攻撃行動頻度が高く、攻撃性とテストステロン値とも正相関していた。一方で、高テストステロン値の個体ほど必ずしも他個体に対して多く攻撃するわけではなく、支配的地位に伴う体格(筋肉量)の違いが順位とホルモンの相関を説明していた。すなわち、高順位になると他個体との争い(地位確立・維持)に積極的になることが多く、その結果として交尾機会や生殖成功が増す傾向にある。
- 性的強制: 野生調査では、**非発情期の雌への攻撃(性的強制)**が高順位オスの生殖成功と有意に結びつく例が報告されている。具体的に、メスの発情期外に攻撃的に干渉するほど、そのオスの子を得る確率が高くなる傾向が示された。ただし、西部コートジボワール(Taï)群の事例では、オスによるメスへの直接的攻撃は稀であり、攻撃行動自体は主に支配順位獲得の手段であって、生殖的選択を直接強制する効果は弱いとする報告もある。
- 若年オスの攻撃行動: 思春期前後の若年オスでも、地位獲得の努力としてメスに対し攻撃的になることがあるが、これも支配欲求による行動であり、性的強制よりも優先度の高い社会的地位の形成が動機と考えられる。
インファンティサイドや雌への攻撃
- 雌主体のインファンティサイド: 従来「メスはおとなしい」とされてきたが、Budongo(ウガンダ)のソンソ群では雌主体の幼獣殺しが複数記録された例がある。Townsendら(2007)は、ソンソ群の成獣雌(母親)らが他群の幼獣を攻撃・殺害する事件を少なくとも3件観察し、「雌の攻撃性は男性ほど目立たないものの、無視できない」ことを示した。これらの事例の多くで殺された幼獣は生後間もない子であり、母親は負傷したものの生き残ったと報告されている。
- オス主体のインファンティサイド: Budongoの同群では24年間で計33件の幼獣攻撃が記録され、そのうち11件が確実な殺害例だった。攻撃者が特定できた23件はいずれも複数のオスから成っており、犠牲になった幼獣の約2/3が生後1週未満だった。このデータは、犠牲者の多くが母親の再発情を促しオスの繁殖機会を高める「性的選択仮説」を支持している。肉食(幼獣の肉利用)は副次的で稀な行動にとどまり、餌資源獲得仮説の証拠は見られなかった。
- 外群による雌攻撃: 前述のIssa事例でも、攻撃の標的は遭遇した一匹の雌とその幼獣であり、集団外のオスによる攻撃が孤立したメスと子を狙う傾向を示していた。これらのことから、チンパンジー社会では幼獣や母親の攻撃も、主に生殖戦略の文脈で説明される行動であると考えられる。
社会的・生態的要因
- 資源分布と季節変化: 資源が散在するサバンナ環境でも、特定の食物が豊富な領域がある場合、そこを巡る群間競合が激しくなる可能性が示唆されている。例えばIssa群の場合、食物分布が広範でも局所的な果実集中地を巡って陣取り争いが起こりうることが示唆された。またナンゴゴ群の例では、果実の豊凶周期(mast fruiting)に伴う境界付近での遭遇増加が一連の攻撃を引き起こし、結果的に攻撃群のテリトリー拡大につながった。こうした結果は、果実の豊富さや季節パターンが集団間闘争を活性化させる要因となりうることを示している。
- 社会構造と個体差: オス同士の連携行動には、鍵となる個体の存在も影響する可能性が指摘されている。成功群では決定的な機会に率先する個体がおり、彼らの存在が攻撃開始の引き金になる場合がある。実際、「成功した群はライバル群のテリトリーを奪う」ことが知られており、領域拡張によってその群の生殖成功が高まると考えられている。また大群では協調的な境界監視(集団的パトロール)が可能になる半面、個体間の社会的結び付きや順位安定度が攻撃に与える影響も大きい(階級が不安定な時期には攻撃性やストレス増加が認められる例がある)。
- 繁殖戦略と選択圧: 上述のように、多くのインファンティサイドや性行動は性的選択に起因すると考えられる。オスは自らの繁殖成功を高めるため、競合する個体の子を排除したり、メスへの接近を攻撃で制限しようとする。一方、メスは機会を増やすために複数のオスと交尾する戦略を取り、攻撃をかわす動きが観察されることもある。これらの戦略的相互作用が、攻撃行動の出現頻度や形態を決める社会的要因となっている。
ボノボとの比較
- 集団内攻撃頻度: 近縁種ボノボとの比較では、オス同士の集団内攻撃について意外な結果が得られている。Mouginotら(2024)は、3群の野生ボノボと2群の野生チンパンジーを同様の手法で追跡し比較し、ボノボの方がチンパンジーより集団内攻撃の頻度が高いことを見いだした。ただし両種とも、攻撃的オスは繁殖機会が増える傾向が共通していた。従来「チンパンジーは好戦的、ボノボは平和的」とされてきたイメージに対し、「ボノボのオスも積極的に攻撃を用いる」複雑な性質が明らかになりつつある。
- 雌の役割と集団間関係: ボノボ社会では雌同士の連携が強く、オスによる致死的攻撃は比較的まれとされる(異群交遊や融和行動が多い)。一方、チンパンジーでは雌主体の攻撃例も報告されるなど、雌の攻撃性の表れ方にも種間差がある。総じて、ボノボでは集団内の衝突が平和的解決される傾向にある一方、チンパンジーでは激烈な対立が頻発するという違いが指摘されている。
1. 捕食行動に伴う争い チンパンジーは雑食性ですが、とりわけ霊長類を含む小型から中型の哺乳類を襲って捕食することで知られています。特に有名なのが、東アフリカや中央アフリカの一部の個体群における「レッドコロブス(赤コロブスザル)集団」への集団狩猟です。
- 赤コロブスザルに対する集団的襲撃 コートジボワールやウガンダ、タンザニアなどで観察されており、チンパンジーのオスを中心に複数頭が集団を形成し、木上にいる赤コロブスザルを追い立てる形で片端から捕縛します。捕獲された個体は樹上から地上へ引きずり落とされることもあり、その際に仲間のチンパンジーが協力しつつ引き離す様子が報告されています(例:Ngogo研究地など)(greencorridor.info)。
- その他の霊長類や小型哺乳類 赤コロブスザル以外にも、ウガンダ・ブドンゴ森林(Budongo Forest)では、チンパンジーがマングベイサル(Mangabey)やダイアノサル(Colobus guereza)を襲う事例があります。また、西アフリカではパーレイアントロプスとして知られるオールドワールドモンキー類(Cercopithecus属)も捕食対象になり、群れの幼獣が狙われることが多いとされています(greencorridor.info, link.springer.com)。
2. 中・大型哺乳類(ウマ目・ウシ目など)との衝突 チンパンジーは主に森林域に生息しますが、そこにはシクレ(シカの一種)やブッシュバック、デューカー(Duiker)といった小型~中型のウシ目動物も含まれます。これらを捕食する際、チンパンジーは地上を歩く個体を見つけると地上まで追いかけ、歯や手足で咬みついて仕留めることがあります。
- デューカーやブッシュバックへの襲撃 西アフリカの研究地では、チンパンジーが単独または少数頭でデューカーの幼獣を襲う記録があり、捕捉の際に木陰まで追い詰めて殺すことがあると報告されています。こうした行動は個体によって頻度に差があるものの、食物不足時や機会を見つけた際に発生しやすいと考えられています(greencorridor.info)。
- カメ類(リクガメなど)への攻撃 一部のチンパンジー集団では、地上でゆっくり歩くリクガメを発見すると、棒などで甲羅を叩いて割れ目から肉を引き出して食べる行動(カメの甲羅打ち割り行動)が報告されています。これは高度な道具使用行動の一例とも捉えられており、対象が逃げられず防御手段も少ないため、比較的容易に成功する捕獲対象です(greencorridor.info)。
3. 同属他種(ゴリラ)に対する致死的攻撃 極めて稀ながらも、チンパンジーが同属ではないが同じ類人猿であるゴリラに対して集団的、致死的な攻撃を行ったという報告があります。
- ガボン・ルアンゴ国立公園における二例 2021年に発表された研究では、西アフリカ・ガボンのルアンゴ国立公園で、パントログロディテス亜種のチンパンジーがシロテナガザル(Gorilla gorilla gorilla)の幼体複数頭をターゲットにし、数に勝るチンパンジーが連携して襲うという致死的攻撃事例が少なくとも2回観察されました。いずれも幼獣が犠牲になり、母親をはじめとする成獣のゴリラは逃走や抵抗を試みたものの、チンパンジー群の数的優位と集団行動が功を奏して幼獣は殺害されたとされています。論文では、「捕食(predation)」と「競合(competition)」の両面が交錯した行動であり、チンパンジーの領域防衛的な集団行動とゴリラ個体の社会的脆弱性が重なった可能性が指摘されています(nature.com)。
4. 捕食者・脅威動物との攻防 チンパンジー自身が他種の捕食者から狙われるケースもあり、その際に激しい攻防が見られます。代表的なのがヒョウやニシキヘビです。
- ヒョウ(Panthera pardus)との攻防 アフリカの森林域ではヒョウがチンパンジーを襲うことがあり、特に幼獣や負傷個体がターゲットになりやすいとされています。複数の研究で報告される例では、チンパンジーは仲間を呼び寄せて木の高い位置へ逃げ込み、長い枝を振り回す、集団でヒョウを取り囲むなどしてヒョウを追い払おうとする防衛行動が確認されています。こうした「群れを挙げた追い払い行動」は、領域性の強いチンパンジー社会の結束の現れとも言え、実際にヒョウを撃退できた例も報告されています(greencorridor.info)。
- ヘビ(ニシキヘビなど)との攻撃・防衛行動 西アフリカや東アフリカの密林地帯では、ニシキヘビ類(Python属)やジムグリ(boas)のような大型のヘビがチンパンジー幼獣を捕食することがあります。チンパンジーはヘビを発見すると数頭でヘビを石や棒で打ち払い、最終的には噛みついて殺すことがあります。いくつかの個別報告では、ヘビを担ぎ上げて木の根元にたたき落とす様子や、集団で協力してヘビをぐるぐる巻きにして除去する行為も観察されています(greencorridor.info)。
5. 幼獣・他個体群との小競り合い 上記のような「捕食」や「致死的攻撃」には至らないものの、チンパンジーと他種の動物が食料や縄張りを巡って衝突する小規模な事例も多数あります。
- 果実資源を巡る競合 熱帯雨林では、チンパンジーと他の霊長類(例えばコロブスザルやマントモンキー)が同じ果樹を好んで利用します。チンパンジーは力や体格で優位なため、果実が大量になっている樹冠に他種のサルが近づくと、威嚇して追い払う行動が見られることがあります。この結果、他種のサルは離れた木でしか採食できず、チンパンジーが消費を終えて去った後にようやく辿り着く、という「先に遺棄された残余資源」を利用する傾向が観察されています(greencorridor.info)。
- 地上採食場所での衝突 チンパンジーは地上にも降りて果実を拾ったり昆虫を捕ったりしますが、その際にシクレ(小型のシカ類)やイノシシなどのほ乳類と鉢合わせになることがあります。シクレやイノシシはチンパンジーの方が大きくて力も強いため、チンパンジーが威嚇して相手が退散するケースが大半ですが、ときにイノシシが突進してきてチンパンジーが木に逃げる、あるいは逆にチンパンジーが集団でイノシシを追い払うといった小競り合いが報告されています(greencorridor.info)。
まとめ チンパンジーと他種の動物との争いは、大きく分類すると以下のようになります。
- 捕食行動による対立・攻撃:赤コロブスザルやデューカー、カメ類などを獲物とした「狩猟・捕食」行動。
- 致死的な異種への攻撃:ゴリラ幼獣に対する集団攻撃など、稀ながら非常に衝撃的な事例。
- 捕食者・脅威動物への防衛行動:ヒョウや大型ヘビなどから幼獣や集団を守るための「追い払い・攻撃」。
- 資源を巡る小競り合い:果実採食の優先権を巡る霊長類間の威嚇、地上採食場所でのイノシシ・シクレなどとの小競合。
参考文献(主要出典)
- Humle, T., et al. (2011). Chimpanzee interactions with nonhuman species in an anthropogenic habitat. (PDF全体を通じて、多種多様なチンパンジーと他種の相互作用をまとめている)(greencorridor.info)
- Southern, L. M., Deschner, T., & Pika, S. (2021). Lethal coalitionary attacks of chimpanzees (Pan troglodytes troglodytes) on gorillas (Gorilla gorilla gorilla) in the wild. Scientific Reports. (チンパンジーによるゴリラ幼獣への致死的攻撃を初めて記録・解析)(nature.com)