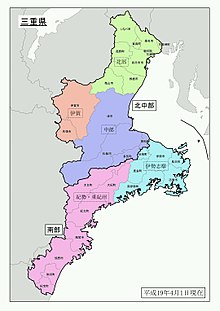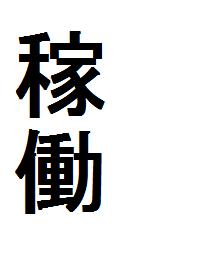この動画では、NVIDIAの株価が過去最高値を更新し、一時的に時価総額が3兆ドルを超えた背景にある「ニューラルネットのスケーリング則」について解説しています。
スケーリング則とは? [03:42]
スケーリング則とは、ニューラルネットワークの性能が、モデルのパラメーター数、学習に使うデータ量、計算リソースを増やすことでどのように向上するかを示す法則です。つまり、モデルを大きくしたり、より多くのデータを使ったり、計算量を増やすことで、予測可能な形でパフォーマンスが向上するという経験則です。
スケーリング則がNVIDIAの株価に与える影響 [ 06:19 ]
09:33 ]
- 従来のコンピューター業界では、ハードウェアの性能向上とソフトウェアの進化が二人三脚で進んできました。しかし、ニューラルネットワークにおいては、ソフトウェア側が人間が書くものではなくニューラルネットであるため、ハードウェアの性能を上げれば、単にパラメーター数を増やすだけで性能が向上するという「スケーリング則」が当てはまります。
- これにより、ハードウェアに投資すればするほど性能が向上するという状況が生まれ、各社がAI開発に巨額の資金を投じるようになりました。 [
07:06 - この開発競争において、ニューラルネットの計算、特に学習プロセスにおいて最も有効なハードウェアがNVIDIAのGPUであるため、NVIDIAのGPUに対する需要が爆発的に増加しました。 [
08:14 - NVIDIAは競争相手が少ないため、高い利益率でGPUを販売しており、品不足の状態が続いています。これがNVIDIAの売上と利益、そして株価を押し上げている主な要因です。 [
08:32
-
- 中国のDeepSeek社が、古いGPUを使ってより少ない計算量で大規模言語モデルを開発した事例が紹介されました。 [
10:14 - これは、同じGPUからより高い能力のモデルが作れるようになれば、NVIDIAのGPUの需要が減るのではないかという懸念を生みましたが、実際には逆で、コストが下がることで新たな用途が生まれ、市場がさらに拡大すると考えられています。 [
11:05 - 例えば、大規模言語モデルの呼び出しコストが下がったことで、キーボード入力中のオートコンプリートなど、リアルタイムでのAI活用が可能になりました。 [
12:24 - 同様に、テキストから画像を生成するコストが下がり、今後はテキストから映像を生成するコストも下がれば、Instagramでのアニメーション投稿など、一般ユーザーがAIを日常的に活用する機会が増えることが期待されています。 [
12:45 - このように、AIを活用した分野の広がりは今後も大きく、コストが下がることでこれまでハードルが高かった技術やサービスがより多くの人にとって身近なものになり、新たなイノベーションが生まれると予測されています。 [
13:40
- 中国のDeepSeek社が、古いGPUを使ってより少ない計算量で大規模言語モデルを開発した事例が紹介されました。 [
同じGPUからより高い能力のモデルが作れるようになれば、NVIDIAのGPUの需要が減るのではないのでしょうか?
いいえ、動画の解説によると、同じGPUからより高い能力のモデルが作れるようになっても、NVIDIAのGPUの需要は減らないと考えられています。
その理由は、コストが下がることで新たな用途が生まれ、AI市場がさらに拡大すると予測されているからです。例えば、大規模言語モデルの呼び出しコストが下がったことで、キーボード入力中のオートコンプリートなど、リアルタイムでのAI活用が可能になりました。同様に、テキストから画像を生成するコストが下がり、今後はテキストから映像を生成するコストも下がれば、Instagramでのアニメーション投稿など、一般ユーザーがAIを日常的に活用する機会が増えることが期待されています。
このように、AIを活用した分野の広がりは今後も大きく、コストが下がることでこれまでハードルが高かった技術やサービスがより多くの人にとって身近なものになり、新たなイノベーションが生まれると予測されています。