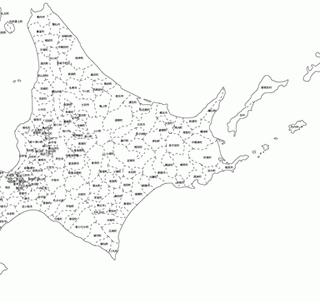わが国では、生産性というと労働生産性を想起する事が多いのではなかろうか。
労働生産性とは、労働者1人当たりが生み出す成果であり、付加価値額を労働投入量(労働者数またはのべ労働時間)で除したものとされる。
日本の生産性本部で公表されているOECD(欧州経済協力機構)の国際比較によると、我が国の労働生産性はOECD諸国の中では2016年では20位であり、
過去20年間においてもその順位はほぼ変わらない。
我が国は生産性が低いという一般的な認識は、このOECDの統計においても裏付けられているといえる。
しかし労働生産性は、生産性の測定指標として問題があることも古くから指摘されている。
労働生産性指標に対する批判的検討
まず労働生産性の分子について考えたい。分子に付加価値額を用いる場合、ここに価格の要素が含まれることから、
アウトプット(生産・販売量)を一定にして、価格をあげれば労働生産性の指標が改善する。
労働生産性に限らず、一般的に生産性を上昇するとは、同じ生産要素の投入のもとで、より多くの生産・販売量を生み出せるようになるということである。
そこで、生産性はそもそも価格とは関係ない指標であり、価格を単に引き上げるのみで生産性が向上するというのは、
定義に問題がるあるからだといえる。
付加価値額を生産性の分子に用いることによって、産業が寡占化・独占化すると生産性があがったり、儲ける事が生産性をあげたりすることが統計上生じ得るのだ。
他方で、労働生産性に限らず、生産性の指標には付加価値が広く用いられているのは、データ利用の限界からきているものと想像される。
生産・販売される物理的な量(例えば鉄鋼で言えば、生産や販売に係る鉄鋼トン数であり、電力であればkWhやkW)がデータでは捕捉できないことも多く、
その場合には付加価値額を使わざる追えない。
付加価値額を生産性指標の分子に用いることによって生じるバイアスについてKletteand Griliches(1996)によって明示的に指摘され、
それ以来、バイアス解消のために様々な取組がなされているが、未だに実務的な付加価値額を用いることが多く、生産性指標の解釈には注意を要する。
全要素生産性
労働生産性の問題を解消する一つの指標が全要素生産性(TFP)である。
TFPとは労働のみならず、生産に必要とされる主要な生産要素(資本等)を勘定した上で、それらの生産要素が生み出す生産量の増加以外の要素量的に表した指標である。
一般的には、資本や労働の質、イノベーションなどといった、生産要素としてデータでとらえられていないが、生産増に貢献するような因子を総合したものをTFPとよぶ。
TFPは、労働生産性と異なり、労働のみならず、他の主要な生産要素の投入量も考慮していることから、
労働生産性の問題点を解消しており、生産性の指標としても望ましい性質を持つ。
他方で、TFPの測定単位は指数化しており、労働生産性のように労働者一人(あるいは一時間)あたりが生み出す付加価値(円)や
生産量(鉄鋼ならばトン数)というようなわかりやすい指標ではないことから、TFPのレベル感をイメージしにくい。
こうした事情から、TFPを指標として用いるときには、変化率で表現することが多い。
OECD諸国のTFPの変化率をここ20年余りで比べてみると、確かに日本の生産性は大きく低下したが、2000年代にはいると他のOECD諸国のTFPは低位に収斂してきており、
我が国のTFPはやや高めにも見える。
もっと知るには・・・