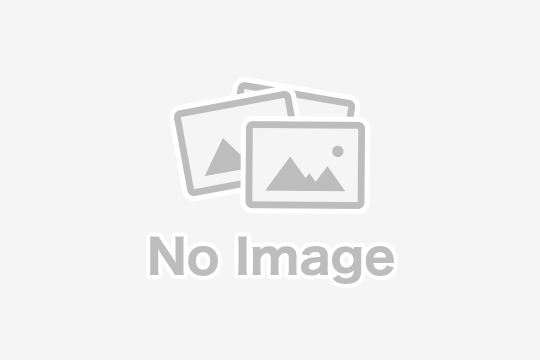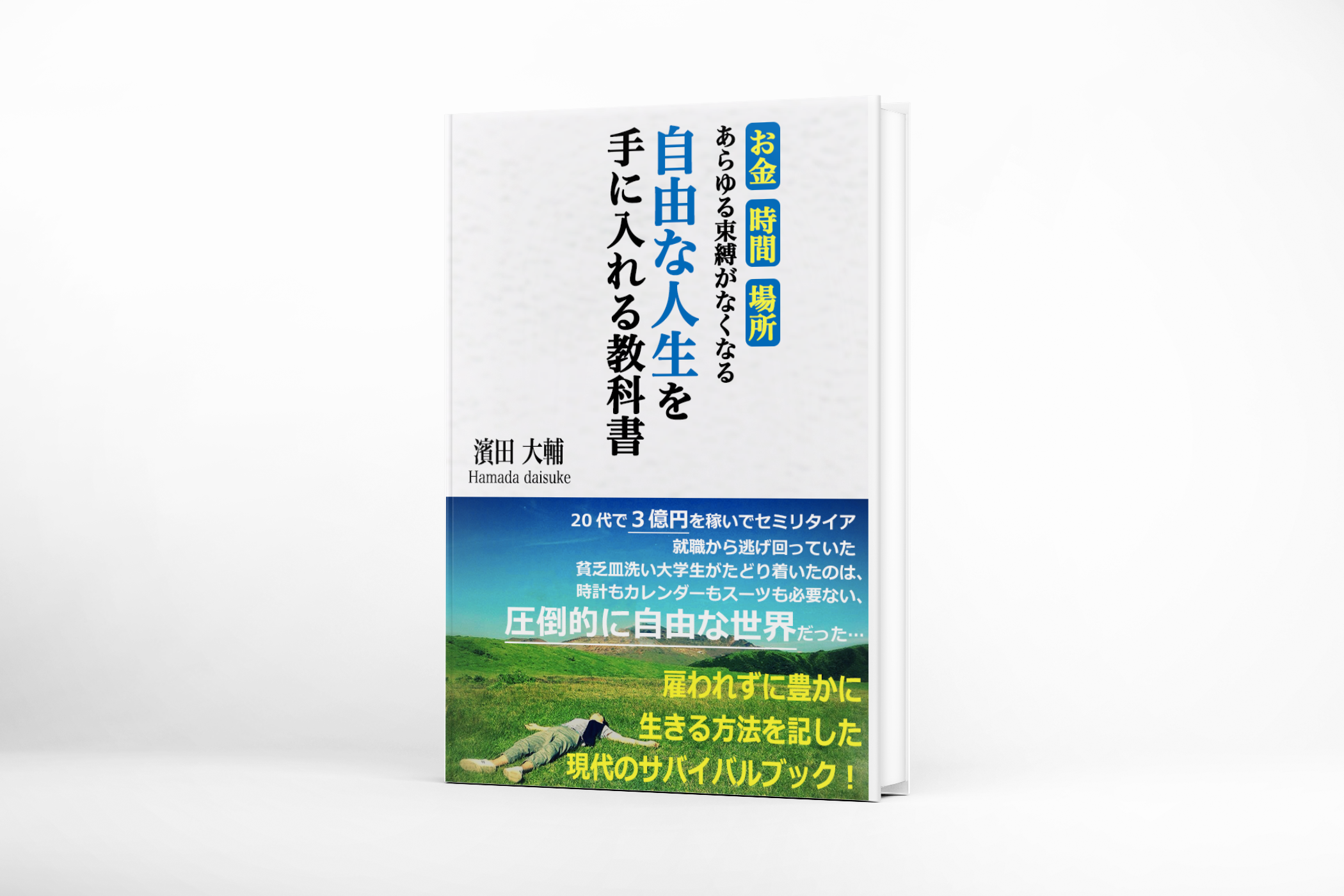答え:⑤
各指標
- ア:立ち上がり時間 (Rise Time)
ステップ入力後,出力が 0.1
(10%)から 0.9
(90%)へ到達するまでの時間。図では初期立ち上がり部分を示す短めの横矢印。
- イ:行き過ぎ時間 (Peak Time)
出力が最初の最大値(オーバーシュート頂点
)に達するまでの時間。図のピーク位置(縦破線)までの矢印。
- ウ:整定時間 (Settling Time)
出力が初めて ±5% バンド(0.95
~1.05
)内に入り、以後その帯域を外れなくなるまでの時間。図で最も長い矢印。
したがって組合せは
ア=立ち上がり時間,イ=行き過ぎ時間,ウ=整定時間 の
⑤ が正解です。
補足
- 最大オーバーシュート量は
(図では 1.05
付近)で示されているが、今回の矢印では“値”ではなく“時間”の指標を問うもの。
- 他の定義(遅れ時間 50% 到達など)を使う文献もあるので、問題図と読みの整合が重要です。今回はご指定の読み取りに合わせています。
参考:
技術士第一次試験-令和2年度機械部門Ⅲ-14解答例 | 技術士のたまご
立ち上がり時間、遅れ時間、行き過ぎ時間、整定時間について教えてください。
以下,ステップ応答に対して頻出の 4 つの時間指標
遅れ時間 (delay time),立ち上がり時間 (rise time),行き過ぎ時間 / ピーク時間 (peak time),整定時間 (settling time)
を体系的にまとめます。
0. 前提:典型的な 2 次標準形
制御入門で多く用いる代表モデル:
単位ステップ入力に対する(
の)出力
この式から各時間指標が導かれます。以下では「最終値(定常値)」を
と書きます。
1. 遅れ時間 (遅れ時間
, Delay Time)
定義(典型的): ステップ入力後,出力が最初に
50%(0.5
)に到達するまでの時間。
教科書や分野によって 10% あるいは某パーセンタイルを使う定義もありますが,日本語「遅れ時間」は Ogata などで 50% 到達時間を指すことが多いです。
意味: 応答が立ち上がり始めてから“半分”に達するまでの『初動の遅れ感』を表す。
備考: 1 次系(
)なら
なので
.
2 次標準形(
が 0.2~0.8 程度)では解析解から求められるが,設計では重要度が低いため実務では頻繁には要求されない。
2. 立ち上がり時間 (立上り時間
, Rise Time)
定義(よく用いられる): 出力が
10% から
90%(0.1~0.9
)に上昇するのに要する時間。
- 別定義:0%→100%(非振動・無オーバーシュート系)、5%→95% など。仕様書では必ず定義の百分率を明示すること。
意味: 応答の早さ(スピード感)を示す指標。
2 次標準形の近似式(
):
厳密には
これは 0→100% を仮定した形。10–90% 定義ではわずかに短くなる(ζ=0.5 付近で約 0.35/ζω_n 程度)。
簡便近似(
):
t_r \approx \frac{1.8}{\omega_n} \quad(\zeta\approx0.6\) のとき)
ただし ζ 依存を無視した粗い目安。
3. 行き過ぎ時間 / ピーク時間 (ピーク時間
, Peak Time)
定義: 最初のオーバーシュート(最大値)に達するまでの時間。
式(2 次標準形):
関連:最大オーバーシュート
(%表示は
)。
ピーク値
.
意味: 最初の振動が現れる速さ(振動性モードの“周期的速さ”)。
4. 整定時間 (整定時間
, Settling Time)
定義: 出力が指定された許容誤差帯(±2% あるいは ±5% が標準)に入り,
その後離脱しない で留まるようになるまでの時間。
(問題文の図では ±5% バンド:0.95~1.05。)
2 次標準形の近似式:
指数包絡線
を用い
意味: “十分落ち着く” までの時間。設計仕様・比較に最も多用される。
5. 指標間の関係(典型:ζ=0.6 の例)
| 指標 |
代表式 |
ζ=0.6, ω_n=5 rad/s の数値例 |
| 遅れ時間
(50%) |
数値計算 |
≈0.24 s |
| 立ち上がり時間
(10–90%) |
≈
|
≈0.42 s |
| ピーク時間
|
|
≈0.73 s |
| 整定時間
(±2%) |
|
≈1.33 s |
| 最大オーバーシュート
|
|
≈10% |
(ここで
,
)
6. なぜ複数必要か
| 指標 |
主な設計意図 |
| 遅れ時間 |
初期反応の速さ(センサ/アクチュエータ遅れ感) |
| 立ち上がり時間 |
目標に近づく速さ(立上り性能) |
| ピーク時間 |
振動性の周期尺度,オーバーシュートとの連携 |
| 整定時間 |
実用上「落ち着いた」とみなすまでの時間(安定収束速度) |
一つだけでは “速いが振動が大きい” などのトレードオフを把握できないため,複数を指定してバランスを図る。
7. 定義のバリエーションと注意
- Rise Time の百分率 は文献で差が大きい(0–100%, 5–95%, 10–90%)。仕様書で必ず明記。
- Settling Band も ±2% か ±5% を必ず明記。
- Delay Time は扱わない資料もある(代わりに“時間遅れ (time delay)”=輸送遅れ
と混同しないよう注意)。
- 高次系では “支配的 2 次モード” がある場合のみこれらの近似式が妥当。複数モードが同程度なら数値シミュレーションで直接測定する。
8. 設計への使い方(逆算例)
仕様例:
-
→
-
→
なら
.
→ これで極を
付近に配置する など。
9. “行き過ぎ時間” と “オーバーシュート” の違い
- 行き過ぎ時間 (ピーク時間
) は “時間”。
- オーバーシュート (最大オーバーシュート
) は “割合(高さ)”。
図ではピーク時刻が縦破線、縦位置が
。
10. まとめ(要約)
| 用語 |
記号 |
代表的定義 |
2 次系代表式 |
| 遅れ時間 |
|
0→50% 到達時間 |
(求め方は式代入 / 数値) |
| 立ち上がり時間 |
|
10→90% 上昇時間 |
近似 |
| 行き過ぎ (ピーク) 時間 |
|
最初の最大値に到達 |
|
| 整定時間 |
|
±α% バンド内定着 |
(2%),
(5%) |
さらに「各式の導出過程が見たい」「任意の ζ と ω_n で値を計算したい」「高次系の場合の測定手順」などあれば続けてどうぞ。どこを深掘りしますか?
 答え:⑤
答え:⑤