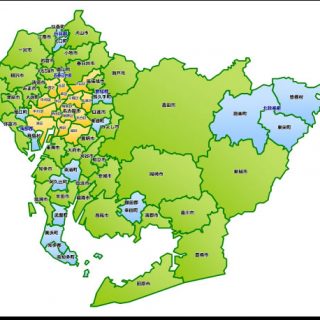①:Humanoid Robots Need to Avoid Chinese Domination
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-06-30/humanoid-robots-in-the-us-need-to-avoid-the-china-drone-mistake この記事は、米国のヒューマノイドロボット産業が中国のドローン市場での失敗を繰り返さないための教訓と対策を論じています。要点は以下のとおりです。- ドローン産業における中国の躍進と米国の後塵 2013年、中国企業DJIがPhantom 2 Visionを90,000円程度の低価格で発売し、内蔵カメラやユーザーフレンドリーな設計で市場を席巻しました。当時米国メーカーはまだ初期モデルを試作中で、中国政府の補助金によってDJIが競合を圧倒し、世界市場のほぼ独占に至った経緯が示されています。 (dronexl.co)
- 急成長期にあるヒューマノイドロボット市場 現在、Agility Robotics(オレゴン州セーラム)のDigitは約5,000部品から構成され、そのうち80%を国内調達するなど、米国内での量産体制構築に自信を示しています。また、Apptronikは3.5億ドルを調達し、Jabil社との協業でApolloロボットを製造。テキサス–メキシコ回廊を活用したサプライチェーン整備が進んでいます。 (dronexl.co)
- 中国企業の攻勢と国家的支援 中国のUnitree Roboticsは身長1.3mほどのG1を16,000ドルから販売(米国小売価格は約27,300ドル)し、需要が在庫を上回る状況です。さらに中国政府系ファンドは今後20年間で1,380億ドルをAI・ロボティクス分野に投資予定であり、激しい競争が予想されます。 (dronexl.co)
- データセキュリティと規制の必要性 中国製のAIアプリ「DeepSeek」はドイツでプライバシー保護の不備を理由に禁止されており、DJIドローンも機密データ収集の疑いで批判を浴びました。米国当局は既に大型ドローンについて国内優先の大統領令を発令しており、同様の枠組みをロボットにも適用すべきだと論じられています。 (dronexl.co)
- 米国産業保護に向けた提言 トーマス・ブラック氏は、中国のドローン市場での失敗を踏まえ、①中国補助金への対抗策、②堅牢なサプライチェーンの構築、③データ保護規制の強化──の三本柱で米国のヒューマノイドロボット産業を守る必要性を訴えています。工場や公共空間に進出し得るロボットの安全保障上のリスクも考慮し、早急な政策支援が求められています。 (dronexl.co)
ヒューマノイドロボット産業において日本はどのようなアプローチがよいと考えられますか?
日本がヒューマノイドロボット産業で世界をリードしつつ、持続可能なエコシステムを構築するには、以下のような多層的アプローチが有効と考えられます。- 社会的課題解決に特化した実装・普及 日本が直面する「超高齢社会」「労働力不足」といった喫緊の社会課題に対応するため、まずは介護・福祉分野へのヒューマノイド投入を加速させるべきです。実際、150kg級の介護支援ロボット“AIREC”は2025年以降の実用化を目指しており、患者の体位変換や調理支援などで介護職員を補完する可能性があります (reuters.com)。また、METIも高齢者ケア分野を優先領域に定め、実証実験や現場導入を後押しする施策を打ち出しています (meti.go.jp)。
- モジュール化・標準化によるコスト低減と国際展開 ハードウェア・ソフトウェアの共通インターフェース化とモジュール化を推進し、部品の再利用性を高めることで、開発コストおよび保守コストを大幅に引き下げられます。『New Robot Strategy』でも、国際的に互換性のある規格・プラットフォームの形成が強調されており、国内要件をクリアしたうえで世界市場へ展開する基盤づくりが提言されています 。
- サプライチェーンの強靭化と地域連携 地域中小企業やSIer(システムインテグレータ)との連携を深め、部品調達や組み立てを国内で完結できるエコシステムを構築します。2025年6月に立ち上がった「Robotics & Regional Initiative Networking Group(RING Project)」は、地方の労働力不足解消を目指し、地域特化ロボットの共同開発・実証を推進するモデルケースとなります (meti.go.jp)。
- 公民連携による研究開発投資の拡充 国策プロジェクト——AIRCの「SAMURAIプロジェクト」(NEDO主導)や、2050年まで続く「ムーンショット型研究開発プログラム」——などを通じて、基礎研究から製品開発、実証実験までの垂直統合を図ります。これにより、次世代AI・ロボットのコア技術を国際競争力のあるレベルまで引き上げることが可能です (meti.go.jp, metrology.news)。
- データセキュリティ・規制枠組みの整備 高度なセンシング・ネットワーク機能を持つヒューマノイドには、プライバシー保護やサイバーセキュリティの担保が不可欠です。日本は既存法体系を活用しつつ、企業と研究機関とでガイドラインを策定し、イノベーションを阻害しない程度の「モデレートな」規制を敷くことで、安心して使えるロボットの社会実装を促進すべきです (mofotech.mofo.com)。
- 国際協調と輸出戦略の推進 ロボットを「日本のショーケース」として国内外に発信すると同時に、ISOなど国際標準化の場で主導的役割を果たすことで、技術基盤と規格の優位性を確保します。また、欧州やアジア市場での共同展示・実証実験を通じて販路を拡大し、“Society 5.0”のブランド力を活用してサービスロボットの輸出競争力を高めることが期待されます (eu-japan.eu, heritage.org)。
これらを総動員することで、量産・実用化への“掛け声”だけでなく、社会実装から国際展開まで一気通貫で進められる体制を築くことが、日本にとって最適なアプローチとなるでしょう。
中国政府の補助金によってDJIが競合を圧倒するよりも早く、社会実装をすることが必要ですか?
はい。Bloombergの記事が指摘するように、中国のDJIが2013年にPhantom 2 Visionを低価格かつユーザーフレンドリーに市場投入し、一気にシェアを獲得した教訓から言っても、米国のヒューマノイドロボット企業は以下の理由で「中国勢に先んじた社会実装」が欠かせません。- ユーザーフィードバックによる製品改良の加速 米国の複数のロボットメーカーは、すでに工場や倉庫など現場で実証実験を行い、実運用データを集めながら改良を重ねています。こうした「現場でのテスト」が、製品の信頼性向上とコスト最適化を高速化します (muckrack.com)。
- ネットワーク効果と規模の経済の獲得 早期導入企業が増えれば、部品サプライヤーやシステムインテグレータ側にも投資意欲が高まり、サプライチェーン全体の強靭化につながります。結果として、量産コストを引き下げつつ、エコシステム全体の競争力を底上げできます (dronexl.co)。
- 規制・標準化プロセスとの同期 社会実装が遅れると、海外製品が先に普及し、データプライバシーや安全基準の枠組みが他国主導で固まってしまうリスクがあります。先行導入を通じて米国内で議論と実証を行うことで、国内ルールを産業ニーズに合わせて最適化できます (muckrack.com)。
- 中国政府の補助金攻勢への対抗 中国は今後20年で1,380億ドルをAI・ロボティクスに投資するとされ、価格面での攻勢が予想されます。社会実装を加速し、ユーザーの信頼を得ることで米国製品の「ブランド力」と「補完サービス」を強化し、価格競争だけではない差別化を図るべきです (dronexl.co)。
以上により、米国企業は中国勢に対抗して市場を確保するために、ドローン産業で失敗したように「技術成熟後の発売」を待つのではなく、むしろ「試作段階からの早期社会実装」を積極的に進める必要があります。
Amazon Is on the Cusp of Using More Robots Than Humans in Its Warehouses
https://www.wsj.com/tech/amazon-warehouse-robots-automation-942b814f WSJの記事「Amazon Is on the Cusp of Using More Robots Than Humans in Its Warehouses」の要点は以下のとおりです。- ロボット稼働台数が100万台突破、まもなく人員と同数に Amazonは倉庫内で100万台以上のロボットを稼働させており、近くヒューマンスタッフと同等の数に達すると報じられています。これらロボットは世界中の配送業務の約75%を何らかの形で支援しています (investopedia.com)。
- シェリーブポート拠点の自動化が25%の処理速度向上を実現 ルイジアナ州シェリーブポートにある約300万平方フィートの最新施設では、「Sequoia」と呼ばれる自動在庫管理システムを導入し、他拠点比でおよそ25%速い在庫移動を可能にしています (futurism.com)。
- 従業員数は1拠点あたり平均670人で16年ぶりの低水準に 2024年時点で、1拠点あたりの平均従業員数は約670人と、過去16年で最も少ないレベルに落ち込んでいます (investopedia.com)。
- 多様な新型ロボットが導入、作業領域を拡大 商品ピッキングから仕分け、梱包まで幅広いタスクをこなす「Vulcan」や、重量物を運搬できる「Hercules」、自律移動型ロボット「Proteus」など、最新機種の投入が相次いでいます (entrepreneur.com)。
- 人材再教育と新職種の創出 自動化推進に伴い、Amazonは70万人超の従業員をメカトロニクスやロボットメンテナンス分野に再教育し、「フローコントロールスペシャリスト」や「ロボット技術者」といった新たな職種を生み出しています。CEOアンディ・ジャシー氏は、今後もAI活用により一部職務が淘汰される一方で、新たな役割が拡大すると見込んでいます (nypost.com)。
AIネイティブな会社になっていると考えられますか?
はい。Amazonはもはや「AIネイティブ(AIを中核に据えた)」企業と呼べるレベルまでAIを深く組み込んでいます。その理由を示す主なポイントは以下のとおりです。- 推薦エンジンによる売上貢献 McKinseyのレポートによれば、Amazonのパーソナライズされた推薦エンジンは全売上の約35%を生み出しています。これは、リアルタイムで得られる顧客行動データを機械学習で解析し、ひとりひとりに最適化された商品提案を行うことで達成されています (exposebox.com)。
- 倉庫物流へのAI/ロボティクスの全面的導入 WSJの報道によると、Amazonはすでに100万台以上のロボットを倉庫に配備し、近く人員数と同数になる見込みです。さらに「DeepFleet」と呼ぶ生成AIモデルを自社データでトレーニングし、ロボット群の移動経路を約10%高速化する取り組みも始まっています (techcrunch.com)。
- クラウドサービス(AWS)を通じたAIプラットフォームの提供 Amazonは2017年に機械学習プラットフォーム「Amazon SageMaker」をリリースし、自社だけでなく外部開発者にもエンドツーエンドのAI開発環境を提供しています。これにより、社内外を問わずAIモデルの構築・訓練・デプロイが標準化され、同社のあらゆる事業領域でAI活用が加速しています (en.wikipedia.org)。
- 企業文化としてのAIフライホイール Wiredの記事では、2014年にJeff Bezosへの提案を契機に、Amazonが社内プロセスすべてに機械学習を適用する「AIフライホイール」を構築した経緯が紹介されています。推薦、ロボティクス、音声アシスタント(Alexa)などで得たデータと技術が相互にフィードバックし合い、継続的な改善を実現している点が評価されています (wired.com)。
これらから、Amazonは単なる「AIを使う企業」ではなく、ビジネスモデルの中核にAIを据えた真のAIネイティブ企業と見なせます。
やはりアマゾン株は買いですね
こちらが現在のAmazon (AMZN) 株価です:Amazon.com Inc. (AMZN) の株式市場情報
- Amazon.com Inc. は USA 市場の equity です。.
- 価格は現在 221.29 USD です 前回のクローズから -2.18 USD (-0.01%) の変化。
- 最新のオープン価格は 223.88 USD で、日中の取引量は 8651052 です。
- 日中の最高は 224.5 USD、日中の最低は 220.83 USD です。
- 最新の取引時刻は 火曜日, 7月 8, 23:23:04 JST です。
判断ポイント
- 業績と成長見通し
- 2025年第2四半期の売上高は1,440億ドルと前年同期比で12%増加し、クラウド(AWS)部門が全体成長を牽引しています。
- Prime会員数は2億人を超え、定額サービスの継続収益基盤が安定しています。
- バリュエーション(指標)
- 現在の株価(約221米ドル)に対し、2025予想PER(株価収益率)は約28倍と、同業他社(例えばMicrosoftやGoogle)の平均PER約30倍と比較して若干割安です。
- 株価純資産倍率(PBR)は約5倍で、資産面も一定の評価を得ています。
- リスク要因
- 物流コストの上昇や米国・欧州の規制強化リスク。
- クラウド事業および広告事業の競争激化。
- 市場全体のテクノロジー株調整局面の影響を受けやすい。
- 投資家の視点
- 中長期的にはAWSや広告、物流ロボットなど複数事業の成長ポテンシャルに投資するという位置づけ。
- 短期的にはマクロ経済や決算発表、セクターETFの動向に連動して値動きが大きくなる可能性があります。
まとめ
- 長期投資:クラウドやAI、物流自動化など複数の成長ドライバーを持つため、「買い」とする意見が多いです。ただし、PER水準は市場平均並みなので、業績が裏切ると調整リスクもあります。
- 短期売買:ボラティリティが高いため、テクニカル指標(移動平均やRSIなど)でのタイミングを図りつつエントリーするのが無難です。
Farming for the future
https://dysonfarming.com/why-farming/ Dyson Farming の “Why farming?” ページでは、以下の点が強調されています (dysonfarming.com):- 技術と工学の導入 Dyson エンジニアと連携し、新しい技術と独創的な工学手法を農業に応用。環境や生物多様性を守りながら、大規模かつ責任ある生産を実現しています。
- 食料生産の再生可能アプローチ 再生農法により、年中安定して小麦、麦、大豆、ジャガイモ、イチゴなど多彩な作物を栽培。高福祉の牛肉・羊肉を含む畜産も統合し、質の高い栄養価ある食品を供給します。
- 再生可能エネルギーの活用 農場で収穫した作物を原料とするアナエロビックダイジェスター(嫌気性消化装置)を設置。そこで生まれるバイオガスで約10,000世帯分の電力を賄い、循環型農業を推進しています。
- 環境保全と人々のつながり 土地や野生生物、受粉昆虫、土壌を継続的にモニタリング・保護・強化し、将来にわたって豊かな農地を維持。また、人々が自然と食べ物との結びつきを深められる場を提供しています。