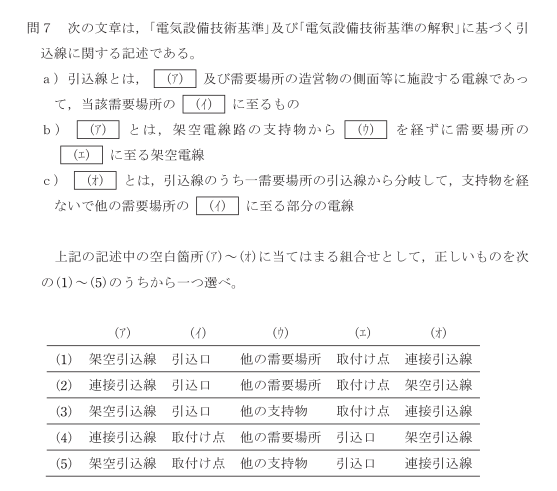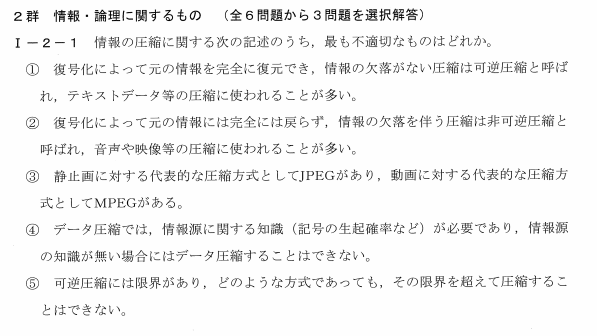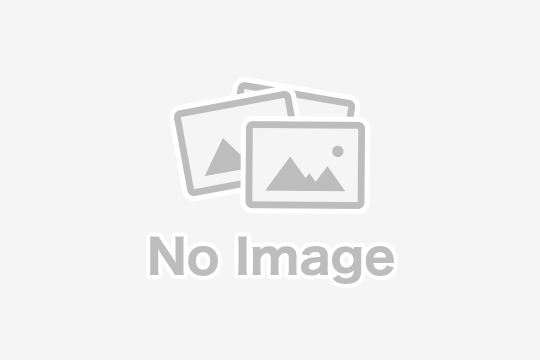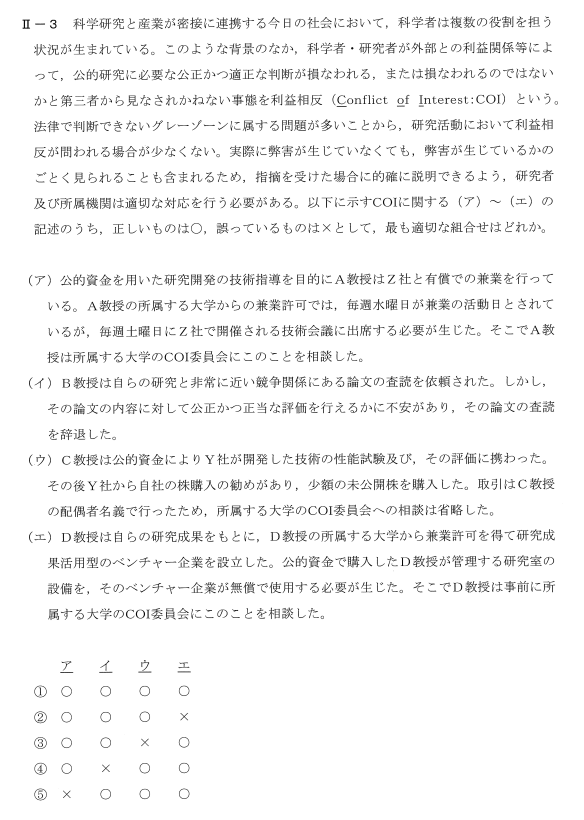【テクノロジーの教科書】IT大手がゲームに参入する理由
これまでゲームはソフトウェアを店頭やウェブサイトなどで購入して、それを専用の機器や高性能なパソコンを使って遊ぶのが当たり前でした。
ゲームはコントローラーからの入力を処理し、人間がストレスを感じない速度でその結果をビジュアルに反映させる必要があります。
特に最近はリアルさを追求するため、引力や空気抵抗などの物理現象をシミュレートしたり、流麗な3次元グラフィックスを処理したりするため、かなり大掛かりな計算処理が必要です。
ゲームの見栄えの良さは、ゲーム機の処理能力の高さに依存してきました。
同じメーカーの製品、例えば「ファミリーコンピュータ」から今のニンテンドースイッチに至るまでのゲームの進化を見れば納得していただけるでしょう。
一方で動画配信の進化を思い起こしてください。
以前は磁気テープのVHSや、DVDブルーレイ・ディスク(BD)などのメディアをレンタル店から借りてきて、専用の機器で再生するのが主流でした。
しかし今は光ファイバーの普及などもあってインターネットが高速化し、専用再生機器がなくてもブルーレイと同等の高画質の映像が配信できるようになりました。
「ネットフリックス」など動画ストリーミング配信が普及し、レンタル店は縮小の一途です。
ゲームは基本的にはこのストリーミングにコントローラーの入力が反映されればよいわけです。
そこでスタディアでは、最新ゲーム機器である「PS4プロ」や「Xbox One」を凌駕する処理をクラウドで実現しました。
半導体メーカーの米AMDと共同開発したグラフィックスチップを採用しています。
このようなクラウドサービスは米マイクロソフトや米エヌビディアも力を入れているところです。
グーグルはゲームの遅延については既存のデータセンターのほかに、消費者に近い場所にミニサーバーを設置すると明らかにしました。
物理的な距離による遅延を少なくするためです。
昔から米国で光ファイバー事業も手掛けていたグーグルだからこそできる取り組みだと思います。
この点はマイクロソフトが開発した「xクラウド」よりも踏み込んだ設計内容になっています。
グーグルはコンテンツの充実はもちろん、ユーチューブのゲーム映像からユーザーを誘導するなど、サービスへの導線にも力を入れています。
ゲームが好きな人にとってはいいゲームをプレイしたいという欲求があり、クラウドの処理能力がゲーム機の性能を超えてきたタイミングで消費者が移るのだろうと考えているのでしょう。
もちろん、ストリーム配信するゲームにはデメリットがあります。
例えば新幹線でトンネルを通るときなど、高速通信が維持できない環境ではゲームが途切れてしまいます。
ただクラウドなら中断される前の数分間のゲームの状態は自動的に保存されているため、1人用のゲームならば問題なく再開できるでしょう。
このタイミングでグーグルがゲームのストリーミング配信に乗り出した背景には、5Gがあるのは間違いないでしょう。
同じゲームを家の中でも外でも遊びたいというニーズには、高速かつ低遅延の5Gが必須の技術です。