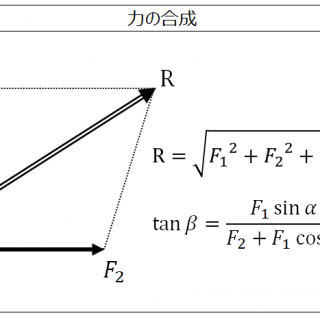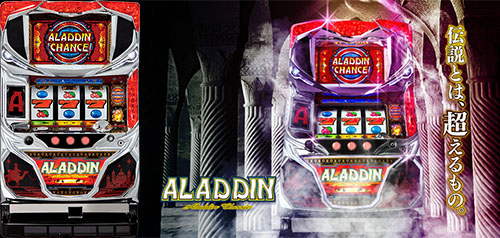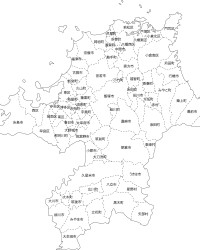- トラック販売からサービス事業へ: テスラセミトラックを単に販売するのではなく、自律走行型トラックサービスを自社で運営することで、より大きな利益を生み出すことができると動画は示唆しています [
02:13 - 巨大な市場の可能性: 世界のトラック輸送市場は数兆ドル規模であり [
00:45 02:47 - 財務予測: 動画で言及されている情報源によると、自律走行型トラック1台あたり、年間約40万ドルの利益を生み出す可能性があります [
02:54 02:59 - 従来のトラック輸送に対する利点: 自動運転トラックには、人間が運転するトラックに比べていくつかの利点があります。
- ロボタクシーとの比較: 話し手は、自律走行型トラック事業はロボタクシー事業よりもはるかに有望な機会であると考えています [
02:23 07:46 07:55
【未来予測】TESLAの本命は“ロボトラック”だった!? イーロン・マスクは「眠れる2兆ドル市場」を切り拓けるか【中島聡】
- 更新日:
- 公開日:
この動画は、テスラの自律走行型トラック事業(「ロボットラッキング」)の巨大な可能性について論じています。
主なポイントは以下の通りです。