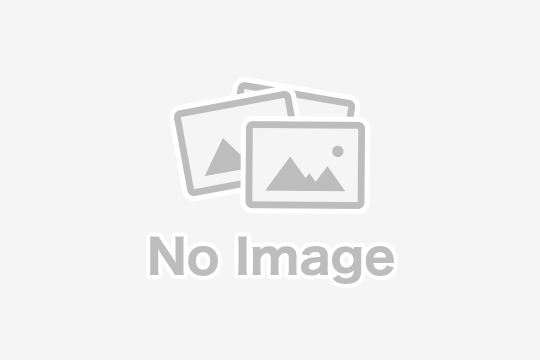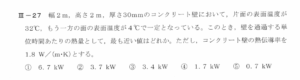
はい。定常熱伝導でフーリエの法則を使います。
与えられた値
- 面積:
- 温度差:
- 厚さ:
- 熱伝導率:
熱流束(単位時間あたりの熱量)
答え
①
6.7 kW
参考:
熱伝 | 副業の宮殿【PR】
技術士第一次試験-令和2年度機械部門Ⅲ-27解答例 | 技術士のたまご
フーリエの法則を教えてください
わかりました。
フーリエの法則は、熱がどのように物質内部を伝わるか(熱伝導)を定量的に表した基本法則です。
1. 定式化(微分形)
-
:単位面積あたりの熱流束ベクトル(熱の流れるエネルギーの密度、単位:W/m²)
-
:熱伝導率(物質固有の係数、単位:W/(m·K))
-
:温度勾配ベクトル(K/m)
- マイナス符号は「熱は高温から低温へ流れる」ことを反映している(温度が高い側から低い側へ向かう方向が熱流の向き)。
例:1次元(x方向)で温度が
と変化するとき、
これは単位面積当たりの熱の流れ(W/m²)を与える。
2. 積分形(定常・定厚さ・定熱伝導率のとき)
厚さ
、断面積
、両端の温度差
に対して、定常状態なら:
-
:単位時間あたりの全熱流量(W)
- これを「熱抵抗」で書くと:
は伝導による熱抵抗(K/W)。
3. 多次元・異方性
一般の三次元ではフーリエの法則はテンソル形も取り得る(異方性材料):
ここで
は熱伝導率テンソル(方向によって異なる伝導性を持つ材料向け)。
4. 連続の式と熱方程式
エネルギー保存と組み合わせると、温度の時間変化を含む**熱拡散方程式(熱方程式)**が得られる:
-
:密度
-
:定圧比熱
-
:体積あたりの内部熱生成(W/m³)
5. 境界条件の例
- ディリクレ条件(温度指定):境界の温度が既知(例:片面が一定温度)。
- ノイマン条件(熱流束指定):境界を通る熱流が既知。
- 対流(ニュートン冷却):境界と外部流体との熱交換がある場合、
:熱伝達係数(W/(m²·K))、外部温度
。
これを伝導と連成すると表面での全合成抵抗が出てくる。
6. 仮定と適用範囲・限界
- 連続体近似:物質が微視的に連続とみなせるスケール(原子スケールより大きい)。
- 拡散型伝熱:熱運搬が粒子のランダムな振る舞いに支配される(非弾道的)。ナノスケールや極低温ではフーリエの法則が破綻し、ボールスティック輸送など非古典的挙動が出る。
- 定常 / 非定常:積分形は定常かつ
、ジオメトリが一定のとき簡単に使えるが、時間変化や温度依存
がある場合は偏微分方程式を解く必要がある。
7. 類似性(他の拡散法則との対応)
- フィックの法則(物質拡散):
(濃度勾配に比例)
- オームの法則(電流):
(電場に比例)
フーリエの法則はこれらと同型構造(勾配→流れ)を持つ。
8. 実例(前の問題と同じ)
コンクリート壁(面積
、厚さ
、温度差
、熱伝導率
)に対して:
必要なら、非定常の場合の温度分布の時間発展(熱拡散方程式の解)、複合壁(多層)の熱抵抗の合成、数値解法の手法(有限差分など)も出せます。どれを深掘りしますか?
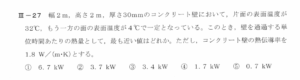 はい。定常熱伝導でフーリエの法則を使います。
はい。定常熱伝導でフーリエの法則を使います。