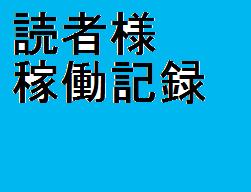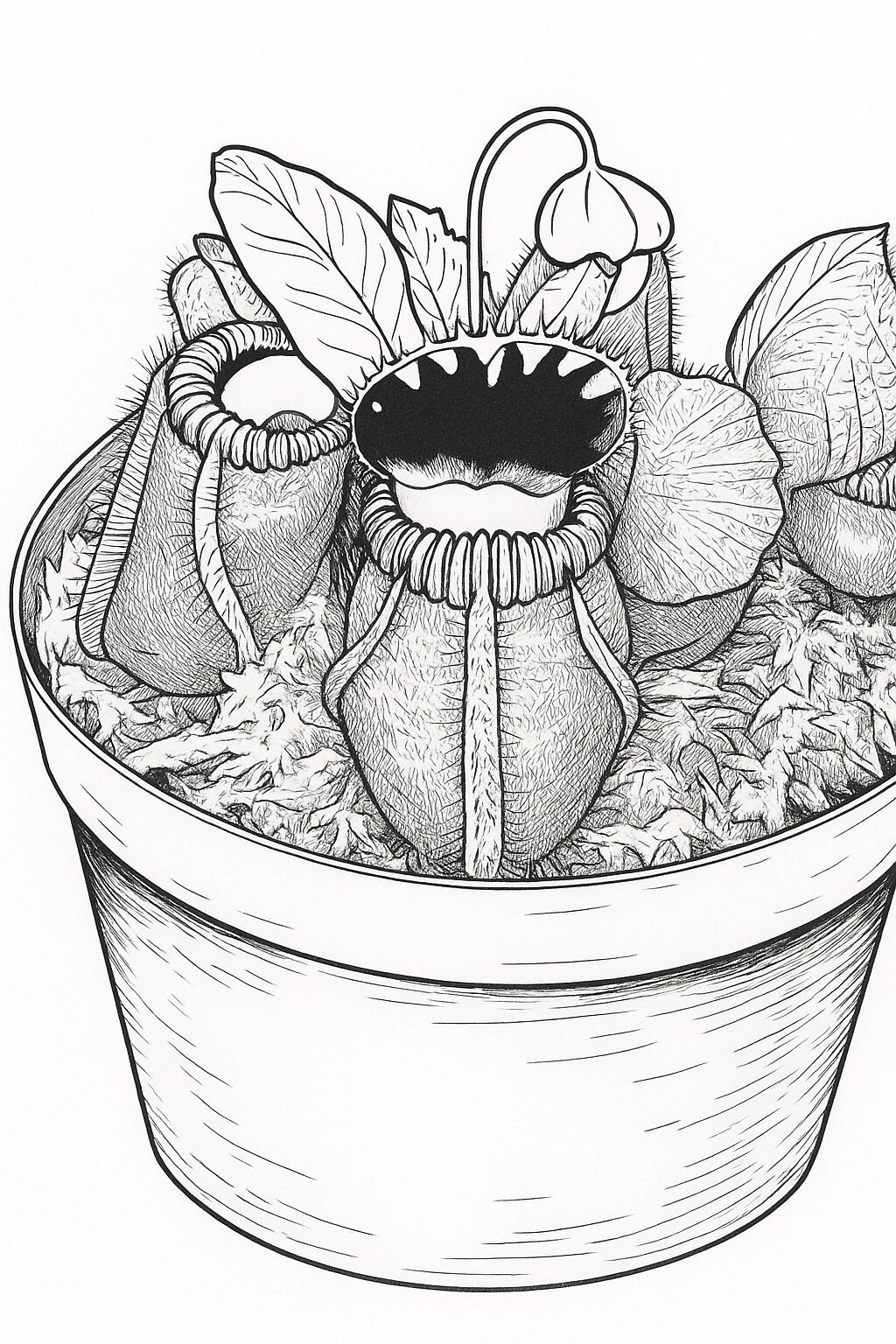プロ公式戦で使われた囲い(2020~2024年)
過去5年間のプロ棋戦では、穴熊囲いの強さが際立ちました。特に居飛車側が振り飛車に対抗するときに用いる居飛車穴熊は「振り飛車の天敵」と評され、藤井聡太などトップ棋士が採用すると無類の勝率を誇りました (藤井聡太棋聖が順位戦B級2組3連勝! 強すぎる藤井穴熊、組めば必勝!?|将棋情報局)。一方、振り飛車側の定番である美濃囲い系統も依然使用頻度は高く、機動力と安定感で評価されています。以下、主要な囲いの使用状況と勝率、代表的な棋士や戦型との関係を整理します。居飛車穴熊 – 振り飛車キラーの堅陣
- 使用頻度・勝率: 振り飛車対策として最有力の囲いで、この5年も対抗型の主流でした。プロの対抗形(居飛車 vs 振り飛車)対局では穴熊が圧倒的に多く、他の囲い(エルモ囲い、舟囲い等)は限定的です (対振りでのエルモ囲い、船囲い、金無双だとプロの使用率はどの辺が高いので... - Yahoo!知恵袋)。藤井聡太は振り飛車相手に居飛車穴熊で 14戦全勝(勝率100%) と驚異的な数字を残しており (藤井聡太棋聖が順位戦B級2組3連勝! 強すぎる藤井穴熊、組めば必勝!?|将棋情報局)、羽生善治も居飛車穴熊の勝率が高いことで知られます (藤井聡太棋聖が順位戦B級2組3連勝! 強すぎる藤井穴熊、組めば必勝!?|将棋情報局)。穴熊同士の相穴熊となった場合は互角ですが、長期戦になりやすく、決定打を与えにくい展開になります (藤井聡太六冠が「穴熊囲い」 タイトル戦では初めて 師匠が語る「藤井穴熊」とは) (藤井聡太六冠が「穴熊囲い」 タイトル戦では初めて 師匠が語る「藤井穴熊」とは)。
- 代表的な使用棋士: 藤井聡太の穴熊は「藤井穴熊」とまで呼ばれ、師匠の杉本昌隆八段は「非常に攻撃的な穴熊」であり、囲いの金銀ですら攻撃に転用する独特の指し方だと解説しています (藤井聡太六冠が「穴熊囲い」 タイトル戦では初めて 師匠が語る「藤井穴熊」とは)。また豊島将之、羽生善治ら居飛車党のトップ棋士も対振り飛車戦で愛用しました。振り飛車党でも菅井竜也などは自陣穴熊(振り飛車穴熊)で居飛車穴熊に対抗することがあり、2023年王将戦や叡王戦では藤井vs菅井で双方穴熊に組む相穴熊の熱戦も生まれました (藤井聡太六冠が「穴熊囲い」 タイトル戦では初めて 師匠が語る「藤井穴熊」とは) (藤井聡太六冠が「穴熊囲い」 タイトル戦では初めて 師匠が語る「藤井穴熊」とは)。
- 有利となる戦型・局面: 振り飛車戦における居飛車穴熊は極めて有力で、「居飛車穴熊は振り飛車の天敵」とまで言われます (藤井聡太棋聖が順位戦B級2組3連勝! 強すぎる藤井穴熊、組めば必勝!?|将棋情報局)。振り飛車側の速攻を凌ぎきれば堅陣が活き、終盤の逆転を許しにくいのが勝率の高さに直結しています。逆に相居飛車戦では穴熊は滅多に出現しません(相手も急戦策を採りやすいため)。ただし持久戦志向の将棋ではごく稀に双方が穴熊に組むケースもあり、その場合は「じっくりとした戦い」になりがちです (藤井聡太六冠が「穴熊囲い」 タイトル戦では初めて 師匠が語る「藤井穴熊」とは)。
- 評価・解説: 解説者の間でも居飛車穴熊の堅牢さは高く評価されています。実際、藤井棋聖の公式戦での居飛車穴熊採用時の勝率は驚異の100%で「組めば必勝!?」とも称されました (藤井聡太棋聖が順位戦B級2組3連勝! 強すぎる藤井穴熊、組めば必勝!?|将棋情報局)。その堅さゆえ「大駒を渡しても簡単には攻略されない」のが最大の利点であり (藤井聡太六冠が「穴熊囲い」 タイトル戦では初めて 師匠が語る「藤井穴熊」とは)、攻めあぐねる展開に持ち込めれば勝利に直結するとみられています。棋士からも「穴熊に組まれてしまうと潰すのは容易でない」との声が多く、居飛車穴熊の評価はこの5年間不動のものがありました。
美濃囲い・銀冠 – 振り飛車の伝統と堅実さ
- 使用頻度・勝率: 美濃囲いは振り飛車党の基本形として依然最多クラスの採用率です。対抗形では振り飛車側の多くが美濃系統(ノーマル美濃、高美濃、銀冠など)に組み、速攻とバランスを両立しています。美濃囲い自体の勝率は相手の戦法次第ですが、穴熊相手では持久戦になると不利とされ、居飛車穴熊 vs 振り飛車美濃の組み合わせでは終盤に囲いの堅さの差が出てしまう傾向があります (藤井聡太棋聖が順位戦B級2組3連勝! 強すぎる藤井穴熊、組めば必勝!?|将棋情報局)。それでも、美濃は組み上げのスピードが速く攻めにも転じやすいため、対穴熊でも中盤までに主導権を握れば十分勝機をつかんできました。例えば振り飛車名手の鈴木大介九段は美濃から発展させた銀冠を構築し巧みに攻めましたが、藤井棋聖の穴熊を崩しきれず完敗した例があります (藤井聡太棋聖が順位戦B級2組3連勝! 強すぎる藤井穴熊、組めば必勝!?|将棋情報局)。総じて、振り飛車側が穴熊以外を用いた場合、居飛車穴熊側の勝率が6~7割とやや高い傾向にあります (四間飛車 shogidata.info) (四間飛車 shogidata.info)。
- 代表的な使用棋士: 振り飛車党の大半が美濃囲いを指しこなします。藤井猛九段や鈴木大介九段といったベテラン振り飛車党は美濃~銀冠の使い手として有名です。女流トップの西山朋佳も四間飛車美濃の名手です。また振り飛車転向組では、タイトルホルダー菅井竜也八段が三間飛車穴熊を志向しつつ、美濃や高美濃も柔軟に使い分けています。居飛車党でも相振り飛車戦になれば美濃囲いに組むケースがあり、近年台頭した若手振り飛車党(例えば古賀悠聖五段 (向かい飛車対局一覧 shogidata.info))も美濃の安定感を評価しています。
- 有利となる戦型・局面: 美濃囲いは対抗形のみならず相振り飛車戦でも頻出します。相振りでは互いに自玉を美濃に囲う展開が多く、実質的に美濃 vs 美濃の戦いになることもしばしばです。その場合は「美濃は崩れにくい」という格言どおり我慢比べの展開になり、終盤まで大きな差がつかないまま持久戦となります。美濃囲いは端攻めに弱い側面がありますが、銀冠に発展させることで弱点補強が可能です。銀冠は美濃からさらに玉を深く入城させた形で、対急戦にも耐久力を発揮しました。特に四間飛車vs居飛車急戦のような将棋では、銀冠に組んで粘り強く戦うことで勝率を五分近くまで押し戻す展開も見られました (四間飛車 shogidata.info)。
- 評価・解説: 美濃囲いは「美濃は崩れにくい」との格言があるほど安定感が評価されています。解説者からも「まず美濃に囲っておけば序盤の不利は避けられる」といった趣旨のコメントが頻繁に聞かれます。また銀冠については「美濃の発展形で、攻め合いに強い囲い」と高評価です。もっとも、AI時代の研究により居飛車穴熊 vs 美濃の構図では居飛車有利が定跡化しつつあり、プロの間では振り飛車側も穴熊囲いを採用するケースが徐々に増えてきました (対振りでのエルモ囲い、船囲い、金無双だとプロの使用率はどの辺が高いので... - Yahoo!知恵袋)。それでも、スピード重視の将棋や相振り飛車では美濃・銀冠の信頼性は依然高く、5年間を通じて使用率トップクラスの囲いです。
矢倉囲い – 相居飛車の伝統戦法
- 使用頻度・勝率: 矢倉囲いは相居飛車戦で歴史的に最も有名な囲いですが、近年は採用率がやや下がりました。公式戦全体に占める矢倉戦の割合は直近では5%前後 (矢倉 shogidata.info)と少なく、AI研究の進展で「矢倉離れ」も指摘されています。それでも矢倉囲い同士の将棋(相矢倉)は依然として名勝負が多く、勝率も互角です。年度別に見ると、例えば2021年の矢倉戦は先手勝率45.9%:後手54.1%と若干後手有利、2022年は先手39.7%:後手60.3%と後手優勢でしたが (矢倉 shogidata.info)、2023年は先手46.4%:後手53.6%と戻しています (矢倉 shogidata.info)。このように統計上は年ごとにばらつきがあり、どちらか一方が明確に高勝率という状況ではありません(研究の深化で互角に収束)。
- 代表的な使用棋士: 矢倉囲いを得意とする棋士としては、渡辺明九段や佐藤康光九段などが挙げられます。渡辺九段はタイトル戦でも矢倉戦を何局も戦い抜いており、伝統的な「矢倉森下システム」を愛用しました。森内俊之九段や藤井猛九段といったベテランも相居飛車では矢倉を志向する傾向があります。また若手では上野裕寿五段など矢倉採用率の高い棋士もいます (矢倉 shogidata.info)。藤井聡太竜王名人は相居飛車では角換わり腰掛け銀などを選ぶことが多く矢倉戦自体は少ないものの、矢倉囲いそのものの有用性は認められており場面次第で採用しています。
- 有利となる戦型・局面: 矢倉囲いは典型的な相居飛車型(矢倉戦)で現れ、相手も同じく矢倉に組んでこそ真価を発揮します。双方が矢倉に囲った将棋は**「最も将棋らしい将棋」とも称され、攻防のバランスに優れた展開になります。ただし近年は、矢倉模様から途中で急戦策に転じる駆け引きも増えました。先手が矢倉を目指し後手が急戦策(▲4六銀速攻など)を採るケースや、逆に後手が矢倉を誘導するケースもあり、純粋な矢倉囲い同士の対局自体が減少傾向です (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。そうした中でもタイトル戦など長丁場では矢倉が選択されることがあり、深い研究を背景にした大熱戦**が繰り広げられました。
- 評価・解説: 矢倉囲いはプロ棋士から「理想的な陣形」と評価されてきました。玉の堅さと攻撃力の両立した陣形で、中盤以降に▲7七銀~▲6六歩型の厚みが終盤力を発揮します。ただAIによる新手発見により、矢倉戦の定跡は複雑化し評価値的にも先手有利とは言えなくなりました (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士) (矢倉 shogidata.info)。それでも、「矢倉で勝った将棋は内容が充実している」と言われるように、矢倉囲いでの勝利は高く評価されます。解説者からも「矢倉はロマン」「矢倉を制する者が将棋を制す」といった声が根強く、勝率以上に将棋ファンや棋士の間での評価が高い囲いです。
雁木囲い – 復活した新戦法の堅陣
- 使用頻度・勝率: 雁木囲いは2017年前後からプロ棋界で再注目された囲いで、この5年でも採用局が増えました (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。特に2020~2021年にかけて採用率が高まり (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)、「相掛かりや角換わりの合間に雁木を選ぶ」ケースが目立ちました (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。雁木は玉を囲いつつ角道・銀の活用を図る実戦的な囲いですが、序盤から一直線に雁木に組む作戦は勝率的にやや不利とされています (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。実際、いきなり雁木に組んだ将棋は、先手番・後手番問わず相手に有力な対策を許しやすく、統計的にも五分を下回る勝率に留まりました (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。一方、相手の出方を見てから雁木に構える作戦(例:先手が角換わり模様から雁木にシフトする、新型の後出し雁木)では健闘が多く、研究の裏付けがある場合は勝率も5割以上と実戦向きです (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。
- 代表的な使用棋士: 雁木囲い復興の立役者としては、永瀬拓矢九段や糸谷哲郎八段らが挙げられます。永瀬九段は早い段階から新型雁木を導入しタイトル戦でも採用しました。また渡辺明九段も角換わり腰掛け銀とのミックスで雁木を指すなど、トップ棋士が取り入れています (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。振り飛車党からも*「居飛車も指せる」タイプの棋士(例えば菅井竜也八段)が相居飛車の際に雁木を選ぶケースが増えました (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士) (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。こうした流れから*「雁木=実戦的で勝ちやすい囲い」**との評価が定着し、将棋AIの形勢判断でも一定の高評価を得ています。
- 有利となる戦型・局面: 雁木囲いは主に相居飛車戦で現れますが、特徴的なのは角換わりや相掛かりの途中から雁木に組み替える指し方です (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。これにより定跡形から外れ、自分の土俵に持ち込めるメリットがあります (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。また振り飛車党が居飛車に転じたときにも雁木を採用する傾向があり、振り飛車党に馴染み深い△4三銀型の形を活かせる点が理由とされています (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。雁木同士の相雁木もまだ未開拓の部分が多く、研究勝負になりやすいですが、その分詳しい側が有利です (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。総じて、相居飛車の変化球として雁木は有力であり、**「変化球だが今後も増える囲い」**との見方が強いです (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。
- 評価・解説: 解説者からは「雁木復権」として話題になりました。遠山雄亮六段は「いきなり雁木囲いを目指すのは先手に対応策が多く不利」だが、「工夫次第で今後も多く指されそう」と評しています (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士) (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。また「振り飛車党でも居飛車と同じ土俵で戦える新風」として高く評価する声もあります (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。実際プロの公式戦でも雁木で勝ち星を重ねた例が多々あり、勝率的にも増加傾向にあります (プロの居飛車 現在地 ー2021年3月ー|遠山雄亮/将棋プロ棋士)。ただし研究の浅い部分も残っており、一部では「未知の局面になりやすくリスクもある囲い」との指摘もあります。それでも雁木囲いはこの5年で確実に定着し、評価が急上昇した囲いと言えます。
その他の囲い – 新旧の工夫
- ミレニアム囲い: 2000年頃に登場しAI時代に再注目された対振り飛車囲いです。玉を右翼深くに据え金銀4枚で厚く囲うのが特徴で、隙の無さから一時大流行しました。2019年前後から若手や将棋ソフト発の新手を受けて再評価され、対振り飛車急戦策に対抗する囲いとして使われています (【ノーマル四間飛車(持久戦)】ミレニアム他 - 将棋備忘録)。近年は古賀悠聖五段が振り飛車ミレニアムの著書を出すなど、プロアマ問わず研究が進みました。ただ組み上がりに時間がかかるため急戦相手には不向きとも言われ (指され始めて日が浅く、これからに期待。ミレニアム(振り飛車 ...) (2000年ごろに指され始めた「ミレニアム囲い」の特徴と組み方を学 ...)、勝率は穴熊ほどではありません。それでも対抗形で穴熊以外を採用する場合の有力候補で、佐藤康光九段や羽生九段が指した例もあります (四間飛車対局一覧 shogidata.info) (四間飛車対局一覧 shogidata.info)。
- エルモ囲い: 将棋ソフト「Elmo」に由来する新囲いで、▲6八銀・▲7九金型の独特な陣形です。対振り飛車の早囲い策として2018年頃から注目され、ここ5年でも急戦志向の棋士が採用しました (対振りでのエルモ囲い、船囲い、金無双だとプロの使用率はどの辺が高いので... - Yahoo!知恵袋)。プロでは穴熊に比べ採用数は少ないものの、一部で流行しています (対振りでのエルモ囲い、船囲い、金無双だとプロの使用率はどの辺が高いので... - Yahoo!知恵袋)。たとえば阿部健治郎七段や及川拓馬七段が公式戦でエルモ囲いを試み勝利した例があります (elmo囲い shogidata.info) (elmo囲い shogidata.info)。勝率は五分前後ですが、舟囲いより堅く新機軸を出しやすい点が評価されました (対振りでのエルモ囲い、船囲い、金無双だとプロの使用率はどの辺が高いので... - Yahoo!知恵袋)。
- 金無双: 玉を真ん中に据え左右から金で挟む古典的囲いです。相振り飛車戦でお互いに金無双に組むことが多く、相振りでは標準的な囲いと言えます。一方で対抗形の居飛車側が使うことは少なく、プロでは「穴熊を使った方が実戦的」とされています (対振りでのエルモ囲い、船囲い、金無双だとプロの使用率はどの辺が高いので... - Yahoo!知恵袋)。実際この5年、居飛車側で金無双が現れる局面はごく稀でした(地下鉄飛車戦法など例外を除く) (対振りでのエルモ囲い、船囲い、金無双だとプロの使用率はどの辺が高いので... - Yahoo!知恵袋)。相振り戦での金無双同士の勝率は互角で、終盤まで大差が付かない堅実な囲いとして認識されています。
- 右玉(ミレニアム右玉含む): 玉を初期位置付近にとどめたまま戦う戦法で、囲いというより未囲い戦法ですが、一部の力戦派棋士が活用しました。例えば高田明浩五段の「高田流左玉」(相振り飛車で玉を左に囲わず戦う)が話題になったことがあります (【日本將棋】獅子王戰第一局(相振飛車對高田流左玉) - YouTube)。右玉は奇襲的な意味合いが強く、勝率もケースバイケースですが、囲いを省略して攻めに振り切るコンセプトが評価される場面もあります。ただし安定度では正統派の囲いに劣るため、長期戦には不向きでプロ公式戦では少数派でした。