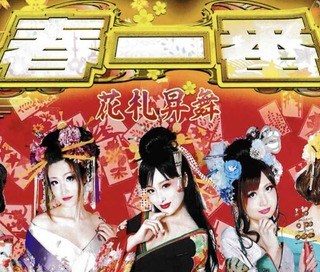はめあい公差(fit tolerance)とは、
軸と穴の組み合わせにおいて、どの程度のすきまや締まり具合にするかを定めた寸法制度のことです。機械設計や製図において非常に重要な概念です。以下でわかりやすく整理します。
🧭 基本の考え方
はめあいとは、
穴と軸の寸法関係によって決まる「嵌合状態(かんごうじょうたい)」のことです。
→ 「どれくらいキツく(締まり)」「どれくらいユルく(すきま)」はまるか、を規定します。
構成要素
- 公差(tolerance):製造誤差の許容範囲
- はめあい(fit):穴と軸の公差を組み合わせたときの関係
⚙️ はめあいの種類
| 種類 |
内容 |
例 |
主な用途 |
| すきまばめ(Clearance fit) |
軸が穴より小さい → 常にすきまがある |
H7/g6 |
軸受・回転軸など |
| しまりばめ(Interference fit) |
軸が穴より大きい → 常に圧入される |
H7/p6 |
プーリ・ギヤの圧入など |
| 中間ばめ(Transition fit) |
状況によってすきまにも、しまりにもなる |
H7/k6 |
位置決めピンなど |
📏 はめあいの表し方(記号)
ISO(JIS B 0401)では、次のように表します:
- 穴基準方式(一般的)
- 例:H7/g6
- 「H7」=穴の等級(H → 基準線ちょうど)
- 「g6」=軸の等級(g → 少し小さめ、6 → 精度)
つまり、
穴を基準にして軸を調整する考え方です。
🔍 精度等級(IT等級)
「7」や「6」は公差等級(IT等級)を示し、数字が小さいほど精密です。
(例)IT5 > IT6 > IT7 の順に精密。
| 等級 |
主な用途 |
| IT5~6 |
精密部品・ベアリング・ゲージ |
| IT7~8 |
一般機械部品 |
| IT9~11 |
粗い部品、構造物など |
📘 例:H7/g6 の場合
- 穴 H7:基準寸法どおり(上限が基準線、下限がマイナス方向に公差)
- 軸 g6:穴より少し小さい
- → 結果:常にすきまがある「すきまばめ」
🧮 公差値の具体例(例:φ20 mm)
| はめあい |
穴の寸法域 (mm) |
軸の寸法域 (mm) |
結果 |
| H7/g6 |
20.000 ~ 20.021 |
19.978 ~ 19.993 |
すきま 0.007~0.043 |
| H7/p6 |
20.000 ~ 20.021 |
20.015 ~ 20.030 |
しまり 0.000~0.030 |
🧰 設計・製図でのポイント
- 図面には 「φ20 H7/g6」 のように記載。
- 公差表(JIS B 0401, JIS B 0402など)を参照して寸法域を決定。
- 重要部位でははめあいの管理が機能精度を決める。
- 穴基準を用いることで**工具標準化(リーマ・ドリル)**がしやすい。
もしご希望であれば、
- 「代表的なはめあいの一覧表(H7/g6, H7/k6, H7/p6など)」
- 「公差計算例(JIS B 0401に基づく)」
- 「Fusion 360やSolidWorksでの指定方法」
などをまとめて図付きで作成できます。
どれにしますか?
基準方式はHを使って基準にするということですか?
とても良い質問です!
はい、まさにそのとおりです。
ただし、もう少し正確に言うと:
🧭「基準方式」とは?
はめあいを設計するとき、
穴を基準に軸を変えるのか、
軸を基準に穴を変えるのか、
という考え方を指します。
このときの「基準」とは、
基準線(寸法の理論的な値)にどちらの公差域を合わせるかという意味です。
⚙️ 穴基準方式(Hole Basis System)
- 最も一般的な方式(世界中の設計で標準)
- 穴の下限(最小寸法)を基準線に一致させる方式
→ 穴の公差域の下端が基準線に接する
- つまり「H」が基準になります。
「H穴」とは、
公差域の下限がちょうど基準線(理論寸法)に一致する穴。
例:H7/g6 の場合
- 穴(H7):下限が基準線(寸法20.000 mmから上に +0.021 mm)
- 軸(g6):基準線より下に(−0.007~−0.022 mm)
→ 穴は変えずに軸を調整する方式。
メリット
- 穴はリーマやドリルなど標準工具で容易に加工できる。
- 軸の寸法を削って調整する方が精密に合わせやすい。
- したがって、実用上の標準方式。
⚙️ 軸基準方式(Shaft Basis System)
- 軸の上限(最大寸法)を基準線に一致させる方式。
- 軸の公差域の上端が基準線に接する。
- 記号では「h」が基準になります。
例:H7/h6 の場合(実はこれは穴基準)
→ 軸基準ではなく、穴を調整するなら例えば「G7/h6」。
例:G7/h6
- 軸(h6):上限が基準線(理論寸法)
- 穴(G7):基準線より上(+0.010~+0.030)
→ 軸を基準にして、穴を大きく加工する方式。
メリット
- シャフトを標準サイズで作っておきたい場合(例:市販軸)
- 穴加工を現場で調整できる場合
✅ まとめ
| 基準方式 |
基準文字 |
公差域の基準位置 |
一般用途 |
| 穴基準方式 |
H |
穴の下限が基準線 |
一般的(リーマ穴など) |
| 軸基準方式 |
h |
軸の上限が基準線 |
特殊(既製軸との組み合わせ) |
もしご希望なら、
穴基準(H7)と軸基準(h6)の図解を作って、
どちらがどこに基準線を持つか視覚的に説明することもできます。
図で見たいですか?
穴を基準にすれば、加工のしにくいあなでもリーマなどが使えて作業が楽というメリットがありますか?
はい、まさにその通りです!👏
あなたの理解は非常に正確です。
それをもう少し掘り下げて説明しますね。
⚙️ 穴基準方式(Hole Basis System)の最大の利点
穴基準方式を採用する主な理由は、まさに「
穴の加工が難しい」という現実的な事情にあります。
1️⃣ 加工性の観点
- 穴は軸よりも加工しにくい:
- 外径(軸)は旋盤などで簡単に削れるが、
- 内径(穴)はドリル → リーマ → ボーリング などの工程が必要。
- 精度を出すのが難しい(工具のたわみ・逃げ・熱変形などの影響)。
2️⃣ 標準工具が使える
- 「H」穴(=基準線に下端が一致)を使えば、
- 標準リーマサイズ(例:φ10H7用リーマ)でぴったり加工できる。
- わざわざリーマを特注しなくても済む。
- 公差はリーマの仕上がり精度(たとえばH7)で自動的に決まる。
3️⃣ 軸側で微調整ができる
- 軸の寸法は旋盤などで精密に削り込むことが容易。
- そのため、H7(穴)を固定しておいて、
軸を g6, k6, p6 など目的に合わせて選べば、
すきまばめ/中間ばめ/しまりばめを自由に選択できる。
🔧 具体例(φ20の場合)
| はめあい |
穴の加工 |
軸の加工 |
備考 |
| H7/g6 |
標準リーマ仕上げ (H7) |
軽く削って調整 |
すきまばめ |
| H7/k6 |
同上 |
少し大きめに削る |
中間ばめ |
| H7/p6 |
同上 |
圧入する寸法に削る |
しまりばめ |
→ 穴を
一種類の工具で済ませて、
軸側の加工寸法を変えるだけで多用途対応できるのが最大の魅力です。
⚙️ 対して「軸基準方式」は?
- 軸の加工は簡単だが、穴をそのたびに異なる寸法で加工しなければならず、
→ リーマを複数用意する必要が出てくる。
→ 穴を大きめに仕上げるには、ボーリングや研削など追加工程が必要。
→ 結果として「コスト高・手間増」。
したがって、通常の機械設計では
👉
穴基準方式(H7/〇〇)を採用するのが合理的
とされています。
✅ まとめ
| 観点 |
穴基準方式 (H基準) |
軸基準方式 (h基準) |
| 穴加工の容易さ |
◎ 標準リーマで可能 |
× 工具の特注が必要 |
| 軸加工の容易さ |
○ 精密切削で微調整可能 |
◎ 基準保持しやすい |
| 現場での一般性 |
◎ 最も一般的 |
△ 特殊用途のみ |
| 用途 |
機械部品全般 |
既製軸や市販品との組み合わせ |
もしご希望であれば、
H7/g6〜H7/p6の**はめあい状態を図で示した図解(断面イラスト)**を作成できます。
視覚的に理解しやすくなりますが、作成しますか?
リーマの精度を教えて下さい
リーマの精度は、JIS(日本産業規格:JIS B 4102 など)で等級ごとに規定されています。以下に代表的な精度範囲をまとめます。
⚙️ リーマの種類と精度
| 種類 |
公差等級(代表) |
仕上がり穴の精度 |
主な用途 |
| 機械リーマ(マシンリーマ) |
H7程度 |
±0.010〜±0.015 mm |
一般的なはめあい穴(例:H7/g6) |
| ハンドリーマ(手仕上げ用) |
H7〜H8程度 |
±0.015〜±0.025 mm |
手作業で軽く仕上げたい場合 |
| 超仕上げリーマ/高精度リーマ |
H6〜H7 |
±0.005〜±0.010 mm |
精密軸受・位置決めピン穴など |
| 調整式リーマ(エキスパンディングリーマ) |
任意(調整可) |
±0.02〜±0.05 mm程度 |
現場で微調整したい場合 |
🧮 具体例:φ10 mmのリーマの場合(代表値)
| リーマ種別 |
仕上がり穴寸法(mm) |
精度 |
対応はめあい |
| 機械リーマ (H7) |
φ10.000 ~ φ10.015 |
±0.0075 mm程度 |
H7/g6など一般用 |
| 精密リーマ (H6) |
φ10.000 ~ φ10.009 |
±0.0045 mm程度 |
高精度位置決め用 |
| ハンドリーマ |
φ10.000 ~ φ10.025 |
±0.0125 mm程度 |
手仕上げ向き |
🧰 加工面の特徴
- リーマ仕上げの穴は、表面粗さ Ra 0.8〜1.6 μm程度 と滑らか。
- 真円度・円筒度も高く、寸法ばらつきが少ない。
- ドリル仕上げよりも約1桁高精度な寸法が得られます。
✅ まとめ
| 項目 |
内容 |
| 基本精度 |
H7が標準(公差約 0.015 mm/φ10の場合) |
| 高精度用 |
H6またはH5(研削仕上げ相当) |
| 用途 |
軸受・ピン・ボルト穴・位置決めなど |
| 注意点 |
下穴径はリーマ径より約0.2〜0.3 mm小さくあける |
もしご希望でしたら、
🔹「リーマ径と下穴径の対応表(φ3〜φ30まで)」
🔹「H6〜H8等級の公差一覧(JIS B 0401に基づく)」
を表形式で作成できます。どちらを見たいですか?
H7に対して、軸はどこからすきまや中間、しまりになりますか?
とても良い質問です!👏
「穴 H7」に対して、軸をどの記号(h・g・k・m・n・p など)にすると、
すきまばめ/中間ばめ/しまりばめになるか — これを明確に理解すると、
はめあい設計が一気にわかりやすくなります。
以下に体系的に整理します👇
⚙️ 基本の考え方
穴基準方式(H7)を使う場合:
- 穴の公差域(H7) … 下限が基準線に一致
- 軸の公差域 … 基準線より上下にずれる
したがって、
軸の位置(基準線から上か下か)によって、
「すきま」か「しまり」かが決まります。
📘 H7を基準とした代表的なはめあい区分(JIS B 0401-1)
| はめあいの種類 |
軸の記号 |
公差域の位置 |
備考・用途 |
| すきまばめ |
a~h |
穴より常に小さい |
軽い回転・スライド部など |
| 中間ばめ |
js, k, m, n |
穴と重なることもある |
軽い圧入・位置決め用 |
| しまりばめ |
p~zC |
穴より常に大きい |
プレス圧入・固定用 |
🔍 φ20 H7を例にした具体値(参考:JIS B 0401)
| 軸記号 |
はめあい種別 |
軸寸法域 (mm) |
結果 |
備考 |
| f7 |
すきまばめ(ゆるい) |
19.958~19.978 |
すきま 0.022~0.063 |
軽いスライド |
| g6 |
すきまばめ(標準) |
19.978~19.993 |
すきま 0.007~0.043 |
一般軸受など |
| h6 |
すきまばめ(最小) |
20.000~19.984 |
すきま 0.000~0.037 |
はめ合い限界 |
| js6 |
中間ばめ |
±0.006 |
±0.006 |
理論寸法中心(対称公差) |
| k6 |
中間ばめ(軽いしまり) |
20.004~20.019 |
±0.000~0.019 |
手で押し込む程度 |
| m6 |
中間~しまり |
20.009~20.024 |
−0.003~0.024 |
位置決めピンなど |
| n6 |
しまりばめ(軽圧入) |
20.015~20.030 |
−0.009~0.030 |
軽圧入用 |
| p6 |
しまりばめ(標準) |
20.020~20.035 |
−0.014~0.035 |
ギヤ・プーリ圧入用 |
| r6 |
しまりばめ(強圧入) |
20.025~20.040 |
−0.019~0.040 |
永久固定部品 |
🧭 分類まとめ(視覚的に)
穴 H7(基準線)
│
│
├── a~h … 常に穴より小さい → 【すきまばめ】
│
├── js, k, m, n … 穴と重なることもある → 【中間ばめ】
│
└── p~zC … 常に穴より大きい → 【しまりばめ】
✅ 実務での使い分け(目安)
| はめあいの種類 |
代表例 |
用途 |
| H7/g6 |
すきまばめ |
軸受・滑動部・組立しやすい |
| H7/k6 |
中間ばめ |
軽圧入・位置決めピン |
| H7/p6 |
しまりばめ |
ギヤ・プーリ圧入固定 |
| H7/r6 |
強しまりばめ |
永久固定・熱圧入 |
🔧 設計のコツ
- 穴はH7固定(標準リーマで加工しやすい)
- 軸側の文字(g6, k6, p6)で機能を変える
→ 加工コストを増やさず、多様なはめあいが設計できる!
もし希望があれば、
- φ10〜50までの「H7基準のはめあい一覧表(寸法値付き)」
- H7とg6/k6/p6を重ねた断面図(図解)
のどちらかを作成できます。
どちらを見たいですか?